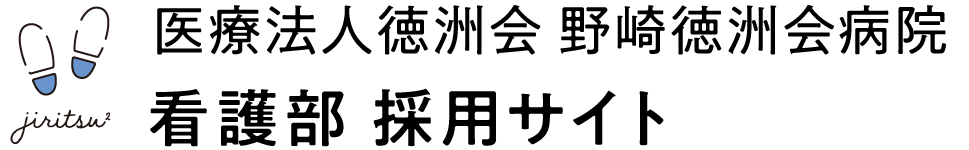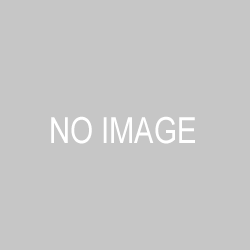Q.1
職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。(第106回)
①労働組合法
②労働基準法
③労働安全衛生法
④労働関係調整法
解答を見る
正解:3
- 労働組合法
労働組合法は自主的に労働組合を組織して団結することを擁護すること、使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすることおよびその手続きを助成するために必要なことを規定している。 - 労働基準法
労働基準法は最低の労働条件の基準を定めており、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない。さらにその向上を図るように努めるよう規定している。 - 労働安全衛生法
労働安全衛生法は職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としており、選択肢のなかで最も近い。 - 労働関係調整法
労働関係調整法は労働組合法とともに、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、または解決する法律である。
労働に関わる法律の目的を整理しておこう。
Q.2
労作性狭心症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。(第98回)
①低残渣の食事をとるよう心がける。
②ニトログリセリンを定期的に使用する。
③動いたら休む習慣をつけるよう心がける。
④入浴は42℃くらいのお湯で肩までつかる。
解答を見る
正解:3
- 低残渣の食事をとるよう心がける。
消化管の疾患ではないため、低残渣の食事をとる必要はない。便秘をしないような食事を心がける。 - ニトログリセリンを定期的に使用する。
ニトログリセリンは速効性があるため、胸痛発作時または胸痛発作が出そうだと感じたときに用いる。定期的に使用する薬剤ではない。 - 動いたら休む習慣をつけるよう心がける。
活動と休息のバランスが大切である。動いたら休む習慣をつけるよう指導することは適切である。 - 入浴は42℃くらいのお湯で肩までつかる。
熱いと感じる湯は血圧を上昇させるため心臓に負担がかかる。入浴は40℃以下のぬるま湯が望ましく、選択肢ではやや熱い。また、長時間の入浴も避けるように指導する。
労作性狭心症の患者の生活指導は再発防止のためにも重要である。病気自体を認識してもらったうえで、栄養の摂り方、運動の仕方、薬剤の管理方法、日常生活、飲酒の仕方、禁煙など生活全般に及ぶ指導が必要である。
Q.3
急性心筋梗塞で、緊急に左大腿動脈から経皮的冠状動脈内血栓溶解療法(PTCR)を受けた患者が、2時間後に「あおむけに寝ているから腰が痛い」と訴えた。穿刺部位からの出血はなく、バイタルサインは安定している。この時の対応で適切なのはどれか。(第97回)
①膝の屈伸運動を促す。
②穿刺部位の圧迫を除去する。
③腰部にバスタオルを入れる。
④ゆっくり側臥位になるよう促す。
解答を見る
正解:3
- 膝の屈伸運動を促す。
臥床状態で膝の屈伸運動をすれば、どうしても股関節を動かすことになる。これは穿刺部位を動かすことになり、出血の恐れがあるため適切ではない。 - 穿刺部位の圧迫を除去する。
腰痛に対して穿刺部位の圧迫を除去しても痛みがとれるとは考えにくい。 - 腰部にバスタオルを入れる。
腰部にバスタオルを入れることで腰痛の緩和になり、また穿刺部位を動かさずに挿入できるため適切である。 - ゆっくり側臥位になるよう促す。
側臥位になることで穿刺部位を動かすことになり、出血の恐れがあるため適切ではない。
大腿動脈を穿刺していることから、施術後は出血を誘発する行動をとらないことを考えると解答できる。
Q.4
40歳の男性。会社員。3年前の定期健康診査で徐脈を指摘されていた。3か月前から時折、めまいを感じることがあったが放置していた。本日、会社から帰宅途中に意識消失発作があり、アダムス・ストークス症候群の疑いで入院した。脈拍数32/分、血圧120/80mmHg。意識は清明。めまいを訴えている。入院時、イソプレナリン塩酸塩(β刺激薬)が投与された。患者に説明する内容で最も適切なのはどれか。(第96回改変)
①「熱が上がることがあります」
②「ドキドキするようなら教えてください」
③「排尿しづらくなったら教えてください」
④「物が二重に見えるので気をつけてください」
解答を見る
正解:2
- 「熱が上がることがあります」
イソプレナリン塩酸塩に体温を上昇させる作用はない。 - 「ドキドキするようなら教えてください」
イソプレナリン塩酸塩の副作用に動悸があるため、患者への説明としては適切である。 - 「排尿しづらくなったら教えてください」
イソプレナリン塩酸塩に尿閉の副作用はない。 - 「物が二重に見えるので気をつけてください」
イソプレナリン塩酸塩に複視の副作用はない。
イソプレナリン塩酸塩の薬効や副作用を知っていれば解答できる。高度な徐脈などに使用される薬剤である。よって心拍数を増加させる働きがある。副作用には動悸、頻脈、血圧変動、嘔気、頭痛、発汗、手足の振戦などがある。
Q.5
狭心症による胸痛の持続時間で適切なのはどれか。(第103回追試)
①5秒
②5分
③50分
④5時間
解答を見る
正解:2
- 5秒
心筋梗塞に比べると痛みの持続時間は短いが5秒ということはない。 - 5分
多くの狭心症で5分以内の痛みが生じている。 - 50分
胸痛の持続時間が50分であれば狭心症ではなく心筋梗塞を疑う。 - 5時間
胸痛の持続時間が5時間であれば狭心症ではなく心筋梗塞を疑う。
狭心症と心筋梗塞の痛みの時間の違いを覚えておこう。狭心症の痛みの持続時間は数分程度で、ほとんどが5分以内とされている。心筋梗塞では、20分以上激しい痛みが続き、多くは6~10時間に及ぶ。
Q.6
急性心不全患者の心臓の負担を減らす体位はどれか。2つ選べ。(第103回追試)
①仰臥位
②腹臥位
③側臥位
④起坐位
⑤Fowler〈ファウラー〉位
解答を見る
正解:4・5
- 仰臥位
仰臥位では、右心系への静脈還流が増加し、これが肺血流を増加させ肺うっ血を引き起こし、呼吸困難が出現してしまう。 - 腹臥位
腹臥位では、右心系への静脈還流が増加し、これが肺血流を増加させ肺うっ血を引き起こし、呼吸困難が出現する。 - 側臥位
側臥位では、右心系への静脈還流が増加し、これが肺血流を増加させ肺うっ血を引き起こし、呼吸困難が出現する。 - 起坐位
仰臥位、腹臥位、側臥位では、右心系への静脈還流が増加し、これが肺血流を増加させ肺うっ血引き起こし呼吸困難が出現する。起坐位ではこれらの一連の流れが軽減することになる。 - Fowler〈ファウラー〉位
仰臥位、腹臥位、側臥位では、右心系への静脈還流が増加し、これが肺血流を増加させ肺うっ血引き起こし呼吸困難が出現する。ファウラー位ではこれらの一連の流れが軽減することになる。
心不全のある患者が起坐呼吸をとろうとする理由を理解しておくとよい。左心不全の状態で臥位をとると、右心系への静脈還流が増加し、続いてこの増加から肺血流が増加して肺うっ血を引き起こし、呼吸困難が出現する。起坐位ではこれらの一連の流れが軽減するため、患者はおのずと起坐位をとろうとする。
Q.7
Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200mL、出血量480mL、尿量980mLであった。術後1日。経口気管チューブが挿入され、人工呼吸器による補助換気が行われている。吸入酸素濃度40%、動脈血酸素分圧〈PaO2〉96Torr、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉35Torr。断続性副雑音が聴取され、気道から泡沫状の分泌物が吸引された。胸部エックス線写真で両肺全体に透過性の低下を認める。胸水を認めない。Aさんに起こっていると考えられる合併症はどれか。(第102回)
①無気肺
②肺水腫
③肺血栓塞栓症
④人工呼吸器関連肺炎
解答を見る
正解:2
- 無気肺
設問では、「断続性副雑音が聴取され」とある。無気肺が起こっているときの呼吸音は、聴診によって肺胞呼吸音減弱や気管支呼吸音化が認められることから、無気肺が起こっているとは考えにくい。 - 肺水腫
設問に、「断続性副雑音が聴取され、気道から泡沫状の分泌物が吸引された」とあることから肺水腫の典型的な症状を呈していると考えられる。 - 肺血栓塞栓症
肺血栓塞栓症が起こったとき、一般的に呼吸音や胸部エックス線写真は正常であることが多い。よって肺血栓塞栓症を起こしているとは考えにくい。 - 人工呼吸器関連肺炎
人工呼吸器関連肺炎とは、入院時や気管挿管時には肺炎がなかったが、気管挿管による人工呼吸管理開始後48~72時間以降に発症する肺炎のことをいう。設問は術後1日であることから人工呼吸器関連肺炎ではない。
肺にある肺胞の周りは毛細血管が取り巻き、空気と血液との間でガス交換がされている。肺水腫はこの毛細血管から血液の液体成分が肺胞内へしみ出した状態をいう。肺胞の中に液体成分がたまるため、酸素の取り込みが障害される。肺水腫には、左心室から全身へ血液を送り出す力が低下し血液が肺に過剰に貯留するために起こる心原性肺水腫と、肺毛細血管の壁が病的変化により液体成分がしみ出しやすくなることが原因で生じる非心原性肺水腫がある。肺水腫の主な症状は呼吸困難やピンク色泡沫痰である。
Q.8
Aさん(55歳、男性)は、仕事中に胸痛発作に襲われ、急性心筋梗塞で緊急入院した。入院直後に、経皮的冠状動脈形成術<PTCA>を受けた。看護師がAさんに心筋梗塞の再発作の予防について説明した。Aさんは「左胸が痛くならなければ大丈夫なんですか」と尋ねた。胸痛以外の発作の兆候の説明として適切なのはどれか。(第100回)
①羞 明
②背部痛
③乾性咳嗽
④出血傾向
解答を見る
正解:2
- 羞 明
羞明とはまぶしく見えることである。心筋梗塞の発作の徴候ではない。 - 背部痛
発作の徴候として、背部に放散痛が出現することがある。 - 乾性咳嗽
乾性咳嗽は心筋梗塞の発作の徴候ではない。 - 出血傾向
出血傾向は心筋梗塞の発作の徴候ではない。
心筋梗塞の発作の徴候には、胸痛のほかに、左肩、左腕、顎、背部、上腹部などに放散痛が出現することがある。
Q.9
55歳の男性。営業職、10年前に定期健康診断で高血圧症と脂質異常症(高脂血症)とを指摘され、薬物治療を続けていた。2年前から階段昇降時に胸部圧迫感を感じていた。今朝、駅の階段を登ったところ、胸痛と息苦しさとが出現し、労作性狭心症の疑いで入院した。身長170cm、体重84kg、脈拍数84/分、整、血圧162/80mmHg。入院後の12誘導心電図は正常である。血清クレアチンキナーゼ(CK)、AST(GOT)の上昇はみられない。
翌日の午前中に冠状動脈造影を行うことになった。
事前の説明で適切なのはどれか。(第95回改変)
①検査は全身麻酔で行われる。
②造影で息苦しさが改善される。
③検査後、穿刺部の圧迫止血が行われる。
④造影用カテーテルは24時間留置される。
解答を見る
正解:3
- 検査は全身麻酔で行われる。
検査はカテーテル穿刺部の局所麻酔で行われる。 - 造影で息苦しさが改善される。
冠状動脈造影は、それだけでは検査であり治療ではないため、造影で息苦しさは改善されない。 - 検査後、穿刺部の圧迫止血が行われる。
大腿動脈や上腕動脈、橈骨動脈などからカテーテルを穿刺して行う検査であるため、検査後は穿刺部の圧迫止血が行われる。 - 造影用カテーテルは24時間留置される。
検査後、造影用カテーテルは速やかに抜去される。24時間留置されることはない。
冠状動脈造影は、大腿動脈や上腕動脈、橈骨動脈から挿入したカテーテルで冠状動脈内に造影剤を流しX線撮影する検査である。
Q.10
急性心筋梗塞患者の合併症を早期に発見するための徴候で正しいのはどれか。(第108回)
①皮疹の出現
②頻脈の出現
③時間尿の増加
④腹壁静脈の怒張
⑤うっ血乳頭の出現
解答を見る
正解:2
- 皮疹の出現
皮疹の観察では早期発見できない。 - 頻脈の出現
急性心筋梗塞で障害された心筋の運動を補うために頻脈を伴う不整脈が出現しやすい。よって、頻脈の出現や心電図波形の観察が重要となる。 - 時間尿の増加
時間尿の増加の観察では早期発見できない。 - 腹壁静脈の怒張
腹壁静脈の怒張の観察では早期発見できない。腹壁静脈の怒張は主に門脈圧亢進で出現する。 - うっ血乳頭の出現
うっ血乳頭の観察では早期発見できない。うっ血乳頭は主に頭蓋内圧亢進で出現する。
急性心筋梗塞の主な合併症には、不整脈や心不全、脳梗塞がある。
Q.11
慢性心不全患者の生活指導で、心臓への負担を少なくするのはどれか。(第108回)
①肺炎球菌ワクチン接種の回避
②蛋白質を制限した食事
③食直後の散歩
④排泄後の休息
解答を見る
正解:4
- 肺炎球菌ワクチン接種の回避
肺炎球菌ワクチンを接種すると肺炎になるリスクを軽減できる。肺炎発症による身体的負担は慢性心不全増悪の原因となるため、肺炎球菌ワクチンを接種することで心臓への負担を少なくすることにつながる。 - 蛋白質を制限した食事
心不全患者の食事指導でのポイントは、塩分制限と水分の過剰摂取の制限である。蛋白質を制限した食事では心臓への負担は少なくならない。 - 食直後の散歩
疾患にかかわらず、食直後の運動は消化を妨げるため推奨されない。 - 排泄後の休息
排泄、特に排便では努責をかけると身体への負担が生じる。排泄後に休息をとることで排泄による身体的負担からの回復を促すことができ、心臓への負担も少なくすることができる。
慢性心不全は徐々に進行するため、特に生活指導では心不全を悪化させる要因を排除することが重要である。
Q.12
A君(15歳、男子)は、病院に併設された院内学級に通いながら骨肉腫に対する治療を続けていた。現在、肺に転移しており終末期にある。呼吸困難があり、鼻腔カニューラで酸素(2L/分)を投与中である。A君の食事の摂取量は徐々に減っているが、意識は清明である。1週間後に院内で卒業式が予定されている。A君は「卒業式は出席したい」と話している。看護師のA君への対応として最も適切なのはどれか。(第103回)
①今の状態では出席は難しいと話す。
②出席できるように準備しようと話す。
③出席を決める前に体力をつけようと話す。
④卒業式の前日に出席するかどうか決めようと話す。
解答を見る
正解:2
- 今の状態では出席は難しいと話す。
子どもの希望をすぐに否定することは、気力を失わせることにつながる。 - 出席できるように準備しようと話す。
A君の希望を尊重した対応であるため、適切である。 - 出席を決める前に体力をつけようと話す。
A君は呼吸困難があり、食事の摂取量も減少している終末期の状態なので、現状では体力をつけるように話すことは適切ではない。 - 卒業式の前日に出席するかどうか決めようと話す。
出席の決定を前日に先延ばしする対応より、今は出席したいというA君の希望を受け止め、出席できるように環境を整えていくことが大切である。
終末期を迎える子どもの看護の基本は、苦痛の緩和、子どもの疑問や不安に対してうそやごまかしを言わないこと、子どもと家族の希望を尊重すること、その子らしく日常の生活を送ることができるように環境を整えることである。
Q.13
公的年金制度について正しいのはどれか。(第106回)
①学生は申請によって納付が免除される。
②生活保護を受けると支給が停止される。
③保険料が主要財源である。
④任意加入である。
⑤積立方式である。
解答を見る
正解:3
- 学生は申請によって納付が免除される。
国民は誰でも20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務となる。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度がある。本人の所得が一定額以下であることが条件で、親の所得は関係がない。免除ではなく猶予であることに注意する。 - 生活保護を受けると支給が停止される。
年金等の収入がある場合、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を引いた差額が保護費として給付される。支給は停止されない。 - 保険料が主要財源である。
保険料、国庫負担、積立金が主要財源である。令和2年(2020年)の国民年金の収支決算では保険料が財源の約36%、厚生年金では保険料が財源の約66%を占める。 - 任意加入である。
公的年金は国民皆年金なので任意ではなく、強制的に加入することになる。 - 積立方式である。
日本の公的年金は賦課方式である。賦課方式は加入者の保険料はその時点の高齢世代の年金給付費になり、加入者の将来の年金のために積み立てておくことはしない方法である。
20歳になっている人は、保険料の支払いなど自分の年金がどうなっているか一度調べるとより理解が深まる。
Q.14
労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。(第106回)
①失業時の教育訓練給付金
②災害発生時の超過勤務手当
③有害業務従事者の健康診断
④業務上の事故による介護補償給付
解答を見る
正解:4
- 失業時の教育訓練給付金
雇用保険法第10条で、「失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする」と規定されている。失業時の教育訓練給付金は労働者災害補償保険法ではない。 - 災害発生時の超過勤務手当
労働基準法第33条で、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、または第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」と災害発生時の超過勤務手当について規定されている。 - 有害業務従事者の健康診断
労働安全衛生法第66条で、有害業務従事者に対し医師あるいは歯科医師による健康診断を行わなければならないとされている。 - 業務上の事故による介護補償給付
労働者災害補償保険法第12条の8で、業務災害に関する保険給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付が規定されている。
労働とそれに伴う健康被害について規定されている法律を整理しておこう。
Q.15
Aさん(50歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。Aさんは十二指腸潰瘍の既往がある。このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。(第104回)
①Romberg〈ロンベルグ〉徴候
②Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候
③Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候
④Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候
解答を見る
正解:2
- Romberg〈ロンベルグ〉徴候
ロンベルグ徴候とは、足を閉じて立位をとり、その後開眼から閉眼することによって、開眼時よりも身体の動揺が大きくなり最後には転倒に至る現象をいう。ロンベルグ徴候が陽性の場合には、脊髄性の運動失調を疑う。 - Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候
ブルンベルグ徴候とは、腹壁を垂直に押し、その後すばやく離したときに痛みを感じることをいう。これは反跳痛ともいわれ、腹腔内の炎症によって生じる痛みであるため、設問の突然の上腹部痛の診察には必要である。 - Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候
クールボアジェ徴候とは、胆囊より下部の総胆管が、圧迫によって閉鎖し、胆囊内に胆汁が蓄積することで無痛性の胆囊腫大が起こることをいう。総胆管癌、乳頭部癌、膵頭部癌にみられる。 - Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候
トレンデレンブルグ徴候とは、患肢で片脚立ちをしたとき、健肢側の骨盤が下がる現象をいう。先天性股関節脱臼などにみられる。
腹腔内の炎症を知るための徴候を覚えておくとよい。腹腔内に炎症があると腹壁を垂直に押し、その後すばやく離したときに痛みを感じる反跳痛が出現する。これをブルンベルグ徴候ともいう。
Q.16
胃全摘術を予定している患者に、中心静脈カテーテルを挿入した直後から呼吸困難が出現した。最も優先される検査はどれか。(第97回)
①心電図
②胸部CT
③胸部エックス線撮影
④上部消化管内視鏡検査
解答を見る
正解:3
- 心電図
気胸を起こしていることが疑われる場合に、心電図検査は最優先で行われる検査ではない。 - 胸部CT
気胸を起こしていることが疑われる場合に、胸部CT検査は最優先で行われる検査ではない。 - 胸部エックス線撮影
気胸を起こしていることが疑われる場合に、最優先で行われるべき検査は胸部エックス線撮影である。 - 上部消化管内視鏡検査
気胸を起こしていることが疑われる場合に、上部消化管内視鏡検査をすることは見当違いである。
中心静脈カテーテルを挿入する場合、穿刺部位に選ばれるのは、内頸静脈、鎖骨下静脈、大腿静脈などである。鎖骨下静脈から穿刺した場合、肺がそばにあることから誤って肺を刺してしまうと気胸が起こる。設問では中心静脈カテーテルを挿入した直後から呼吸困難が出現したとあるため、気胸を起こしていると考えられる。よって、気胸の診断方法を理解していれば解答できる。
Q.17
成人男性の直腸診で腹側に鶏卵大の臓器を触れた。この臓器はどれか。(第99回)
①副 腎
②膀 胱
③精 巣
④前立腺
解答を見る
正解:4
- 副 腎
副腎ではない。 - 膀 胱
膀胱ではない。 - 精 巣
精巣ではない。 - 前立腺
前立腺である。
成人男性の直腸診で腹側に触れる鶏卵大の臓器は前立腺である。
Q.18
急性胃腸炎で38℃の発熱と頻回の水様性下痢がみられる患者への対応で適切なのはどれか。(第103回追試)
①飲水を制限する。
②発汗状態を観察する。
③下腿のけいれんには冷罨法を行う。
④Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候の有無を観察する。
解答を見る
正解:2
- 飲水を制限する。
急性胃腸炎で頻回の水様性下痢があるときには、脱水症状を起こさないように適切に水分補給をする必要がある。 - 発汗状態を観察する。
発熱と頻回の水様性下痢で脱水症状を起こす危険があるため、発汗の状態を観察することでどれくらいの水分を損失しているのかがある程度わかる。 - 下腿のけいれんには冷罨法を行う。
脱水による下腿のけいれんは、体内から水分やナトリウムなどの電解質が失われたために生じている。冷罨法を行っても問題の解決には至らない。 - Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候の有無を観察する。
患肢で片脚立ちをしたとき、健肢側の骨盤が下がる現象をトレンデレンブルグ徴候という。先天性股関節脱臼などにみられる。
発熱や頻回の水様性下痢がある場合に重要なことは何かを考えるとよい。急性胃腸炎では、嘔吐、下痢、腹痛、発熱の症状がみられる。重篤な脱水症状を起こす危険があり、適切な水分補給をすることが大変重要になってくる。
Q.19
高齢者が脱水になりやすい原因はどれか。(第96回改変)
①心拍出量の減少
②尿濃縮機能の低下
③口渇中枢の感受性上昇
④蛋白質摂取量の減少
解答を見る
正解:2
- 心拍出量の減少
心拍出量の減少と、脱水のなりやすさには関連がない。 - 尿濃縮機能の低下
腎機能の低下とともに尿濃縮機能が低下する。体内の水分が余分に排泄されてしまうことにより、脱水になりやすい。 - 口渇中枢の感受性上昇
口渇中枢の感受性の低下により、喉の渇きを感じにくくなり脱水になりやすい。 - 蛋白質摂取量の減少
蛋白質摂取量の減少と脱水のなりやすさには関連がない。
高齢者は、身体機能の変化や経口摂取量の低下などによって脱水になりやすい状態である。
Q.20
高齢者のうつ病の説明で正しいのはどれか。(第103回)
①電気けいれん療法は行わない。
②認知症との区別はつきやすい。
③三環系抗うつ薬を第一選択薬とする。
④若年者と比べて身体症状の訴えが多い。
解答を見る
正解:4
- 電気けいれん療法は行わない。
電気けいれん療法は、薬物療法が困難なうつの場合や自殺企図の高い場合に用いられる。 - 認知症との区別はつきやすい。
高齢者はうつや認知機能低下が混在して現れることが多く、発見が遅れることがあるので鑑別が必要である。 - 三環系抗うつ薬を第一選択薬とする。
三環系抗うつ薬は副作用が強いため、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が選択される。抑うつに加え、無気力・無関心がある場合は、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)が選択される。 - 若年者と比べて身体症状の訴えが多い。
若年者と比べて、頭痛、めまい、腹痛、消化器症状などの身体症状の訴えが多い。
高齢者のうつは典型的な症状を呈さないことが多いので、その特徴を頭に入れてかかわることが重要である。