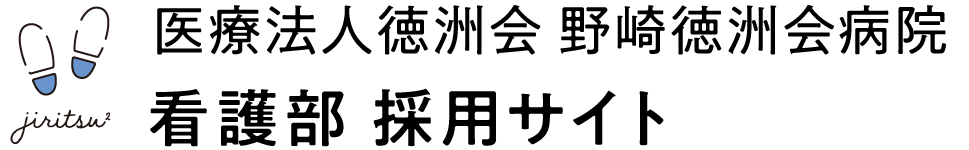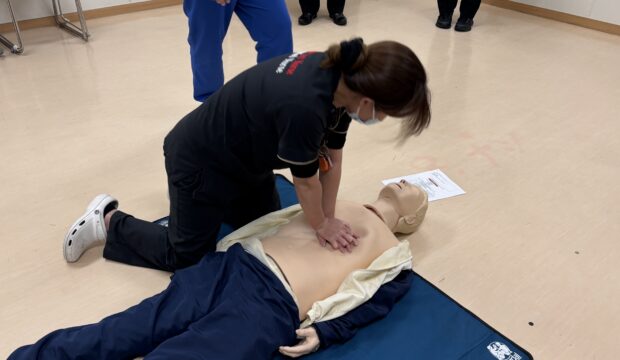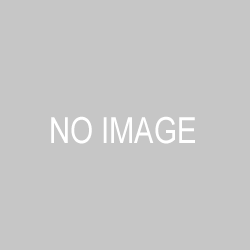Q.1
正常の分娩経過で正しいのはどれか。(第103回)
①分娩開始は、陣痛が15分間隔に起こった時点とする。
②発露は、胎児先進部が陰裂間に常に見えている状態である。
③分娩第2期は、破水から胎児が娩出するまでの期間である。
④分娩第4期は、胎盤娩出から会陰縫合術の終了までの期間である。
解答を見る
正解:2
- 分娩開始は、陣痛が15分間隔に起こった時点とする。
分娩開始は、陣痛が10分おきに規則正しく起こるか、1時間に6回の陣痛が起こった時点である。 - 発露は、胎児先進部が陰裂間に常に見えている状態である。
発露は、児頭先進部が陰裂間に常に見えている状態である。排臨は、陣痛間欠時に児頭先進部が後退し見えなくなる状態である。 - 分娩第2期は、破水から胎児が娩出するまでの期間である。
分娩第2期は、子宮口全開大から胎児娩出までの期間である。 - 分娩第4期は、胎盤娩出から会陰縫合術の終了までの期間である。
分娩第4期は、胎盤娩出から分娩後2時間までの期間である。
分娩第1期から第4期までの正常な分娩経過について押さえておこう。
Q.2
正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。(第103回)
①分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。
②後頭部が先進する。
③胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。
④肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。
解答を見る
正解:2
- 分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。
分娩開始時、矢状縫合は、骨盤入口面横径に一致している。胎児の児背は、第1胎向では母体の左側、第2胎向では母体の右側を向いている。 - 後頭部が先進する。
第1回旋で、児頭の屈位が強まり、後頭部(小泉門)が先進する。 - 胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。
胎児の顔は、母体の背側を向いて娩出される。 - 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。
胎児娩出時、肩甲横径は骨盤の縦軸(前後径)に一致している。
胎児が顎を引き、骨盤内を回転しながら下降していく一連の動きを回旋という。第1回旋から第4回旋までの産道通過機序を考えよう。
Q.3
食物アレルギーのある8歳の児童がアナフィラキシーショックを発症した場合の対応として適切なのはどれか。(第103回)
①水分の補給
②抗ヒスタミン薬の内服
③副腎皮質ステロイドの吸入
④アドレナリンの筋肉内注射
解答を見る
正解:4
- 水分の補給
水分を補給してもショックの改善はできない。 - 抗ヒスタミン薬の内服
抗ヒスタミン薬の内服はアレルギー症状を緩和する効果はあるが、作用に時間がかかるためショック時の対応としては適切ではない。 - 副腎皮質ステロイドの吸入
副腎皮質ステロイドの吸入は、抗炎症作用があり気管支喘息などの気道の炎症を抑える効果はあるが、ショック時の対応には適切ではない。 - アドレナリンの筋肉内注射
アドレナリンの筋肉内注射はすばやく交感神経系に作用し、効果が現れる。血圧を上昇させショック状態を改善させるため、適切である。
食物アレルギーによるアナフィラキシーショックは原因となる食品を摂取、あるいは吸入、接触によっても引き起こされる。生命を脅かす危険性があり、迅速な対応が求められる。ショック時はアドレナリンの自己注射を救急処置として行う。
Q.4
溺水して意識のない小児への救急処置で適切でないのはどれか。(第98回)
①呼吸の有無を確認する。
②必要に応じて心臓マッサージを開始する。
③水を吐かせる。
④保温をする。
解答を見る
正解:3
- 呼吸の有無を確認する。
溺水で意識がない子どもに対しては、気道の確保をして呼吸の有無の確認を行う。 - 必要に応じて心臓マッサージを開始する。
心停止が疑われる場合は、直ちに心臓マッサージ(胸骨圧迫)を開始する。 - 水を吐かせる。
意識のない状態で、子どもに水を吐かせようとすると誤嚥する危険性があるため適切ではない。心肺蘇生を優先する。 - 保温をする。
溺水によって低体温になりやすいため、子どもの身体の保温は重要である。
子どもの事故と予防について理解しよう。
Q.5
幼児の心肺蘇生で正しいのはどれか。(第95回)
①心臓マッサージ3回につき1回人工呼吸をする。
②心臓マッサージは60回/分を目安に行う。
③心臓マッサージは胸骨中央下部を圧迫する。
④心臓マッサージは実施者の示指と中指とで行う。
解答を見る
正解:3
- 心臓マッサージ3回につき1回人工呼吸をする。
心臓マッサージ(胸骨圧迫)30回と人工呼吸2回を繰り返して行う。心臓マッサージ(胸骨圧迫)3回につき1回人工呼吸をするのは、出生時(新生児)の場合である。 - 心臓マッサージは60回/分を目安に行う。
心臓マッサージ(胸骨圧迫)は、1分間に約100~120回のリズムで行う。 - 心臓マッサージは胸骨中央下部を圧迫する。
心臓マッサージ(胸骨圧迫)は乳首を結ぶ線より少し足側の、胸骨中央下部(胸骨の下半分)を圧迫する。 - 心臓マッサージは実施者の示指と中指とで行う。
幼児の心臓マッサージ(胸骨圧迫)は、片方の手のひらの付け根、あるいはもう一方の手をその上に重ねた両手で行う。ただし、基本的に手全体を使わない。乳児には、実施者の指2本(示指と中指あるいは中指と環指)で心臓マッサージ(胸骨圧迫)を行う。
子どもの心肺停止は、そばにいる成人がしっかり心肺蘇生法を身につけておけば、救命できる可能性が高い。
Q.6
疾病とその特徴的な所見の組合せで正しいのはどれか。(第102回)
①急性虫垂炎 ― 血 便
②ネフローゼ症候群 ― 高血圧
③重症筋無力症 ― けいれん
④クループ症候群 ― 吸気性喘鳴
⑤Cushing〈クッシング〉症候群 ― 頸部リンパ節腫脹
解答を見る
正解:4
- 急性虫垂炎 ― 血 便
急性虫垂炎では、腹痛、発熱、食欲低下、嘔吐、下痢などがみられることがあるが、血便はみられない。血便は、感染性腸炎や腸重積でみられる。 - ネフローゼ症候群 ― 高血圧
ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体の障害により大量の蛋白が尿に漏れ、低蛋白血症となることで下肢や眼瞼に浮腫が出る状態をいう。高血圧との関係性は特にない。高血圧が生じやすい腎疾患は、急性糸球体腎炎である。 - 重症筋無力症 ― けいれん
重症筋無力症は、神経から筋肉への指令が伝わらなくなり、疲れやすく、また力が入らなくなる疾患である。眼筋型と全身型がある。けいれんとの関係性はない。 - クループ症候群 ― 吸気性喘鳴
クループ症候群は、喉頭を中心とする上気道の狭窄により、吸気性喘鳴、犬吠様咳嗽、嗄声(させい)などがみられる。 - Cushing〈クッシング〉症候群 ― 頸部リンパ節腫脹
クッシング症候群では、体内の副腎皮質ホルモン(糖質コルチコイド)が過剰な状態となる。満月様顔貌(ムーンフェイス)、中心性肥満などの症状はあるが、頸部リンパ節腫脹はみられない。
それぞれの疾患の、特徴的な症状をよく理解する。吸気性喘鳴はクループ症候群の特徴的な症状の一つである。
Q.7
幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。(第109回)
①胸骨中央下部を圧迫する。
②実施者の示指と中指とで行う。
③1分間に60回を目安に行う。
④1回の人工呼吸につき3回行う。
解答を見る
正解:1
- 胸骨中央下部を圧迫する。
胸骨中央下部を圧迫するため、正しい。 - 実施者の示指と中指とで行う。
幼児の場合は、実施者の片手もしくは重ねた両手で行う。実施者の指2本(示指と中指あるいは中指と環指)で行うのは乳児を対象とする場合である。 - 1分間に60回を目安に行う。
1分間に100~120回の目安で30回連続で圧迫する。 - 1回の人工呼吸につき3回行う。
約30回胸骨圧迫した後、人工呼吸2回を繰り返す。
日本蘇生協議会は「JRC蘇生ガイドライン2020」で子どもの一次救命処置の手順を示している。一次救命処置においては子どもは成人と同様で、胸骨圧迫30回につき人工呼吸2回を交互に繰り返す。推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)は100~120回/分であることから考えよう。
Q.8
ファロー四徴症で通院中の1歳児が入院した。体重を把握する方法で最も適切なのはどれか。(第95回)
①泣いている児を単独で体重計に乗せて測定する。
②母親が抱いて測定し、値から母親の体重を引く。
③母親から児の体重を聞く。
④1か月前の受診時に測定した値を用いる。
解答を見る
正解:2
- 泣いている児を単独で体重計に乗せて測定する。
治療のための薬用量や輸液量を決定するうえで体重は重要な情報のため、正確な値を把握する必要がある。子どもが泣いている場合は、体動により正確な数値にならない。泣いている児を単独で体重計に乗せて測定することは、適切ではない。 - 母親が抱いて測定し、値から母親の体重を引く。
子どもを泣かせないことや正確な体重を測定するため、母親が抱いて測定し、値から母親の体重を引くことが最も適切である。 - 母親から児の体重を聞く。
正確な体重の情報収集には計測をする必要があるため、母親から児の体重を聞くことは、適切ではない。 - 1か月前の受診時に測定した値を用いる。
現時点の正確な体重の情報収集をする必要があるため、1か月前の受診時に測定した値を用いることは、適切ではない。
子どもの入院時には、治療のための薬用量や輸液量を決定するうえで体重が重要な情報となる。正確なフィジカルアセスメントをするため、計測の方法を考えよう。
Q.9
先天性疾患で正しいのはどれか。(第99回)
①フェニルケトン尿症は遺伝病である。
②口唇口蓋裂は単一遺伝疾患である。
③近親婚はターナー症候群の発生頻度を高くする。
④ダウン症候群は13番染色体のトリソミーである。
解答を見る
正解:2
- フェニルケトン尿症は遺伝病である。
フェニルケトン尿症は、潜性遺伝(劣性遺伝)によるフェニルアラニン水酸化酵素の欠損が原因の先天性代謝異常である。 - 口唇口蓋裂は単一遺伝疾患である。
口唇口蓋裂は、単一遺伝子の異常だけでなく、多因子遺伝、染色体異常、妊娠中の薬剤あるいは胎児環境などさまざまな要因が挙げられる。 - 近親婚はターナー症候群の発生頻度を高くする。
ターナー症候群は染色体異常症の1つで、近親婚により発生頻度が高くなるということはない。 - ダウン症候群は13番染色体のトリソミーである。
ダウン症候群は21番染色体が1本過剰の計3本(トリソミー)の染色体異常症である。13番染色体のトリソミーであるというのは、正しくない。
小児期の特有の疾患を理解しよう。
Q.10
小児の1型糖尿病の説明で正しいのはどれか。(第103回追試)
①三大症状には体重増加が含まれる。
②インスリン療法が必須である。
③空腹時血糖80mg/dL以下で低血糖と判定する。
④運動を制限する必要がある。
解答を見る
正解:2
- 三大症状には体重増加が含まれる。
3大症状は、多飲・多尿・体重減少であり、体重は増加しない。 - インスリン療法が必須である。
インスリン注射療法が必須である。 - 空腹時血糖80mg/dL以下で低血糖と判定する。
低血糖の数値の定義はないが、血糖値が50mg/dLぐらいになると低血糖症状が出現することが多い。その症状は個人差が大きいともいわれる。 - 運動を制限する必要がある。
運動は血糖を下げるが、低血糖予防のために補食したりすることで運動が可能である。運動を制限する必要はない。
インスリンが欠乏した1型糖尿病は、子どもに多い。多飲・多尿・体重減少が3大症状である。治療はインスリン補充療法が絶対必要となる。インスリン注射に伴う低血糖の予防と対処、血糖コントロール状態の評価、シックデイ対策、食事療法、運動療法などから疾患を理解する。
Q.11
染色体異常と症状との組合せで正しいのはどれか。(第96回)
①ダウン症候群 ― 筋緊張低下
②ターナー症候群 ― 高身長
③13トリソミー症候群 ― 低身長
④クラインフェルター症候群 ― 内眼角贅皮
解答を見る
正解:1
- ダウン症候群 ― 筋緊張低下
ダウン症候群(21番染色体が1本過剰で計3本:トリソミー)は、先天性心疾患、消化器疾患、免疫系・内分泌系の不全、白血病、筋緊張低下などを特徴とする。 - ターナー症候群 ― 高身長
ターナー症候群(2つのX染色体のうち1つが部分的または完全に欠失した状態)は、女児にみられる性染色体異常である。翼状頸、低身長などが特徴である。 - 13トリソミー症候群 ― 低身長
13トリソミー症候群は余分な13番染色体によって引き起こされる染色体異常症の一種で、典型的には脳の発育が悪く、口唇裂や口蓋裂などがみられる。 - クラインフェルター症候群 ― 内眼角贅皮
クラインフェルター症候群は、2つ以上のX染色体に加えて1つのY染色体が存在する異常である。外性器は男性だが、精巣の発育不全、無精子症、女性化乳房などがみられる。内眼角贅皮とは、目頭の皮膚のつっぱりでダウン症に多くみられる。
小児期の特有の疾患を理解しよう。
Q.12
1か月の乳児。噴水状に嘔吐している。児の消化管の狭窄部位はどれか。(第96回)
①食 道
②噴 門
③幽 門
④回 腸
解答を見る
正解:3
- 食 道
食道の狭窄がある場合は、多くはミルクだけを飲んでいる時期に症状がなく、固形の食事を食べ出した離乳食の開始ころに嘔吐の症状が現れる。 - 噴 門
噴門の狭窄では、嚥下困難やつかえ感といった食物通過障害がみられる。 - 幽 門
生後2~3週ころから、飲んだミルクや胃液を噴水状に吐く場合は、肥厚性幽門狭窄症が疑われる。 - 回 腸
先天的に腸(十二指腸、空腸、回腸)の一部が途切れている腸閉鎖と、狭くなっている腸狭窄があり、あわせて腸閉鎖症・狭窄症という。飲み込んだものや腸液が狭窄部または閉鎖部の手前にたまり、胆汁性嘔吐を呈する。新生児で手術が必要な疾患である。
小児期の特有の疾患を理解しよう。
Q.13
思春期の続発性無月経について正しいのはどれか。2つ選べ。(第103回)
①ストレスが誘因となる。
②乳房の発育は認められない。
③急激な体重の増減と関連する。
④妊娠を希望するまで治療対象にならない。
⑤診断基準の1つとして5か月以上の月経停止がある。
解答を見る
正解:1・3
- ストレスが誘因となる。
思春期の続発性無月経が起こる原因は、ストレス、ダイエットなどによる体重減少が多い。 - 乳房の発育は認められない。
二次性徴は、乳房の発育→陰毛の発生→初経の順に出現することが多い。続発性無月経は、初経後、無月経になった状態であるため、すでに乳房の発育は認められている。 - 急激な体重の増減と関連する。
脂肪はエストロゲンの代謝に関与しており、正常な性機能を保持する役割がある。急激な体重の増減により、無月経になる可能性がある。 - 妊娠を希望するまで治療対象にならない。
無月経は不妊症の原因となるため、受診を勧める必要がある。 - 診断基準の1つとして5か月以上の月経停止がある。
続発性無月経は、月経が3か月以上停止したものである。
満18歳を過ぎても初経が起こらないものを原発性無月経、順調であった月経が3か月以上停止したものを続発性無月経という。続発性無月経の原因と診断基準を確認しよう。
Q.14
女性の不妊症の原因になる可能性がある性感染症<STD>はどれか。2つ選べ。(第100回)
①梅 毒
②淋菌感染症
③性器ヘルペス
④尖圭コンジローマ
⑤性器クラミジア感染症
解答を見る
正解:2・5
- 梅 毒
梅毒は女性の不妊症の原因とはならない。 - 淋菌感染症
淋菌感染症により子宮頸管炎→子宮内膜炎→骨盤内炎症性疾患(PID)→不妊症の原因となる。 - 性器ヘルペス
性器ヘルペスは女性の不妊症の原因とはならない。 - 尖圭コンジローマ
尖圭コンジローマは女性の不妊症の原因とはならない。 - 性器クラミジア感染症
性器クラミジア感染症は、現在最も発生頻度が高い性感染症である。自覚症状を認めないことが多く放置されやすいが、子宮頸管炎→子宮内膜炎→骨盤内炎症性疾患(PID)→不妊症や異所性妊娠の原因となる。
女性の不妊症の原因になる可能性がある性感染症は、性器クラミジア感染症と淋菌感染症である。
Q.15
Aさん(16歳、女子)。身長160cm、体重40kg。1年で体重が12kg減少した。Aさんは6か月前から月経がみられないため婦人科クリニックを受診し、体重減少性無月経と診断された。今後、Aさんの無月経が長期間続いた場合、増加することが予想されるのはどれか。(第106回)
①血糖値
②骨吸収
③体脂肪率
④エストロゲン
解答を見る
正解:2
- 血糖値
低栄養により血糖値は低下する。 - 骨吸収
エストロゲンは骨の吸収を抑える働きがあるため、長期にエストロゲンが低値であることで、骨吸収が増加し、骨量が減少する。 - 体脂肪率
体脂肪率と卵巣機能は密接に関係している。正常な月経発来には体脂肪率22%以上が必要で、10%以下ではほぼ無月経になる。Aさんは体重減少性無月経が長期間続いた場合、体脂肪率は低下する。 - エストロゲン
体重減少性無月経では卵巣機能が低下するため、低エストロゲン状態となる。
体重減少性無月経は、急激な体重減少(標準体重の-15%)により排卵と月経にかけるエネルギーが不足し、続発性無月経をきたすもので、続発性無月経の12%にあたり、思春期の女性に好発する。標準体重の90%までの体重回復を目指して、適切な食事や運動メニューなどを指導する。
Q.16
加齢に伴うエストロゲンの減少が発症に関連している疾患はどれか。2つ選べ。(第103回追試)
①白内障
②直腸癌
③子宮頸癌
④骨粗鬆症
⑤脂質異常症
解答を見る
正解:4・5
- 白内障
白内障は、加齢、糖尿病、紫外線との関連が報告されている。 - 直腸癌
直腸癌は、脂肪分が多い食事、喫煙などの生活習慣との関連が報告されている。また、家族性大腸腺腫症などの遺伝的な関連も報告されている。 - 子宮頸癌
子宮頸癌の発症に関連しているのは、ヒトパピローマウイルス(HPV)である。 - 骨粗鬆症
エストロゲンは、骨量を維持する役割があるため、エストロゲン減少により、骨粗鬆症のリスクが高まる。 - 脂質異常症
エストロゲンは、脂質代謝に関与するため、エストロゲンの減少により血液中のコレステロール値が上昇し、脂質異常症のリスクが高まる。
エストロゲンは、生殖器官以外へもさまざまな作用がある。更年期以降の骨量減少、脂質異常症、高血圧、心疾患は、エストロゲン減少と関連があるといわれている。
Q.17
閉経について正しいのはどれか。(第107回)
①月経は永久に停止する。
②子宮機能の低下で生じる。
③原発性無月経のことである。
④月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。
解答を見る
正解:1
- 月経は永久に停止する。
閉経は永続的な月経停止である。日本人の平均閉経年齢は約50歳である。 - 子宮機能の低下で生じる。
子宮ではなく卵巣機能の消失により起こる。 - 原発性無月経のことである。
原発性無月経とは、満18歳を過ぎても初経が起こらないことである。 - 月経が3か月みられない時点で閉経と判定する。
12か月の連続した無月経を確認した場合に、最後の月経があった月にさかのぼって閉経であったと判断される。
閉経は更年期女性の最も特徴的な身体変化であり、永続的な月経停止のことを指す。
Q.18
更年期障害の女性にみられる特徴的な症状はどれか。(第105回)
①異常発汗
②低血圧
③妄 想
④便 秘
解答を見る
正解:1
- 異常発汗
異常発汗は更年期障害の自律神経失調症状である。 - 低血圧
加齢に伴うエストロゲン欠乏症の心血管系疾患に高血圧がある。 - 妄 想
更年期障害の精神神経症状は、うつ・不安・不眠などがある。 - 便 秘
更年期障害の消化器症状の1つとして便秘はあるが、特徴的な症状とはいえない。
更年期障害は、閉経前後に起こる不定愁訴の総称である。更年期障害の症状は、自律神経失調症状として、顔のほてり・のぼせ(ホットフラッシュ)・発汗などや、精神神経症状として、不眠・イライラ・不安感・抑うつ気分など、さまざまな不定愁訴を含む。更年期障害の症状や頻度は国により違いがみられ、日本人は症状を訴える頻度が低い。
Q.19
高齢女性に生じやすい疾患と原因の組合せで正しいのはどれか。(第104回)
①腟 炎 ― 腟分泌物の酸性化
②外陰炎 ― プロゲステロンの減少
③子宮脱 ― 骨盤底筋群の筋力低下
④子宮体癌 ― プロラクチンの増加
解答を見る
正解:3
- 腟 炎 ― 腟分泌物の酸性化
腟に潤いがある場合は腟内は酸性で自浄作用が起こっているが、高齢女性はエストロゲン分泌低下に伴い腟の潤いが低下することで、腟や外陰部が乾燥し、菌が繁殖することで炎症を起こす。腟炎の原因は、腟分泌物の酸性化ではなく、酸性化が弱まることである。 - 外陰炎 ― プロゲステロンの減少
解説[1]のとおり、腟や外陰部の炎症の原因は、プロゲステロンではなく、エストロゲンの減少である。 - 子宮脱 ― 骨盤底筋群の筋力低下
骨盤底筋など支持組織の筋力が低下することで子宮脱が起こる。 - 子宮体癌 ― プロラクチンの増加
子宮体癌は、エストロゲンの刺激が長期間続くことが原因で発生する場合と、エストロゲンとは関係ない原因で発生する場合がある。エストロゲンが関係していると考えられる原因には、出産経験がないこと、閉経が遅いことなどがある。エストロゲンとは関係ない原因には、糖尿病、血縁者に大腸癌になった人がいることなどがある。
女性の加齢に伴う身体的変化について理解しておこう。
Q.20
萎縮性腟炎に伴う状態について正しいのはどれか。(第105回)
①性交痛
②白色の帯下
③腟壁の肥厚化
④腟の自浄作用の亢進
⑤エストロゲン分泌の増加
解答を見る
正解:1
- 性交痛
性交痛は萎縮性腟炎の症状の1つである。 - 白色の帯下
萎縮性腟炎では、黄色で悪臭を伴う膿性帯下がみられる。 - 腟壁の肥厚化
萎縮性腟炎では、腟は萎縮し、腟壁は点状発赤を呈し、出血しやすくなる。 - 腟の自浄作用の亢進
老年期に向かうにつれ腟の自浄作用が低下し、常在菌(デーデルライン桿菌)の減少を招き、萎縮性腟炎が引き起こされる。 - エストロゲン分泌の増加
エストロゲンの分泌の低下により、腟壁や外陰皮膚の萎縮や腟の自浄作用の低下が起こる。
萎縮性腟炎は閉経後の女性や卵巣摘出後の患者にみられる。萎縮性腟炎の性器症状は、乾燥、瘙痒感、灼熱感、性交痛、帯下(黄色・悪臭)、圧迫感・違和感などがある。