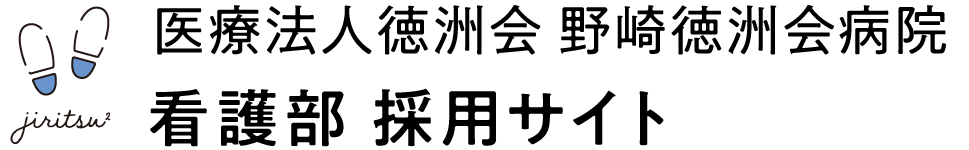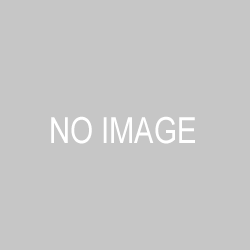Q.1
気管内挿管中の患者の体位ドレナージの実施について適切なのはどれか。(第103回)
①実施前後に気管内吸引を行う。
②体位ドレナージ後に吸入療法を行う。
③自分で体位変換できる患者には行わない。
④創部ドレーンが挿入されている場合は禁忌である。
解答を見る
正解:1
- 実施前後に気管内吸引を行う。
体位ドレナージ後には貯留した気道内分泌物を除去するために気管内吸引を実施する。また、すでに気管内に貯留している気道内分泌物を除去するために体位ドレナージ前にも気管内吸引を実施する。 - 体位ドレナージ後に吸入療法を行う。
吸入療法は気道内分泌物の粘稠度を下げてより排出しやすくする効果があるため、体位ドレナージ前に行う。 - 自分で体位変換できる患者には行わない。
体位ドレナージは重力を利用して気道内分泌物を排出する手技である。患者が自分で体位変換できるかどうかにかかわらず実施できる。 - 創部ドレーンが挿入されている場合は禁忌である。
創部ドレーンが挿入されている場合でも、自己抜去などの事故に注意しながら体位ドレナージを実施することができる。
気管内挿管中の患者の看護だけでなく、体位ドレナージが必要な患者の状況と体位ドレナージの手技の3つの知識を統合して解答しよう。
Q.2
成人の鼻腔からの一時的気道吸引で適切なのはどれか。(第97回)
①カテーテルの内径は12~14Frにする。
②カテーテルは陰圧をかけながら挿入する。
③カテーテルの挿入の長さは2cm以内にする。
④吸引圧は300mmHgを上限にする。
解答を見る
正解:1
- カテーテルの内径は12~14Frにする。
成人の鼻腔吸引では12~14Frのカテーテルを用いる。 - カテーテルは陰圧をかけながら挿入する。
陰圧をかけながらカテーテルを挿入すると、カテーテルが鼻腔内壁に張り付いて挿入が困難になるだけでなく患者は痛みを感じてしまうため、適切ではない。 - カテーテルの挿入の長さは2cm以内にする。
鼻腔吸引の場合、鼻腔から咽頭までの貯留物を吸引する。よって、カテーテルは15cm程度を目安に挿入する。2cmでは短すぎる。 - 吸引圧は300mmHgを上限にする。
鼻腔吸引での吸引圧は150mmHgとする。
鼻腔吸引は鼻腔から咽頭までの貯留物を吸引する手技である。
Q.3
ベンチュリーマスクによる酸素吸入で正しいのはどれか。(第104回)
①最適な酸素流量は18L/分である。
②酸素流量に関係なく加湿器が必要である。
③24~50%の安定した吸入酸素濃度が得られる。
④マスクに空気を溜めることのできるバッグがある。
解答を見る
正解:3
- 最適な酸素流量は18L/分である。
ベンチュリーマスクは設定酸素濃度によってダイリューターを交換し、ダイリューターごとに指示された酸素流量(製品により推奨酸素流量が異なるが、約4~12L/分)を設定する必要がある。 - 酸素流量に関係なく加湿器が必要である。
ベンチュリーマスクは酸素濃度40%以下の場合は、加湿器は必要ないとされている。気管切開患者など必要時にのみ加湿器を用いる。 - 24~50%の安定した吸入酸素濃度が得られる。
ベンチュリーマスクはダイリューターによって、設定酸素濃度を24~50%の間で設定できる。 - マスクに空気を溜めることのできるバッグがある。
ベンチュリーマスクには空気を溜めることのできるバッグはついていない。空気を溜めることのできるバッグがついているのはリザーバー付き酸素マスクである。
ベンチュリーマスクはベンチュリー効果によって多量のガスを噴射し、患者の1回換気量にかかわらず一定の酸素濃度のガスを吸入できる器具である。
Q.4
創傷の治癒過程で正しいのはどれか。(第100回)
①炎症期、増殖期、退行期に分けられる。
②創の局所を圧迫すると、治癒が促進される。
③一次治癒とは、創を開放したままにすることをいう。
④良好な肉芽の形成には、清潔な湿潤環境が必要である。
解答を見る
正解:4
- 炎症期、増殖期、退行期に分けられる。
創傷の治癒過程は4段階(止血期→炎症期→増殖期→成熟期)に分けられる。 - 創の局所を圧迫すると、治癒が促進される。
層の局所を圧迫すると治癒に必要な滲出液の流出や肉芽細胞の形成などを阻害するため、治癒に悪影響を及ぼす。 - 一次治癒とは、創を開放したままにすることをいう。
一次治癒とは皮膚欠損がない場合に、外科的治療で創縁を密着させて治癒させることである。創を開放したままにすることではない。 - 良好な肉芽の形成には、清潔な湿潤環境が必要である。
良好な肉芽の形成には、清潔は湿潤環境が必要である。
創傷の治療では、治癒過程を正しく理解して治りやすい環境を整えることが必要である。
Q.5
フェンタニル貼付剤について適切なのはどれか。(第103回追試)
①冷蔵庫で保存する。
②貼付部位は毎回変える。
③シャワー浴のときは、はがす。
④痛みが強くなったら、もう1枚貼付する。
解答を見る
正解:2
- 冷蔵庫で保存する。
常温保存でよい。麻薬の保管方法に準じて保管する。 - 貼付部位は毎回変える。
毎回同じ部位に貼付するとかゆみなどの皮膚トラブルの原因となるため、貼付部位は毎回変える。 - シャワー浴のときは、はがす。
シャワー浴は貼付したまま可能である。なお、貼付部位を温めすぎると、皮膚から吸収される薬剤量が増えて副作用出現のリスクが高くなるため、熱いお湯への入浴や湯たんぽには注意する。 - 痛みが強くなったら、もう1枚貼付する。
経皮吸収型の薬剤は貼付してから効果が出るまでに時間がかかるため、痛みが強くなったときには即効性のある他の薬剤を使用する。
フェンタニル貼付薬は経皮吸収型の麻薬性鎮痛薬で、がん性疼痛の鎮痛に用いられる。
Q.6
薬の内服方法における頓用で正しいのはどれか。(第109回)
①週に1回服用する。
②食事の前に服用する。
③指定された時間に服用する。
④症状が現れたときに服用する。
解答を見る
正解:4
- 週に1回服用する。
週に1回服用することではなく、症状に応じて必要時に服用するものである。 - 食事の前に服用する。
食事とは関係なく服用する。食事の前に服用するのは食前薬である。 - 指定された時間に服用する。
指定された時間の服用ではなく、症状に応じて必要時に服用するものである。 - 症状が現れたときに服用する。
症状が現れたときに服用するのが頓用であり、正しい。
頓用あるいは頓服とは、ある症状が起こったときや症状が激しいときなどに、必要に応じてその症状に対する薬を内服することである。「38.5℃以上の発熱で服用」の指示がある解熱薬などが頓用に該当する。
Q.7
病棟での医薬品の管理で正しいのはどれか。(第98回)
①生ワクチンは常温で保存する。
②麻薬注射液の残液は直ちに廃棄する。
③用時溶解の薬剤は溶解後冷凍保存する。
④向精神薬は施錠できる場所に保管する。
解答を見る
正解:4
- 生ワクチンは常温で保存する。
生ワクチンは、一般的には遮光して5℃以下(BCGワクチンは10℃以下)で保管する。 - 麻薬注射液の残液は直ちに廃棄する。
麻薬注射液の残液は廃棄せずに麻薬管理責任者に返却する。 - 用時溶解の薬剤は溶解後冷凍保存する。
用時溶解の薬剤は溶解後速やかに使用する。溶解後にそのまま保管したり冷凍すると変質する恐れがある。 - 向精神薬は施錠できる場所に保管する。
向精神薬や麻薬は施錠できる場所に保管する。
薬剤の種類や性質、管理方法について理解しておこう。
Q.8
点眼指導で適切なのはどれか。(第101回)
①油性と水性の薬剤を両方使うときは、油性の薬剤を先に点眼する。
②容器の先端が睫毛に接したら点眼する。
③点眼後は、乾燥するまでまばたきをしない。
④点眼後は、ふき綿で涙囊部を軽く圧迫する。
解答を見る
正解:4
- 油性と水性の薬剤を両方使うときは、油性の薬剤を先に点眼する。
水性は吸収が早いが、油性は吸収が遅く水分をはじく特性がある。よって、油性と水性では水性を先に点眼する。 - 容器の先端が睫毛に接したら点眼する。
容器の先端が睫毛に接してしまうと、睫毛の細菌などによって薬剤が汚染されてしまう可能性がある。よって、容器の先端は睫毛に触れないように点眼する。 - 点眼後は、乾燥するまでまばたきをしない。
眼球が乾燥してしまうとドライアイの状態になってしまう。点眼後は約1分間閉眼する。 - 点眼後は、ふき綿で涙囊部を軽く圧迫する。
点眼後は約1分間閉眼し、ふき綿で涙囊部を軽く圧迫し、薬剤が鼻腔に流れないようにする。
点眼は適切な使用方法で投与することが必要である。
Q.9
Braden〈ブレーデン〉スケールの評価項目で正しいのはどれか。(第109回)
①湿 潤
②循 環
③体 圧
④年 齢
解答を見る
正解:1
- 湿 潤
湿潤はブレーデンスケールにおける評価項目の1つである。 - 循 環
循環という項目はない。 - 体 圧
体圧という項目はない。 - 年 齢
年齢という項目はない。
ブレーデンスケールは褥瘡のアセスメントツールであり、褥瘡発生要因から抽出した6項目(知覚の認知・湿潤・活動性・可動性・栄養状態・摩擦とずれ)を評価している。摩擦とずれは1~3点、その他は1~4点で点数の低いほうが危険度が高い指標となり、在宅・施設では17点を、病院では14点を危険の目安としている。
Q.10
5%グルコン酸クロルヘキシジンを用いて0.2%希釈液1,000mLをつくるのに必要な薬液量はどれか。(第95回)
①10mL
②20mL
③40mL
④50mL
解答を見る
正解:3
- 10mL
10mLではない。 - 20mL
20mLではない。 - 40mL
40mLとなる。 - 50mL
50mLではない。
「必要原液量=希釈濃度÷原液濃度×作成量」から必要量を求める。
必要原液量=0.2÷5×1000=40で、40mLである。
Q.11
発生する粒子が最も小さいのはどれか。(第97回)
①ジェットネブライザー
②超音波ネブライザー
③定量式携帯吸入器
④蒸気吸入器
解答を見る
正解:2
- ジェットネブライザー
ジェットネブライザーの粒子の大きさは1~10μm程度である。気管支拡張薬などの薬液吸入に用いられる。 - 超音波ネブライザー
超音波ネブライザーの粒子の大きさは0.5~5μm程度である。肺胞まで届くエアロゾルを発生できる。 - 定量式携帯吸入器
定量式携帯吸入器の粒子の大きさは2~7μm程度である。 - 蒸気吸入器
蒸気吸入器の粒子の大きさは4~10μm程度である。
吸入療法では発生する粒子が小さいほど肺の深部まで薬剤が到達する。気管支喘息などの呼吸器疾患で用いられる。
Q.12
成人患者への薬剤の投与方法で正しいのはどれか。(第108回)
①筋肉内注射は大殿筋に行う。
②点眼薬は結膜囊に滴下する。
③皮下注射は前腕内側に行う。
④食間の指示の経口薬は食事中に服用させる。
解答を見る
正解:2
- 筋肉内注射は大殿筋に行う。
筋肉注射は、筋肉が厚く大血管や神経の分布が比較的少ない三角筋や中殿筋を選択する。 - 点眼薬は結膜囊に滴下する。
点眼薬は容器先端が睫毛・眼瞼結膜に触れないようにしながら、下眼瞼の結膜囊内に滴下する。 - 皮下注射は前腕内側に行う。
上肢に皮下注射する場合、肩峰と肘頭を結んだ線の下1/3に穿刺する。 - 食間の指示の経口薬は食事中に服用させる。
食間の服薬指示では食後約2~3時間後に服用する。食事中に服用することではない。
薬剤投与はその目的に応じて適切な部位や方法を選択する。
Q.13
抗癌薬を末梢静脈から注入している患者が刺入部の痛みを訴えたため、看護師は直ちに注入を中止した。予期した危険性はどれか。(第95回)
①血管外漏出
②感 染
③血栓形成
④アレルギー反応
解答を見る
正解:1
- 血管外漏出
点滴中の患者が刺入部の痛みを訴えた場合、血管外漏出が考えられる。 - 感 染
感染が生じた場合には刺入部の痛みではなく、発熱などの全身状態に影響する症状が出現すると考えられる。 - 血栓形成
血栓が生じた場合には刺入部の痛みではなく、刺入肢全体の腫脹や疼痛などが生じると考えられる。 - アレルギー反応
アレルギー反応が生じた場合には刺入部の痛みではなく、全身の瘙痒感や蕁麻疹、呼吸困難などが生じると考えられる。
点滴中の患者が刺入部の痛みを訴えた場合、血管外漏出が考えられる。
Q.14
薬剤の取り扱いで正しいのはどれか。(第95回)
①用時溶解の薬剤は溶解後冷凍保存する。
②シロップ剤は常温で保存する。
③向精神薬は鍵のかかる所に保管する。
④麻薬使用後の残った薬液は冷所保存する。
解答を見る
正解:3
- 用時溶解の薬剤は溶解後冷凍保存する。
用時溶解の薬剤は溶解後速やかに使用する。溶解後にそのまま保管したり冷凍すると変質する恐れがある。 - シロップ剤は常温で保存する。
シロップ剤は冷蔵庫などの冷暗所に保存する。 - 向精神薬は鍵のかかる所に保管する。
向精神薬は鍵のかかる所に保管する。 - 麻薬使用後の残った薬液は冷所保存する。
麻薬使用後の残った薬液は、冷所保存ではなく薬剤部に返却する。
薬剤は投与前後においても正しく取り扱う必要がある。
Q.15
65歳の男性のAさんは上部消化管の内視鏡検査を受ける際、抗コリン薬を投与された。看護師がAさんに行う説明で適切なのはどれか。(第100回)
①検査直後から自動車を運転して帰宅できる。
②検査終了後の半日は飲食を禁止する。
③排尿困難を生じる可能性がある。
④腹痛が強くても下血がなければ様子をみる。
解答を見る
正解:3
- 検査直後から自動車を運転して帰宅できる。
抗コリン薬の抗コリン作用によって散瞳が生じ、目のちらつきや視力低下が起こる可能性があるため、検査直後に自動車を運転することができるという説明は適切ではない。 - 検査終了後の半日は飲食を禁止する。
上部消化管の内視鏡検査では咽頭部に麻酔を使用するため、麻酔の効果が消失すれば飲食できる。検査後30分~数時間に飲水をしてむせがなければ飲食が可能である。半日飲食できないという説明は適切ではない。 - 排尿困難を生じる可能性がある。
抗コリン薬の抗コリン作用によって膀胱収縮抑制作用が生じ、排尿困難が起こることがある。 - 腹痛が強くても下血がなければ様子をみる。
内視鏡によって穿孔などが生じる可能性があるため、腹痛がある場合には下血の有無にかかわらずすぐに医師や看護師に伝える。様子をみるという説明は適切でない。
検査前に、消化管の動きを抑制して消化管を観察しやすくすることを目的に、抗コリン薬を投与することがある。抗コリン薬には消化管運動抑制作用の他にさまざまな作用(抗コリン作用)がある。
Q.16
「フロセミド注15mgを静脈内注射」の指示を受けた。注射薬のラベルに「20mg/2mL」と表示されていた。
注射量を求めよ。ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。(第103回)
解答を見る
正解:15
薬剤の量は、総量や有効成分の量で表現される。注射薬のラベルに「20mg/2mL」と表示されていることから、総量2mLの液体の中に、フロセミドの成分が20mg含まれている薬剤であるということがわかる。医師の指示はフロセミド15mgなので、フロセミドが15mg含まれている薬液量を求めればよい。
必要な薬液量をxとすると、20:15=2:xとなる。内項の積と外項の積は等しいことから、
15×2=20x
x=(15×2)/20=1.5mLとなる。
Q.17
癌性疼痛で硫酸モルヒネ徐放薬を内服している患者。内服予定時刻の2時間前に疼痛を訴えた。この時点に最も適している薬剤とその与薬方法はどれか。(第96回)
①抗ヒスタミン薬の内服
②塩酸モルヒネ水の内服
③フェルタニルの皮膚貼用
④ペンタゾシンの筋肉内注射
解答を見る
正解:2
- 抗ヒスタミン薬の内服
抗ヒスタミン薬の内服は、癌性疼痛の緩和には用いられない。 - 塩酸モルヒネ水の内服
塩酸モルヒネ水は癌性疼痛の増強時にレスキューとして使用される薬剤で、速効性がある。 - フェルタニルの皮膚貼用
フェンタニルは癌性疼痛に用いられるが、皮膚貼用の場合は血中濃度の上昇が緩徐のため速効性はない。 - ペンタゾシンの筋肉内注射
モルヒネを投与している患者にペンタゾシンを投与すると拮抗作用を示し、離脱症候や鎮痛効果低下となる可能性がある。
徐放錠とは、薬の成分がゆっくりと長く効くように加工されている薬である。モルヒネ徐放錠は速効性がないためレスキューとしては用いない。
Q.18
輸血後、数日から数週間経過してから出現する副作用(有害事象)はどれか。(第107回)
①溶血性反応
②末梢血管収縮反応
③アナフィラキシー反応
④輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉
解答を見る
正解:4
- 溶血性反応
ABO不適合で起こる急性溶血性反応は輸血開始直後から24時間以内、遅発性溶血性反応は過去に輸血したことのある患者などに輸血後24時間から数日で出現する。 - 末梢血管収縮反応
末梢血管収縮反応は、輸血関連循環過負荷であり、高血圧を生じさせる。輸血開始直後から6時間以内に生じることが多い。 - アナフィラキシー反応
アナフィラキシー反応は、輸血直後から30分以内に発症することが多い。 - 輸血後移植片対宿主病〈PT-GVHD〉
輸血後移植片対宿主病(PT-GVHD)は、輸血後1~2週間で発症する。
輸血の副作用は、輸血開始後から数時間以内に起こる即時性のものと、輸血後数日から数か月経過して起こる遅発性のものがある。
Q.19
点滴静脈内注射360mLを3時間で行う。一般用輸液セット(20滴/mL)を使用した場合の滴下数はどれか。(第100回)
①18滴/分
②36滴/分
③40滴/分
④60滴/分
解答を見る
正解:3
- 18滴/分
18滴/分ではない。 - 36滴/分
36滴/分ではない。 - 40滴/分
40滴/分となる。 - 60滴/分
60滴/分ではない。
このような問題の場合、下記の式を覚えて当てはめるとよい。
1分当たりの滴下数=(1mLの滴下数×1時間当たりの輸液量)÷60
したがって、設問の場合、以下のようになる。
(20×120)÷60=40
Q.20
500mLの輸液を50滴/分の速度で成人用輸液セットを用いて順調に滴下し、現在80分が経過した。
このときの輸液の残量を求めよ。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。(第105回)
解答を見る
正解:300
一般用(成人用)輸液セットの場合、20滴で1mLが体内に入ったことになる。
50滴/分の速度で80分点滴をすると、50×80=4,000滴分の輸液が体内に入ったことがわかる。成人用輸液セットは、20滴で1mLなので、4,000÷20=200(mL)となり、80分経過した時点で200mLの輸液が体内に入ったことがわかる。もともと輸液は500mLだったので、輸液の残量は500-200=300(mL)となる。