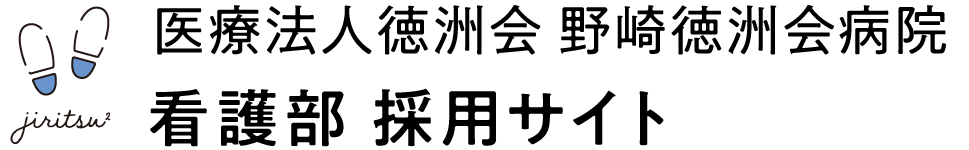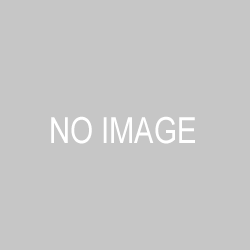Q.1
下腿の蜂窩織炎を繰り返している患者への炎症徴候を早期に発見するための指導で最も適切なのはどれか。(第101回)
①「入浴後に観察しましょう」
②「体温は毎朝測りましょう」
③「膿(うみ)が出ていないか観察しましょう」
④「赤くなっていないか観察しましょう」
解答を見る
正解:4
- 「入浴後に観察しましょう」
入浴後に観察することは正しいが、設問では「炎症徴候を早期に発見するための指導」とあるため、炎症徴候とはどのようなことかを説明すべきである。 - 「体温は毎朝測りましょう」
炎症徴候に発熱があるが、設問では「炎症徴候を早期に発見するための指導」とあるため、毎朝体温を測るより下肢に起きる炎症徴候を直接観察するほうが早期発見につながる。 - 「膿(うみ)が出ていないか観察しましょう」
膿が出る状態となる前に炎症徴候を発見すべきである。炎症徴候を早期に発見するための指導として適切ではない。 - 「赤くなっていないか観察しましょう」
炎症徴候には発赤があるため、炎症徴候を早期に発見するための指導として適切な説明である。
蜂窩織炎は黄色ブドウ球菌やβ溶血性連鎖球菌が原因となって起こる。発熱、発赤、腫脹、疼痛の急性炎症の四徴が起こる。
Q.2
白血球減少症で正しいのはどれか。2つ選べ。(第104回)
①好塩基球数は増加する。
②EBウイルス感染によって起こる。
③白血球数が3,000/μL以下をいう。
④好中球減少症では細菌に感染しやすくなる。
⑤無顆粒球症は単球がなくなった病態をいう。
解答を見る
正解:3・4
- 好塩基球数は増加する。
白血球減少症では好塩基球数は減少する。 - EBウイルス感染によって起こる。
EBウイルスの感染では伝染性単核症を起こす。急性感染症であり、症状として発熱、咽頭通、頸部リンパ節腫脹がある。 - 白血球数が3,000/μL以下をいう。
白血球減少症とは、白血球数が3,000/μL以下のことをいう。 - 好中球減少症では細菌に感染しやすくなる。
好中球数が1,500/μL以下のことを好中球減少症という。好中球は、細菌や真菌の感染を防いでいるため、好中球が減少するとこれらの感染に対して無力となるため、感染しやすくなる。 - 無顆粒球症は単球がなくなった病態をいう。
無顆粒球症とは、顆粒球のうち好中球が500/μL以下になった病態をいう。
白血球減少症とは、白血球数が3,000/μL以下のことをいう。最も多いのは好中球減少症(好中球が1,500/μL以下)で、細菌感染などを起こしやすくなる。ほかに顆粒球減少症、好酸球減少症、リンパ球減少症、無顆粒球減少症などがある。
Q.3
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応で正しいのはどれか。(第105回)
①Ⅰ 型
②Ⅱ 型
③Ⅲ 型
④Ⅳ 型
⑤Ⅴ 型
解答を見る
正解:4
- Ⅰ 型
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応はⅠ型ではない。 - Ⅱ 型
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応はⅡ型ではない。 - Ⅲ 型
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応はⅢ型ではない。 - Ⅳ 型
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応はⅣ型である。 - Ⅴ 型
接触性皮膚炎の原因となるアレルギー反応はⅤ型ではない。
接触性皮膚炎のアレルギー反応はⅣ型(遅延型)であり、48時間が反応のピークになる。感作リンパ球によるもので、ツベリクリン反応もこれにあたる。
Q.4
59歳の男性。両肩と胸部の皮膚に異常をきたしたため来院した。皮膚の写真を別に示す。聴取する項目で優先度が高いのはどれか。(第99回)

①渡航歴
②飲酒歴
③喫煙歴
④予防接種歴
解答を見る
正解:2
- 渡航歴
渡航歴は肝機能低下と直接関係がない。 - 飲酒歴
飲酒歴を聴取することで肝機能低下を疑うことができる。 - 喫煙歴
喫煙歴は肝機能低下と直接関係がない。 - 予防接種歴
予防接種歴は肝機能低下と直接関係がない。
設問の皮膚の写真はくも状血管腫である。くも状血管腫は肝硬変などで肝機能が低下することで発生する。肝機能が低下することに関連する選択肢を選ぶことで解答できる。
Q.5
造血幹細胞移植後に急性移植片対宿主病<GVHD>を疑うのはどれか。(第100回)
①耳 鳴
②鼻閉感
③ばち状指
④頻繁な水様便
解答を見る
正解:4
- 耳 鳴
耳鳴は急性移植片対宿主病(GVHD)を疑う症状ではない。 - 鼻閉感
鼻閉感は急性移植片対宿主病(GVHD)を疑う症状ではない。 - ばち状指
ばち状指は急性移植片対宿主病(GVHD)を疑う症状ではない。 - 頻繁な水様便
頻繁な水様便は急性移植片対宿主病(GVHD)を疑う症状である。
急性移植片対宿主病(GVHD)は移植後早期に起こり、発熱、皮膚病変、黄疸、下痢などが起こる。皮膚病変では、赤い斑点が手のひらや足の裏にできる。下痢は水様の下痢であり、重症になると出血を伴った大量の水様下痢となる。
Q.6
じんま疹のアレルギーのタイプはどれか。(第99回)
①Ⅰ 型
②Ⅱ 型
③Ⅲ 型
④Ⅳ 型
解答を見る
正解:1
- Ⅰ 型
じんま疹はⅠ型アレルギーである。 - Ⅱ 型
Ⅱ型アレルギーには血液型不適応輸血などが含まれる。 - Ⅲ 型
Ⅲ型アレルギーには糸球体腎炎などが含まれる。 - Ⅳ 型
Ⅳ型アレルギーにはアレルギー性接触皮膚炎などが含まれる。
アレルギーはⅠ型からⅣ型の4つのタイプに分類される。
Q.7
花粉症について正しいのはどれか。(第101回)
①ブタクサによる症状は春に多い。
②Ⅱ型アレルギー性疾患である。
③ヒスタミンが放出される。
④好塩基球が増加する。
解答を見る
正解:3
- ブタクサによる症状は春に多い。
ブタクサによる症状は秋頃に多い。春頃はスギによる花粉症が多くなる。 - Ⅱ型アレルギー性疾患である。
花粉症はⅠ型のアレルギー性疾患である。 - ヒスタミンが放出される。
Ⅰ型アレルギーでは抗原である花粉とIgEが反応してヒスタミンなどが放出され、くしゃみや鼻汁、鼻閉などの症状が出現する。 - 好塩基球が増加する。
Ⅰ型アレルギーでは好塩基球ではなく、抗原に特異的なIgEが増加する。
花粉症はⅠ型アレルギーで、抗原である花粉に特異的なIgEがつくられ、抗原抗体反応によって症状が出現する。
Q.8
アトピー性皮膚炎で正しいのはどれか。(第95回)
①IgE抗体が関与する。
②抗核抗体が陽性になる。
③四肢の伸側に好発する。
④患部の発汗が増加する。
解答を見る
正解:1
- IgE抗体が関与する。
アトピー性皮膚炎は、IgE抗体が関与する。 - 抗核抗体が陽性になる。
抗核抗体が陽性になるのは膠原病などである。 - 四肢の伸側に好発する。
アトピー性皮膚炎の好発部位は、前額、眼周、口囲、口唇、耳介周囲、頸部、四肢関節部などである。 - 患部の発汗が増加する。
患部の発汗が増加することはない。
アトピー性皮膚炎では、瘙痒感のある湿疹が繰り返し出現する。IgE抗体を持っていることが多い。
Q.9
疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。(第98回)
①悪性貧血 ― ビタミンB6低値
②ホジキン病 ― ラングハンス巨細胞
③慢性骨髄性白血病 ― フィラデルフィア染色体
④播種性血管内凝固症候群(DIC) ― プロトロンビン時間短縮
解答を見る
正解:3
- 悪性貧血 ― ビタミンB6低値
悪性貧血はビタミンB12の吸収障害が原因で起こる。ビタミンB6ではなく、ビタミンB12が低値となる。 - ホジキン病 ― ラングハンス巨細胞
ホジキンリンパ腫(ホジキン病)は、リンパ節生検でホジキン細胞とリード-シュテルンベルク細胞などの所見がみられる。ラングハンス巨細胞はみられない。 - 慢性骨髄性白血病 ― フィラデルフィア染色体
慢性骨髄性白血病では、異常染色体であるフィラデルフィア染色体(Ph染色体)が出現する。 - 播種性血管内凝固症候群(DIC) ― プロトロンビン時間短縮
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、凝固活性化によって微小血栓が多発し出血傾向や出血症状が生じる。よって、プロトロンビン時間は短縮するのではなく延長する。
疾患には特徴的な所見があるものが多い。疾患の特定にも役立つので、疾患と特徴的な所見は合わせて理解しよう。
Q.10
Behçet〈ベーチェット〉病に特徴的なのはどれか。(第101回)
①真珠腫
②粘液水腫
③紫紅色紅斑
④外陰部潰瘍
解答を見る
正解:4
- 真珠腫
真珠腫は真珠腫性中耳炎でみられる。 - 粘液水腫
粘液水腫は甲状腺機能低下症でみられる。 - 紫紅色紅斑
紫紅色紅斑は多発性筋炎などでみられる。 - 外陰部潰瘍
外陰部潰瘍は外陰部に生じる有痛性の潰瘍で、ベーチェット病で特徴的なものである。
ベーチェット病は繰り返す炎症反応により全身の臓器が障害される疾患である。
Q.11
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉が感染する細胞はどれか。(第102回)
①好中球
②形質細胞
③Bリンパ球
④ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球
⑤細胞傷害性〈CD8陽性〉Tリンパ球
解答を見る
正解:4
- 好中球
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が感染する細胞は、ヘルパー(CD4陽性)Tリンパ球であり、好中球ではない。 - 形質細胞
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が感染する細胞は、ヘルパー(CD4陽性)Tリンパ球であり、形質細胞ではない。 - Bリンパ球
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が感染する細胞は、ヘルパー(CD4陽性)Tリンパ球であり、Bリンパ球ではない。 - ヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が感染する細胞は、ヘルパー(CD4陽性)Tリンパ球である。 - 細胞傷害性〈CD8陽性〉Tリンパ球
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が感染する細胞は、ヘルパー(CD4陽性)Tリンパ球であり、細胞傷害性(CD8陽性)Tリンパ球ではない。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症とは、CD4陽性Tリンパ球と呼ばれる白血球の一種を徐々に破壊し、後天性免疫不全症候群(エイズ)を引き起こすことがある感染症である。CD4陽性Tリンパ球が破壊されると、多くの感染性微生物による攻撃を受けやすくなり死に至ることもある。HIV感染症では、HIVの感染自体ではなく、それ以外の病原体の感染によって生命が脅かされる。
Q.12
Sjögren〈シェーグレン〉症候群について正しいのはどれか。(第107回)
①網膜炎を合併する。
②男女比は1対1である。
③主症状は乾燥症状である。
④抗核抗体の陽性率は30%程度である。
解答を見る
正解:3
- 網膜炎を合併する。
シェーグレン症候群の合併症は、乾燥性角結膜炎や涙腺炎である。 - 男女比は1対1である。
シェーグレン症候群の男女比は1:12であり、50代の女性に多い。 - 主症状は乾燥症状である。
シェーグレン症候群はドライマウス、ドライアイなどの乾燥症状が生じる。 - 抗核抗体の陽性率は30%程度である。
シェーグレン症候群の抗核抗体陽性率は70~90%である。
シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺にリンパ球が浸潤することで起こる慢性的な炎症で、自己免疫疾患である。
Q.13
全身性エリテマトーデス〈SLE〉でみられるのはどれか。(第103回追試)
①体重増加
②光線過敏症
③白血球増加
④高度の変形を伴う関節痛
解答を見る
正解:2
- 体重増加
全身性エリテマトーデスでは体重は減少する。 - 光線過敏症
全身性エリテマトーデスでは光線過敏症がみられる。 - 白血球増加
全身性エリテマトーデスでは白血球の減少がみられる。 - 高度の変形を伴う関節痛
全身性エリテマトーデスでは関節炎がみられるが、骨破壊を伴うことはない。高度の変形を伴う関節痛は変形性膝関節症や関節リウマチなどでみられる。
全身性エリテマトーデスは20~40歳代に発症する人が多く、男女比は1:10ほどで女性に多い疾患である。血液中の抗核抗体が、抗原である核酸と反応し、免疫複合体をつくって全身の皮膚、関節、血管、腎臓などに沈着して疾患が引き起こされる。
Q.14
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の感染経路で正しいのはどれか。2つ選べ。
①感染者の嘔吐物との接触
②感染者の咳による曝露
③感染者の糞便との接触
④感染者からの輸血
⑤感染者との性行為
解答を見る
正解:4・5
- 感染者の嘔吐物との接触
感染者の嘔吐物と接触することはHIVの感染経路ではない。 - 感染者の咳による曝露
感染者の咳による曝露はHIVの感染経路ではない。 - 感染者の糞便との接触
感染者の糞便との接触はHIVの感染経路ではない。 - 感染者からの輸血
感染者からの輸血はHIVの感染経路である。 - 感染者との性行為
感染者との性行為はHIVの感染経路である。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染経路には輸血、血液製剤、注射器の共用、性交渉、授乳、妊娠中の胎盤感染、出産時の産道感染などがある。HIVが損傷を受けた皮膚や粘膜へ侵入し感染する。空気感染、食物を通しての経口感染は起こらない。
Q.15
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。(第104回)
①経皮感染する。
②無症候期がある。
③DNAウイルスによる。
④血液中のB細胞に感染する。
解答を見る
正解:2
- 経皮感染する。
血液、精液、腟分泌液、母乳などに含まれるHIVが粘膜や傷口を介して感染する。経皮感染はしない。 - 無症候期がある。
HIVに感染した後は、急性感染期→無症候期→AIDS発症の経過をたどる。 - DNAウイルスによる。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)はレトロウイルスの一種で、遺伝情報をRNAとして蓄えている。DNAではない。 - 血液中のB細胞に感染する。
CD4陽性リンパ球に入り込み感染する。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症では、血液、精液、腟分泌液、母乳などに含まれるHIVが粘膜や傷口から体内に入り、CD4陽性Tリンパ球に入り込み感染する。HIVが増殖すると、免疫に必要な細胞が減っていき、さまざまな症状が出るようになる。
Q.16
ウイルスが原因で発症するのはどれか。(第100回)
①多発性骨髄腫
②鉄欠乏性貧血
③再生不良性貧血
④成人T細胞白血病
解答を見る
正解:4
- 多発性骨髄腫
多発性骨髄腫は、はっきりした原因が明らかになっていない。何らかの原因によって腫瘍化した形質細胞である骨髄腫細胞が、単一の異常免疫グロブリンを産生し続けることによってさまざまな症状が起こる。 - 鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は鉄の供給不足や需要増大、喪失亢進などが原因である。ウイルスが原因ではない。 - 再生不良性貧血
再生不良性貧血は、はっきりした原因が明らかになっていない。何らかの原因によって造血幹細胞が障害されて血球が産生できなくなる疾患である。 - 成人T細胞白血病
成人T細胞白血病は、ヒトレトロウイルス(HTLV-1)への感染が原因で起こる。主に母乳によって感染し、30~50年の潜伏期間を経て発症する。
疾患の原因は明らかになっていないものも多い。すでに明らかになっている疾患と原因は合わせて理解しよう。
Q.17
スギ花粉によるアレルギー性鼻炎患者の花粉飛散時期前後の指導で適切なのはどれか。(第98回)
①洗濯物は屋外で完全に乾燥させる。
②ほこりを吸わないよう掃除は控える。
③化学繊維素材よりも毛織物の衣類を選ぶ。
④花粉飛散の前から抗アレルギー点鼻薬を使用する。
解答を見る
正解:4
- 洗濯物は屋外で完全に乾燥させる。
洗濯物を屋外で乾燥させるとスギ花粉が付着して、衣服を着用した際にアレルギー性鼻炎を悪化させる恐れがあるため避ける。室内で乾燥させる。 - ほこりを吸わないよう掃除は控える。
掃除を控えるとスギ花粉が床面に残存する可能性があるので適切ではない。こまめに掃除をしてスギ花粉を除去する。 - 化学繊維素材よりも毛織物の衣類を選ぶ。
ポリエステル、ナイロンなどの表面がつるつるした化学繊維素材の衣類では花粉が付着しにくい。ウールなどの毛織物は花粉が付着しやすいので避ける。 - 花粉飛散の前から抗アレルギー点鼻薬を使用する。
花粉飛散の前から抗アレルギー薬を使用することで、症状緩和に役立つ。
アレルギー性鼻炎はⅠ型アレルギーで、くしゃみ、鼻汁、鼻閉などの症状が出現する。
Q.18
1年前にハチに刺された人が再びハチに刺された。起こる可能性があるアレルギー反応はどれか。(第102回)
①Ⅰ型アレルギー
②Ⅱ型アレルギー
③Ⅲ型アレルギー
④Ⅳ型アレルギー
解答を見る
正解:1
- Ⅰ型アレルギー
Ⅰ型アレルギーは、IgE抗体にアレルゲンが結合することにより起こる。アトピー型気管支喘息、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎、アナフィラキシーショックなどが代表疾患である。ハチ、アリなどの刺咬昆虫はアナフィラキシーの原因として代表的である。 - Ⅱ型アレルギー
Ⅱ型アレルギーは、IgGまたはIgM抗体が関与して起こる。代表的な疾患には、不適合輸血による溶血性貧血、自己免疫性溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、薬剤性溶血性貧血、顆粒球減少症、血小板減少症などがある。 - Ⅲ型アレルギー
Ⅲ型アレルギーは、可溶性抗原とIgGまたはIgM抗体との免疫複合体による組織傷害である。代表的な疾患には、血清病、全身性エリテマトーデス(SLE)、リウマチなどの自己免疫疾患、糸球体腎炎、過敏性肺炎などがある。 - Ⅳ型アレルギー
Ⅳ型アレルギーは感作リンパ球と抗原との反応により、感作リンパ球からサイトカインが放出されることで起こる。遅延型アレルギーとも呼ばれ、症状にはツベルクリン反応、接触性皮膚炎などがある。
アレルギー反応の分類法として、現象的には皮膚反応出現にかかる時間と反応の性状により分けられる。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型は血清抗体が関与する体液性免疫、Ⅳ型は感作リンパ球による細胞性免疫と大別される。アナフィラキシーはⅠ型アレルギーである。
Q.19
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。(第107回)
①本人より先に家族に病名を告知する。
②国内では異性間性的接触による感染が最も多い。
③適切な対応によって母子感染率を下げることができる。
④性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。
⑤HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。
解答を見る
正解:3・4
- 本人より先に家族に病名を告知する。
病名告知はまず本人に行う。HIVだからといって本人より先に家族に告知しなければならない理由はない。 - 国内では異性間性的接触による感染が最も多い。
国内の感染経路別で最も多いのは同性間性的接触による感染である。 - 適切な対応によって母子感染率を下げることができる。
HIVの母子感染は産道、胎盤、母乳を介して起こる可能性があるが、帝王切開、抗HIV薬の投与、人工栄養の使用(母乳による授乳の禁止)によって母子感染率を下げることができる。 - 性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。
HIVは体液が粘膜や皮膚の傷口から侵入することで感染する。精液などの体液が粘膜に接触するのを防ぐために、性行為ではコンドームの使用を勧める。 - HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。
AIDSはHIVが進行して免疫不全となってAIDS指標疾患(日和見感染症、悪性腫瘍など)が出現した状態である。HIVに感染すればAIDSと診断されるわけではない。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症は後天性免疫不全症候群(AIDS)の原因となる疾患で、1~10年の無症状期間があるのが特徴である。
Q.20
同種骨髄移植で正しいのはどれか。(第98回)
①提供者とのABO式血液型の一致が条件である。
②手術室において全身麻酔下で移植される。
③免疫抑制薬を用いる。
④骨髄生着後は感染の危険性がなくなる。
解答を見る
正解:3
- 提供者とのABO式血液型の一致が条件である。
骨髄移植では白血球のHLAが一致することが条件である。 - 手術室において全身麻酔下で移植される。
移植は輸血のように点滴で投与される。手術室において全身麻酔下で移植されるのではない。 - 免疫抑制薬を用いる。
同種骨髄移植の合併症である移植片対宿主病を予防するために免疫抑制薬を使用する。 - 骨髄生着後は感染の危険性がなくなる。
骨髄生着後も感染の危険性はある。
同種骨髄移植の合併症としては、移植片対宿主病、生着不全、感染症などが起こることがある。免疫抑制薬を使用して移植片対宿主病の予防を行う。