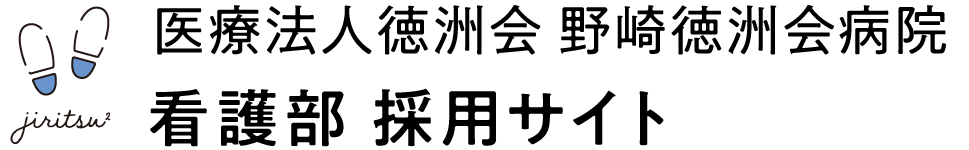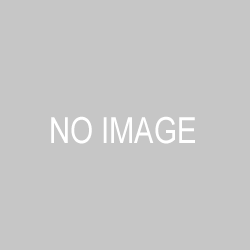Q.1
ビタミンの欠乏とその病態との組合せで正しいのはどれか。(第105回)
①ビタミンA ― 壊血病
②ビタミンB1 ― 代謝性アシドーシス
③ビタミンC ― 脚 気
④ビタミンD ― 悪性貧血
⑤ビタミンE ― 出血傾向
解答を見る
正解:2
- ビタミンA ― 壊血病
ビタミンA欠乏は夜盲症を起こす。壊血病の原因はビタミンC欠乏である。 - ビタミンB1 ― 代謝性アシドーシス
ビタミンB1の欠乏により乳酸が蓄積する結果、代謝性アシドーシスが生じる。 - ビタミンC ― 脚 気
ビタミンCが欠乏すると壊血病が起こる。脚気の原因はビタミンB1の欠乏である。 - ビタミンD ― 悪性貧血
ビタミンDの欠乏により起こるのはくる病(小児)、骨軟化症(成人)である。悪性貧血の原因はビタミンB12欠乏である。 - ビタミンE ― 出血傾向
ビタミンE欠乏により起こるのは神経・筋肉障害である。
ビタミンの欠乏とその病態の組み合わせは国試頻出である。正しい組み合わせを覚えておこう。
Q.2
肝動脈塞栓術〈TAE〉の適応となる疾患はどれか。(第109回)
①脂肪肝
②急性A型肝炎
③肝細胞癌〈HCC〉
④アメーバ性肝膿瘍
解答を見る
正解:3
- 脂肪肝
脂肪肝の治療は禁酒、食事療法、運動療法である。 - 急性A型肝炎
急性A型肝炎の治療は安静、栄養、肝庇護薬(グリチルリチン製剤、ウルソデオキシコール酸など)の投与である。 - 肝細胞癌〈HCC〉
肝動脈塞栓術(TAE)は抗癌薬や動脈を閉塞させる物質(リピオドール、ヒストアクリルなど)を肝細胞癌のそばまでカテーテルを進めて注入する。肝細胞癌の栄養血管を閉じることで癌の死滅を図る。カテーテルは大腿動脈を穿刺して挿入する。 - アメーバ性肝膿瘍
アメーバ性肝膿瘍の治療ではメトロニダゾールやパロモマイシン硫酸塩を投与する。
肝動脈塞栓術(TAE)はインターベンショナルラジオロジー(IVR)の1つである。大腿動脈を穿刺するので、通常6時間程度ベッド上仰臥位とし、穿刺部を圧迫止血する。
Q.3
右大腿動脈からの肝動脈塞栓術施行後の対応で適切なのはどれか。(第98回)
①右足背動脈を触診し拍動を確認する。
②施行後24時間は絶対安静とする。
③施行当日の発熱には抗菌薬が投与される。
④鎮痛薬は肝臓への負担があるため使用できない。
解答を見る
正解:1
- 右足背動脈を触診し拍動を確認する。
血管内操作を行った後であるため、血栓による動脈閉塞を起こしていないか、足背動脈の拍動を触知して確認する。なお、左右両方の足背動脈を触知して拍動の強さを比較することで確認するほうが望ましい。 - 施行後24時間は絶対安静とする。
大腿動脈を穿刺していることから、施術後は止血を確認することが大切であるが、24時間の絶対安静は不要である。 - 施行当日の発熱には抗菌薬が投与される。
施行当日の発熱は細菌の感染によるものではないため抗菌薬は投与されない。 - 鎮痛薬は肝臓への負担があるため使用できない。
疼痛がある場合は鎮痛薬が使用される。
血管内操作をすることから、カテーテルによる血管への直接の障害によって血栓ができたり、もともと血管壁に付着していた血栓が剝がれることがあり、血栓による動脈閉塞を起こすことがある。大腿動脈を穿刺していることから、施術後は止血を確認することが大切である。
Q.4
Aさん(42歳、男性、会社員)は、1人で暮らしている。毎日、たばこを20本吸い、缶ビールを3本飲んでいた。Aさんは週末にラグビーをした後、帰りに焼肉を食べるのを楽しみにしている。高尿酸血症で治療を受けることになり、尿酸排泄促進薬が処方された。缶ビールを1本に減らしたが、尿酸値が高い状態が続いている。身長172cm、体重67kg。その他の血液検査データに異常はない。Aさんへの生活指導で最も適切なのはどれか。(第104回)
①禁 煙
②体重の減量
③過度な運動の回避
④蛋白質摂取の禁止
解答を見る
正解:3
- 禁 煙
禁煙は生活習慣として正しいが、設問では高尿酸血症で治療を受けることになったということであるため、喫煙は直接の禁止事項ではない。 - 体重の減量
BMIが22.65であるが、肥満ではない。 - 過度な運動の回避
痛風発作は過度な運動が原因となって引き起こされる。Aさんはラグビーをしていることから、過度な運動の回避を促すのは適切である。 - 蛋白質摂取の禁止
蛋白質摂取を禁止する必要はない。
痛風発作の原因となるのは激しい運動、過食、多量の飲酒などである。
Q.5
Aさん(52歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。妻は末期の肺癌で、今朝自宅で亡くなった。主治医が死亡診断を行った後のAさんへの訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。(第104回)
①葬儀を手配するよう勧める。
②医療機器は早急に片づけるよう勧める。
③Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。
④本日中に死亡診断書を役所に提出するよう説明する。
解答を見る
正解:3
- 葬儀を手配するよう勧める。
手続きなどに進むには時間が必要である。しばらく妻の死を現実のものと受け止める時間が必要である。 - 医療機器は早急に片づけるよう勧める。
選択肢[1]と同様で医療機器を片づけるには時間が必要である。 - Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。
妻の死を現実のものと受け止める時間として、死後の処置を一緒に行うのもよい。 - 本日中に死亡診断書を役所に提出するよう説明する。
選択肢[1]・[2]と同様に、急がないでよい。死亡診断書と死亡届を役所に提出するのは死後7日以内である。
終末期の最期の死別期である。家族のグリーフケアを行いたい。Aさんは早すぎる死を受け止められず呆然とした状態であることを理解する。
Q.6
Aさん(60歳、男性)は、1年前に膵癌と診断されて自宅で療養中である。疼痛管理はレスキューとして追加注入ができるシリンジポンプを使用し、オピオイドを持続的に皮下注射している。訪問看護師のAさんへの疼痛管理の指導で適切なのはどれか。(第104回)
①シリンジの交換はAさんが実施する。
②疼痛がないときには持続的な注入をやめてもよい。
③レスキューとしてのオピオイドの追加注入はAさんが行う。
④レスキューとして用いるオピオイドの1回量に制限はない。
解答を見る
正解:3
- シリンジの交換はAさんが実施する。
シリンジ交換は訪問看護師が行う。 - 疼痛がないときには持続的な注入をやめてもよい。
疼痛がないのはオピオイドの効果と考えられる。持続的な注入をやめると疼痛が出てくる。 - レスキューとしてのオピオイドの追加注入はAさんが行う。
レスキューは自分でできるタイプがある。自分の疼痛の程度に合わせて使用できるように指導する。 - レスキューとして用いるオピオイドの1回量に制限はない。
制限はある。レスキューの目安として、持続皮下注射の場合は1時間量の投与が可能である。
オピオイドは経口投与を基本とするが、悪心・嘔吐などの消化器症状により経口投与できないときに、バッテリー内蔵持続皮下注射器などを用いて皮下注射する。安全かつ簡便で、投与量の変更が迅速に行え、疼痛コントロールの不安定な場合などにも適用できる。
Q.7
48歳の男性。20歳代で統合失調症を発症し、入退院を繰り返している。発症直後から抗精神病薬を服用している。小刻み歩行や手指振戦がみられるが、日常生活は看護師の介助なしでできる。患者の楽しみは食事やおやつであり、用意された食べ物をとられたくないために口に詰め込み、飲み込むように食べている。最近、食事中に激しくむせるようになってきた。むせる主な原因はどれか。(第95回)
①服薬による咽頭反射の低下
②加齢による生理的変化
③貧困妄想による過食
④固形食の咀嚼困難
解答を見る
正解:1
- 服薬による咽頭反射の低下
抗精神病薬の副作用として、咽頭(嚥下)反射の抑制がみられる。さらに食べ物を取られたくないために口に詰め込み、飲み込むように食べることで、むせに拍車をかけている。 - 加齢による生理的変化
患者は48歳であり、加齢による嚥下機能の低下はあまり考えられない。 - 貧困妄想による過食
「食べ物を取られる」といった被害的な考えはもっているが、貧困妄想ではない。過食の状態でもない。 - 固形食の咀嚼困難
抗精神病薬の副作用および食べ方の問題であり、固形食の咀嚼困難ではない。
抗精神病薬の効果、副作用について見直す。
Q.8
19歳の男性。大学生。両親と兄の4人家族。1か月前から自室で独語をしながら片脚跳びをしている。母親に注意されると「『これをやめたら人生ゲームに乗り遅れる。やめたらおまえの負けだ』という声が聞こえてくる」と言い、夜間も頻繁に行っていた。母親が早く寝るように言うと、殴りかかろうとしたこともあった。次第に、食事や睡眠がとれなくなり、父親と兄に伴われ精神科病院を受診した。父親と精神保健指定医とに説得され入院の勧めに応じた。入院形態はどれか。(第98回)
①措置入院
②任意入院
③医療保護入院
④緊急措置入院
解答を見る
正解:2
- 措置入院
精神保健指定医2名の診察の上での強制入院(措置入院)ではない。自傷他害のおそれもない。 - 任意入院
医師、父親に説得され、本人の同意での入院となったため、任意入院に該当する。 - 医療保護入院
本人の同意による入院であるため、父親(家族)の同意による医療保護入院ではない。 - 緊急措置入院
精神保健指定医の診察ではあるが、緊急的に強制入院させる状態ではない。自傷他害のおそれはない。
入院形態について確認する。
Q.9
次の文を読み問題1に答えよ。
54歳の女性。統合失調症により外来治療中であったが、幻覚妄想状態が悪化したため入院した。入院後2か月が経過し状態は安定してきた。最近、担当看護師に「何でいつも私だけがあなたに薬のことばかり言われなければならないの。薬はもう嫌よ。あなたが私を悪くさせているのよ」と被害的な発言をするようになった。患者への最初の声かけで適切なのはどれか。(第96回)
①「きちんと薬を飲んでください」
②「何で薬を飲まないのですか」
③「薬を飲んだか確認させてください」
④「薬を飲むと具合が悪くなるのですか」
解答を見る
正解:4
- 「きちんと薬を飲んでください」
薬を飲まされることに対して被害的になっているため、「飲んでください」と言っても拒否される可能性が高い。 - 「何で薬を飲まないのですか」
「何で飲まないのですか」と聞いても、本人が拒否する理由を説明するだけである。 - 「薬を飲んだか確認させてください」
確認を拒否したり、確認時に飲んだふりをする可能性があるので適切ではない。 - 「薬を飲むと具合が悪くなるのですか」
「具合が悪くなるのですか」と飲まない、飲みたくない気持ちに寄り添い、共感することが大切である。
精神障害を抱える患者への援助の視点として、服薬アドヒアランスが重要である。患者の気持ちに寄り添った対応を心がけよう。
Q.10
抗不安薬を服用開始直後の患者で最も注意するのはどれか。(第96回)
①便 秘
②起立性低血圧
③静座不能(アカシジア)
④遅発性ジスキネジア
解答を見る
正解:2
- 便 秘
抗不安薬の中には、副作用として下痢、便秘を起こすものもあるが、起立性低血圧の方が注意の優先度は高い。 - 起立性低血圧
抗不安薬の副作用として、血圧低下(起立性低血圧)、立ちくらみ、めまい、ふらつきなどの副作用がみられる。 - 静座不能(アカシジア)
アカシジアは、錐体外路症状による静座不能症状(座ったままでじっとしていられず、そわそわと動き回るなど)のことである。抗精神病薬の副作用によるものが多い。 - 遅発性ジスキネジア
遅発性ジスキネジアは、抗精神病薬による副作用で、主に口の周り、舌、下顎を中心とした不随意運動である。舌を出したり引っ込めたり、口をもぐもぐさせる、顔をしかめる、眉をひそめるなど常同的な運動を起こす錐体外路症状である。
抗不安薬は、不安、緊張を和らげる薬である。ベンゾジアゼピン系の抗不安薬が代表的である。ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は依存性が高く離脱症状が現れることもある。そのため短期間の服用が望ましいとされている。
Q.11
うつ病に最も関連が強い神経伝達物質はどれか。(第103回追試)
①ドパミン
②セロトニン
③グルタミン酸
④アセチルコリン
⑤γ-アミノ酪酸
解答を見る
正解:2
- ドパミン
統合失調症の陽性症状(幻覚・妄想など)は、基底核や中脳辺縁系ニューロンのドパミン過剰によって生じるという仮説がある。 - セロトニン
三環系抗うつ薬により、セロトニンの再取り込みを阻害している状況を改善することで、抗うつ効果を現すという仮説から、うつ病はセロトニンと関連が強いと考えられている。現在はノルアドレナリンなどの関連からも、抗うつ薬が製造されている。 - グルタミン酸
グルタミン酸は、哺乳類の神経伝達物質として利用し、認知・記憶・学習などの高次脳機能に関与しているとされている。 - アセチルコリン
アセチルコリンは、副交感神経や運動神経の末端から放出され、神経刺激を伝える神経伝達物質である。 - γ-アミノ酪酸
γ-アミノ酪酸は、アミノ酸の1つで、主に抑制性の神経伝達物質として機能している物質である。
うつ病の生物学的成因については、神経伝達物質の関与が示唆されており、なかでもセロトニンやノルアドレナリンは、うつ病の発症に関連する神経伝達物質であるといわれている。
Q.12
認知行動療法で最も期待される効果はどれか。(第103回)
①過去の心的外傷に気付く。
②薬物療法についての理解が深まる。
③物事に対する誤った信念が修正される。
④人間の生きる意味を感じとることができる。
解答を見る
正解:3
- 過去の心的外傷に気付く。
過去の心的外傷について振り返り、気づくことだけでは、認知行動療法の目的である考え方や行動の修正は起こらない。 - 薬物療法についての理解が深まる。
薬の目的、意味、効果や副作用などの薬物療法の理解に関しては、服薬心理教育で行われる。 - 物事に対する誤った信念が修正される。
認知行動療法は、物事に対する誤った信念を修正することで、気持ちが楽になったり、行動を変えていける心理療法である。 - 人間の生きる意味を感じとることができる。
認知行動療法は、人間の生きる意味を感じとることではなく、考え方や行動を修正することが目的である。
認知行動療法は、その人のものの考え方や受け取り方を変えることで、気持ちを楽にしたり、行動を変えていったりする療法である。
Q.13
生活技能訓練〈SST〉について正しいのはどれか。(第105回)
①退院支援プログラムの1つである。
②診断を確定する目的で実施される。
③セルフヘルプグループの一種である。
④精神分析の考え方を応用したプログラムである。
解答を見る
正解:1
- 退院支援プログラムの1つである。
SSTは社会復帰・参加を目指したリハビリテーションプログラムである。 - 診断を確定する目的で実施される。
SSTは診断を目的に行われるプログラムではない。 - セルフヘルプグループの一種である。
SSTは認知行動療法の1つである。セルフヘルプグループ(自助グループ)は、悩みを抱えた人が同様な問題を抱えている個人や家族とともに、当事者同士の自発的なつながりで結びついた集団のことある。 - 精神分析の考え方を応用したプログラムである。
SSTは精神分析の考え方を応用したプログラムではない。SSTは行動療法と社会的学習理論に基づき、患者の認知・学習障害に対応した訓練を実施して、患者の生活技能と対処能力を高めることを目的としている。
生活技能訓練(SST)は、精神に障害をもった人などが社会で生活していくために、対人関係を良好に維持する技能を身につけ、自信を回復し、ストレス対処や問題解決ができるスキルを習得する目的で行われるリハビリテーション技法である。
Q.14
集団精神療法の効果が最も期待できるのはどれか。(第104回)
①過眠症
②躁状態
③薬物依存症
④小児自閉症
解答を見る
正解:3
- 過眠症
患者同士の相互作用が深く関わってくる治療法なので、過眠症は対象にならない。 - 躁状態
躁状態では、個人でも集団でも精神療法を受ける状態にはならない。 - 薬物依存症
薬物依存症の治療には、患者同士の相互作用が治療効果に深く関わる。他の患者と共感できる体験をもつことで、薬物から遠ざかることができる。 - 小児自閉症
小児自閉症は特性として、他者とのコミュニケーションの問題がある。集団の場面に参加できない場合が多いと予測されるため、まずは個人的な対応が効果的である。
集団精神療法とは、参加者の相互作用を利用した精神療法である。作業療法やレクリエーション療法も集団精神療法の1つである。
Q.15
統合失調症の幻覚や妄想に最も関係する神経伝達物質はどれか。(第107回)
①ドパミン
②セロトニン
③アセチルコリン
④ノルアドレナリン
解答を見る
正解:1
- ドパミン
ドパミンは統合失調症の病態や治療に密接に関係し、ドパミン系の活動状態により幻覚・妄想などの症状を起こす。 - セロトニン
セロトニンの代謝は、うつ病や不安症状に大きく関係している。 - アセチルコリン
アセチルコリンは、運動神経の興奮を筋肉に伝えるなどの神経伝達物質として機能している。 - ノルアドレナリン
ノルアドレナリンは、激しい感情や強い肉体作業などで人体がストレスを感じたときに、交感神経の神経伝達物質として放出され、うつ病の発症に関連している。副腎髄質からホルモンとしても放出される。
神経伝達物質のうち、モノアミンのドパミン、セロトニン、アセチルコリン、ノルアドレナリンは脳内に広く分布している。これは精神疾患などの症状の背景や向精神薬の作用を理解するうえで重要である。
Q.16
精神障害者の施設症の予防策として、最も適切なのはどれか。(第101回)
①隔離室の使用を避ける。
②病棟の規則を厳密に決める。
③病棟行事はスタッフが企画する。
④地域住民との交流の機会を増やす。
解答を見る
正解:4
- 隔離室の使用を避ける。
患者の隔離は、本人または周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に行われる。施設症は隔離室の使用ではなく長期入院による障害であるので適当ではない。 - 病棟の規則を厳密に決める。
病棟の規則を厳密に定め、それに適応するように患者を指導することで、患者は地域での柔軟な生活様式に対応できなくなり、長期間の入院生活の中で施設症を起こす可能性がある。 - 病棟行事はスタッフが企画する。
病棟行事は、患者も加わって、患者が興味をもち、楽しんで参加できる行事を企画することが大切である。 - 地域住民との交流の機会を増やす。
病院・病棟の文化の中だけの生活ではなく、地域との交流をすることで、地域に適応しやすくなり、社会復帰・社会参加に向かいやすくなる。
施設症(病)はホスピタリズムともいう。長期入院によって、感情の動きの低下や意欲がなく無為な荒廃した生活を送る状態となる。身辺の不潔なども見られ、現実社会から隔離された生活によって起こるともいわれている。
Q.17
精神科デイケアの目的で最も適切なのはどれか。(第107回)
①陽性症状を鎮静化する。
②家族の疾病理解を深める。
③単身で生活できるようにする。
④対人関係能力の向上を目指す。
解答を見る
正解:4
- 陽性症状を鎮静化する。
精神疾患の陽性症状を沈静化するためには、薬物療法が行われる。 - 家族の疾病理解を深める。
家族の疾病理解を深めるためには、家族が対象の心理教育が行われる。 - 単身で生活できるようにする。
精神科デイケアは最終的には社会参加を目指す活動であるが、単身で生活できることに特化した活動ではない。 - 対人関係能力の向上を目指す。
精神疾患により社会から距離ができた患者に対して、地域で安定した生活をするための対人関係能力の向上も目的の1つである。
精神科デイケアの目的は、社会復帰や再発予防であり、健康的に地域生活を送り、最終的には社会参加を目指す。
Q.18
精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。(第101回)
①交付を受けた者の写真は添付しない。
②交付を受けた者は、住民税の控除が受けられる。
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定されている。
④交付を受けた者の公共交通機関運賃の割引は、全国一律で適用される。
⑤交付を受けた者は、精神障害の状態についての認定を毎年受ける必要がある。
解答を見る
正解:2・3
- 交付を受けた者の写真は添付しない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、平成18年(2006年)10月より写真を貼り付けるようになった。 - 交付を受けた者は、住民税の控除が受けられる。
住民税・所得税・相続税の控除、自動車税などの減免が受けられる。 - 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定されている。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定された障害者手帳である。 - 交付を受けた者の公共交通機関運賃の割引は、全国一律で適用される。
公共交通機関運賃の割引については、JRなど主要交通機関では行われていない。地域・事業者によっては行われている場合がある。 - 交付を受けた者は、精神障害の状態についての認定を毎年受ける必要がある。
手帳の有効期限は、公布日から2年が経過する日の属する月の末日までである。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために公共料金の割引、税金の控除・減免、その他のサービスが受けられる。
Q.19
入院患者の精神科リハビリテーションで適切なのはどれか。(第101回)
①経済的な自立を最終目標とする。
②退院日が決まり次第開始される。
③多職種によるチーム連携が必要である。
④精神疾患に関する地域への啓発は含まれない。
解答を見る
正解:3
- 経済的な自立を最終目標とする。
社会復帰の目的として経済的社会参加も必要ではあるが、すべての患者のゴールではない。地域に適応して生活ができるかが、精神科リハビリテーションの目的である。 - 退院日が決まり次第開始される。
激しい陽性症状が落ち着いた後、なるべく早い時期から行う必要がある。 - 多職種によるチーム連携が必要である。
さまざまな視点から支えられるように、精神保健福祉士や作業療法士などとの多職種連携が必要である。 - 精神疾患に関する地域への啓発は含まれない。
精神障害者が、退院して地域生活に適応するために、地域社会が精神疾患について理解し、受け入れるための啓発活動は大切である。
リハビリテーションとは、疾患により失われた機能を取り戻し、さらに地域社会に復帰していくこと(全人的復権)をめざすものである。
Q.20
修正型電気けいれん療法について正しいのはどれか。(第107回)
①保護室で行う。
②全身麻酔下で行う。
③強直間代発作が生じる。
④発生頻度の高い合併症は骨折である。
解答を見る
正解:2
- 保護室で行う。
呼吸管理などができる治療室で行われる。 - 全身麻酔下で行う。
患者の負担が少ないように、全身麻酔薬を用いて行われる。 - 強直間代発作が生じる。
強直間代発作が起こらないように、筋弛緩薬が用いられる。 - 発生頻度の高い合併症は骨折である。
以前の電気けいれん療法では、強直間代発作による骨折事例が多かったが、現在の修正型電気けいれん療法では防止されている。
電気けいれん療法(ECT)は、頭部に通電を行い、脳に人工的なけいれんを誘発することで治療効果を得る精神神経疾患に用いられる治療法で、特に重症うつ病、薬物治療に効果がみられない統合失調症などに行われる。現在は、体の全身けいれんが起こらないようにするために全身麻酔薬と筋弛緩薬を併用する修正型電気けいれん療法(mECT)が行われている。