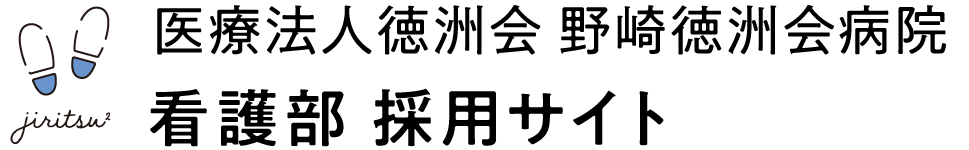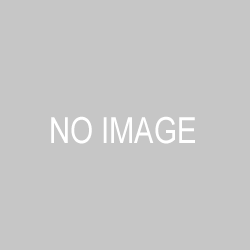Q.1
閉経に近づくと上昇するホルモンはどれか。2つ選べ。(第101回)
①エストロゲン
②プロラクチン
③プロゲステロン
④黄体形成ホルモン<LH>
⑤卵胞刺激ホルモン<FSH>
解答を見る
正解:4・5
- エストロゲン
閉経に近づくと卵巣機能の低下が始まりエストロゲン(卵胞ホルモン)は減少する。 - プロラクチン
プロラクチンの分泌を上昇させるものとして、授乳中の吸啜刺激、エストロゲン、ストレス、ドパミン受容体遮断薬などがある。閉経時にはエストロゲンが低下するため、プロラクチンは上昇しない。 - プロゲステロン
閉経に近づくと卵巣機能の低下が始まりプロゲステロン(黄体ホルモン)は減少する。 - 黄体形成ホルモン<LH>
閉経に近づくと下垂体前葉から分泌される黄体形成ホルモン(LH)は増加する。 - 卵胞刺激ホルモン<FSH>
閉経に近づくと下垂体前葉から分泌される卵胞刺激ホルモン(FSH)は増加する。
閉経とは、卵巣の活動性が次第に消失し、月経が永久に停止した状態をいう。閉経が近づくと卵巣機能の低下によりエストロゲンやプロゲステロンの分泌低下と、フィードバック感受性の低下による黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)の上昇がみられる。
Q.2
女子の第二次性徴に最も関与するホルモンはどれか。(第112回)
①エストロゲン
②オキシトシン
③成長ホルモン
④甲状腺ホルモン
⑤テストステロン
解答を見る
正解:1
- エストロゲン
エストロゲンは卵巣から分泌され、性機能の発現に関与しているため、女子の第二次性徴に最も関与している。 - オキシトシン
オキシトシンは下垂体後葉から分泌され、吸啜や吸引による刺激によって射乳を引き起こす。また、子宮平滑筋を収縮させることで、分娩時には陣痛を促し、分娩後は子宮復古を促進させる。 - 成長ホルモン
成長ホルモンは下垂体前葉から分泌される。思春期に分泌は増えるが、第二次性徴には関与しない。 - 甲状腺ホルモン
甲状腺ホルモンは、甲状腺から分泌され、主に代謝の促進に関与する。 - テストステロン
テストステロンは男子の第二次性徴に関与するホルモンである。
第二次性徴について理解しよう。
Q.3
Aさん(50歳、女性)は、急に体が熱くなったり汗をかいたりし、夜は眠れなくなり疲れやすさを感じるようになった。月経はこの1年間で2回あった。Aさんのホルモンで上昇しているのはどれか。2つ選べ。(第106回)
①エストロゲン
②プロラクチン
③プロゲステロン
④黄体形成ホルモン〈LH〉
⑤卵胞刺激ホルモン〈FSH〉
解答を見る
正解:4・5
- エストロゲン
更年期はエストロゲンが低下する。 - プロラクチン
プロラクチンは上昇しない。 - プロゲステロン
プロゲステロンは上昇しない。 - 黄体形成ホルモン〈LH〉
更年期に卵巣機能が低下し、エストロゲンの減少により視床下部や下垂体へネガティブフィードバックがかかる。そのため、視床下部から分泌されるゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)や下垂体前葉から分泌される黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌が亢進する。 - 卵胞刺激ホルモン〈FSH〉
解説[4]のとおり、卵胞刺激ホルモンの分泌も亢進する。
Aさんの状態は更年期障害と思われる。更年期障害はエストロゲンの低下や心理的・社会的な要因によって起こるといわれている。
Q.4
更年期女性の特徴はどれか。2つ選べ。(第99回)
①平均閉経年齢は55歳である。
②性腺刺激ホルモンの分泌は減少する。
③プロゲステロンの低下によって骨量が減少する。
④閉経後は高脂血症<脂質異常症>の発症が増加する。
⑤更年期症状の出現には社会的・心理的要因が影響する。
解答を見る
正解:4・5
- 平均閉経年齢は55歳である。
日本の平均閉経年齢は約50歳だが、個体差が大きく、早い人では40歳代前半、遅い人では50歳代後半に閉経を迎える。 - 性腺刺激ホルモンの分泌は減少する。
性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)は下垂体前葉から分泌され、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体化ホルモン(LH)がある。更年期ではLHやFSHが増加し、高ゴナドトロピン状態となる。 - プロゲステロンの低下によって骨量が減少する。
更年期女性の骨量の減少に関与するのは、エストロゲンの低下である。 - 閉経後は高脂血症<脂質異常症>の発症が増加する。
エストロゲン欠乏により、閉経後は高脂血症(脂質異常症)の発症が増加する。 - 更年期症状の出現には社会的・心理的要因が影響する。
更年期症状の出現には、身体的な要因だけでなく、社会的・心理的要因が複雑に絡み合い、個人差が大きい。
更年期は生殖期から非生殖期への移行期であり、閉経を挟んだ前後5年間のことである。更年期には加齢に伴う身体的変化がみられ、心理的・社会的にも子どもの自立や親の介護など生活の変化がみられる。
Q.5
更年期女性の骨粗鬆症の予防で適切でないのはどれか。(第96回)
①禁 煙
②有酸素運動
③カロリー制限
④ビタミンDの摂取
解答を見る
正解:3
- 禁 煙
たばこが骨粗鬆症のリスク要因であるため、禁煙は予防として適切である。 - 有酸素運動
運動不足は骨粗鬆症のリスク要因である。運動療法の中でも、強度が中等度のウォーキング、ランニングなどの有酸素運動が予防に有効である。 - カロリー制限
骨粗鬆症の予防として、適切なエネルギー源と栄養素をバランスよく摂取する。痩せや小食(ダイエット)は骨粗鬆症のリスク要因であり、カロリー制限は適切ではない。 - ビタミンDの摂取
骨粗鬆症の予防として、カルシウム・ビタミンD・ビタミンKの摂取を促す。
エストロゲンの低下により骨量は減少するため、更年期女性への骨粗鬆症予防に関する指導は重要である。骨粗鬆症予防について押さえよう。
Q.6
体重6kgの乳児に必要な1日の水分摂取量で適切なのはどれか。(第100回)
①480mL
②600mL
③840mL
④1,200mL
解答を見る
正解:3
- 480mL
計算により、適切ではない。 - 600mL
計算により、適切ではない。 - 840mL
計算により、最も近い840mL が適切である。 - 1,200mL
計算により、適切ではない。
子どもは体全体に占める水分の割合が多く、体重の割に体表面積が大きく不感蒸泄が多いことなどから、成人に比べて体重1kg当たりの1日の必要水分量が多い。乳児の尿量は1日に体重1kg当たり70~90mLで、不感蒸泄は1日に体重1kg当たり50mL である。これを補うため1日に体重1kg当たり120~150mLの水分の摂取が必要である。この値に体重(kg)を掛ければ、1日の必要な水分摂取量が求められる。問題の乳児は体重6kgのため、120~150mL×6kg =720~900mLとなる。
Q.7
標準的な離乳開始の目安はどれか。(第95回)
①生後3か月
②体重7kg
③舌の挺出反射の出現
④咬反射の出現
解答を見る
正解:2
- 生後3か月
生後3か月では早すぎる。 - 体重7kg
体重7kgになるのは生後5~6か月ころであり、離乳開始の目安となる。 - 舌の挺出反射の出現
舌の挺出反射の出現が離乳開始の目安になるのではなく、その反射が弱まることで離乳開始の目安となる。 - 咬反射の出現
咬反射とは、奥歯付近に物が触れると瞬間的に閉口し歯を噛みしめる原始反射である。乳歯の萌出とともに消失していくもので、その出現は離乳開始の目安ではない。
離乳開始の発達の目安は、首のすわりがしっかりして寝返りができる、スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる(舌の挺出反射の減弱)などが挙げられる。時期は生後5~6か月ころが適当である(2019年厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」より)。
Q.8
離乳食の進め方で正しいのはどれか。(第102回)
①開始前からスプーンに慣れさせる。
②開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。
③開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。
④開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。
解答を見る
正解:4
- 開始前からスプーンに慣れさせる。
厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」では、生後5~6か月ころに哺乳反射の減弱によってスプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなるとされている。それ以前に、無理にスプーンに慣れさせる必要はない。 - 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。
離乳開始のときは、アレルギーが生じる可能性の少ない炭水化物(米、パン、じゃがいもなど)の割合を多くする。 - 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。
フォローアップミルクは、離乳食で不足しがちな栄養素を補うものであり、離乳開始ではなく生後9か月以降から利用ができる。必ず与えなければならないものではない。 - 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。
開始から2か月ころの生後7~8か月ころからは、舌でつぶせる固さのものを与える。
離乳の開始とは、なめらかにすりつぶした状態の食物を初めて与えたときをいう。その時期は、生後5~6か月ころが適当である。ただし子どもの発育や発達には個人差があるので月齢はあくまでも目安であり、子どもの離乳食を食べる様子をよく観察しながら進める必要がある。
Q.9
子どもの遊びについて正しいのはどれか。(第102回)
①象徴遊びは3~4歳で最も盛んになる。
②感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。
③並行遊びは6歳以降に増える。
④構成遊びは8歳ころに現れる。
解答を見る
正解:1
- 象徴遊びは3~4歳で最も盛んになる。
象徴遊びは、ごっこ遊びが代表的である。3~4歳で最も盛んになる。 - 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。
感覚運動遊びは、物をなめたり、触ったり、動かしたりして、感覚機能や運動機能をはたらかせる遊びである。これにより感覚器官の発達が促される。乳児期以降に行われ、1歳半ころまでみられる。 - 並行遊びは6歳以降に増える。
並行遊びは、同一の場所で他の子どもと同じように行動しているが、互いに関係なくバラバラに遊ぶものである。2~3歳ころにみられ、6歳以降に増える遊びでない。 - 構成遊びは8歳ころに現れる。
構成遊びは、積み木で何かを作る、絵を描くなどの創造的な遊びであり、2歳ころに現れる。
遊びは、子どもにとって生活そのものであり、生活のすべてが遊びとなっている。また遊びは、知的・運動能力、言語・情緒、想像力・創造力、社会性などの発達を促進させる重要な役割をもち、成長・発達とともに変化する。
Q.10
3歳児の排泄行動の発達に該当するのはどれか。(第109回)
①夜尿をしなくなる。
②尿意を自覚し始める。
③排便後の後始末ができる。
④トイレに行くまで排尿を我慢できる。
⑤遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。
解答を見る
正解:4
- 夜尿をしなくなる。
3歳児は、排泄のコントロールが完全でないため、夜尿をすることがある。 - 尿意を自覚し始める。
尿意を自覚し始めるのは、1歳6か月~2歳である。 - 排便後の後始末ができる。
4~5歳で、排便後の後始末ができる。 - トイレに行くまで排尿を我慢できる。
3歳児では、排尿を我慢し、1人でトイレに行き排尿ができるため、正しい。 - 遊びに夢中になっても排尿の失敗がなくなる。
排尿が自立するのは3~4歳であるが、遊びに夢中になってしまうと失敗することがある。排尿機能の発達に個人差はあるが5~7歳ころに排尿の失敗がなくなる。
排泄の自立は家族が子どもの成長・発達を特に具体的に感じとれるものとして意味が大きい。子どもの標準的な排泄の自立の時期を理解しよう。
Q.11
女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。(第109回)
①9歳で初経が発来する。
②月経開始後に身長の発育が加速する。
③陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。
④性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。
解答を見る
正解:4
- 9歳で初経が発来する。
初経は平均12歳で起こる。小学校6年生で約半数、中学3年生で90%以上が経験する。 - 月経開始後に身長の発育が加速する。
初経の発来は、身長の発育がピークとなる時期の6か月~2年の間に出現するといわれており、月経開始後に身長の発育が加速するわけではない。 - 陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。
陰毛の発生は11歳ころから始まり、乳房の発育は8~13歳で始まるため、陰毛の発生よりも乳房の発育のほうが早い。 - 性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。
月経の開始(初経)は、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)の分泌が亢進し、性腺刺激ホルモンの分泌が高まり卵巣からのエストロゲンの分泌が増すことで起こる。
思春期は小児期から成熟期の移行期で、身長が伸び、体重や体脂肪が増加し、第二次性徴(乳房の発達、陰毛の発生)、性機能の発達がみられる。
Q.12
学童期の肥満で正しいのはどれか。(第111回)
①Kaup〈カウプ〉指数で評価する。
②症候性の肥満がほとんどを占める。
③食事では蛋白質の摂取制限を行う。
④成人期の生活習慣病のリスク因子である。
解答を見る
正解:4
- Kaup〈カウプ〉指数で評価する。
Kaup(カウプ)指数とは、乳幼児の肥満度を評価するための指標の1つであるため、正しくない。 - 症候性の肥満がほとんどを占める。
学童期の肥満は、原発性肥満(単純性肥満)がほとんどを占めるため、正しくない。 - 食事では蛋白質の摂取制限を行う。
食事ではエネルギー量だけでなく栄養素を過不足なく摂取し、バランスのとれた食事にすることが大切である。蛋白質の摂取制限を行うことは、正しくない。 - 成人期の生活習慣病のリスク因子である。
学童期の肥満は、成人期における生活習慣病のリスク因子であるため、正しい。学童期の肥満は、成人期の肥満に移行しやすいため、小児期の生活習慣病との関連が指摘されている。
学童期の肥満は主に肥満度を使って評価する。肥満度は標準体重に対して実測体重が何%上回っているかの指数である。下記の式で計算される。
肥満度=(実測体重-標準体重)÷標準体重×100
Q.13
乳児の事故防止として正しいのはどれか。(第102回)
①直径25mmの玩具で遊ばせる。
②ベッドにいるときはベッド柵を上げる。
③うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。
④屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。
解答を見る
正解:2
- 直径25mmの玩具で遊ばせる。
生後5~6か月ころから、手につかんだものを何でも口に持っていくようになる。乳児の口の大きさはおよそ直径32mmである。それより小さい物は、口に入り、誤飲、窒息につながる恐れがある。 - ベッドにいるときはベッド柵を上げる。
寝返りができないから大丈夫というわけではなく、体をずらして移動することで転落につながる場合がある。新生児期からベッド柵を上げる習慣をつけていくことが、ベッド転落防止となる。 - うつ伏せで遊ばせるときは柔らかい布団を敷く。
柔らかい布団では、子どもが頭を持ち上げることができずに窒息する恐れがある。また、うつぶせ寝は乳幼児突然死症候群の危険因子の1つである。基本的には仰臥位で寝かせるようにする。 - 屋外で遊ばせるときはフード付きの衣服を着用させる。
フード付きの衣服は、遊具などにフードが引っかかり、首がしまって窒息などの事故につながる可能性がある。
子どもの成長・発達段階の特徴からどんな事故が起こりやすいかを整理しておこう。
Q.14
加齢によって高齢者に脱水が起こりやすくなる理由はどれか。2つ選べ。(第102回)
①骨量の減少
②筋肉量の減少
③末梢血管抵抗の増強
④渇中枢の感受性の低下
⑤腎臓のナトリウム保持機能の亢進
解答を見る
正解:2・4
- 骨量の減少
加齢によって起こる脱水は、骨量の減少では起こらない。 - 筋肉量の減少
加齢によって、水分を多く含む筋肉が減少するため、高齢者は脱水になりやすい。 - 末梢血管抵抗の増強
末梢血管抵抗の増強で起こるのではない。 - 渇中枢の感受性の低下
高齢者の脱水の場合、渇中枢の感受性の低下で起こる。 - 腎臓のナトリウム保持機能の亢進
ナトリウム欠乏性(低張性)脱水は、腎臓のナトリウム保持機能の亢進ではなく、減弱から起こる。
高齢者の脱水はよくみられるため、その原因および予防を知っておくことは重要である。加齢によって起こりやすい脱水の原因を、解剖生理学的な要因と身体的特徴から考えよう。
Q.15
加齢による視覚の変化とその原因の組合せで正しいのはどれか。(第103回)
①老 視 ― 毛様体筋の萎縮
②色覚異常 ― 眼圧の亢進
③視野狭窄 ― 散瞳反応時間の延長
④明暗順応の低下 ― 水晶体の硬化
解答を見る
正解:1
- 老 視 ― 毛様体筋の萎縮
老視は加齢による毛様体筋の萎縮や水晶体の弾力低下により起こる。 - 色覚異常 ― 眼圧の亢進
色覚異常は眼圧の亢進では起こらない。眼圧の亢進は緑内障を起こす。 - 視野狭窄 ― 散瞳反応時間の延長
視野狭窄は眼圧が亢進する緑内障などで起こる。 - 明暗順応の低下 ― 水晶体の硬化
明暗順応の低下は、加齢による虹彩の弾力性の低下、視細胞数の減少によるもので、水晶体の硬化とは関係はない。
解剖学的な眼の構造と機能の加齢変化をとらえておく。
Q.16
加齢黄斑変性の症状はどれか。(第109回)
①羞 明
②霧 視
③飛蚊症
④眼圧の亢進
⑤中心視野の欠損
解答を見る
正解:5
- 羞 明
白内障に特徴的な症状であり、誤りである。 - 霧 視
白内障に特徴的な症状であり、誤りである。 - 飛蚊症
加齢による後部硝子体剝離や、疾患による網膜剝離やぶどう膜炎に特徴的な症状であり、誤りである。 - 眼圧の亢進
緑内障に特徴的な症状であり、誤りである。 - 中心視野の欠損
加齢黄斑変性に特徴的な症状であり、正しい。
加齢黄斑変性は加齢により黄斑部の網膜が変性することで起こる。視界の中心に障害が生じ、視力が低下したり物がゆがんで見えたり(変視)する。
Q.17
老人性難聴の特徴はどれか。(第101回)
①耳鳴を伴う。
②伝音性の難聴である。
③低音域が障害される。
④語音の分別能力が低下する。
解答を見る
正解:4
- 耳鳴を伴う。
一般的に、耳鳴は伴わない。 - 伝音性の難聴である。
老人性難聴は、内耳の蝸牛の機能低下によって起こる感音性の難聴である。 - 低音域が障害される。
高音域が障害される。 - 語音の分別能力が低下する。
老人性難聴では、中枢の聴覚刺激の処理能力の低下を伴い語音の分別能力も低下する。
高齢者は内耳にある蝸牛の加齢による機能低下によって高音域の聞き取りや会話の識別が困難になる。このような加齢による聴力の低下が日常生活に支障をきたす場合を老人性難聴という。
Q.18
全身の瘙痒感が強く夜間覚醒することが多い高齢者の援助で適切なのはどれか。(第95回)
①清拭には薬用石けんを用いる。
②化学繊維のパジャマを着用する。
③就寝前に保湿クリームを塗布する。
④室内湿度は30~40%を保つ。
解答を見る
正解:3
- 清拭には薬用石けんを用いる。
薬用石けんは脱脂作用が強いため、皮膚が余計に乾燥し瘙痒感が増強される可能性が高い。清拭には石けんの使用を控えるか、部位を限定して弱酸性の石けんを用いる。 - 化学繊維のパジャマを着用する。
化学繊維(ナイロン・ポリエステルなど)は皮膚に刺激を与えるため、木綿などの柔らかな天然素材を用いる。 - 就寝前に保湿クリームを塗布する。
保湿クリームを塗布することで湿潤環境の保持を助けるため、入浴直後や就寝前の援助が有効である。 - 室内湿度は30~40%を保つ。
室内湿度は50~60%を保つとよい。電気毛布・こたつなどは可能な限り避けるようにする。
高齢者は瘙痒感を訴えることが多く、入眠障害を起こすことも少なくない。
Q.19
老人性皮膚瘙痒症について正しいのはどれか。(第103回)
①感染が原因である。
②高温多湿な夏季に多発する。
③硫黄入り入浴剤の使用で改善する。
④入浴後に保湿クリームの使用を勧める。
解答を見る
正解:4
- 感染が原因である。
老人性皮膚瘙痒症は感染が原因ではない。ドライスキン(皮膚の乾燥)によることが多い。 - 高温多湿な夏季に多発する。
高温多湿な夏季ではなく、日本では乾燥する秋から冬季に多発する。 - 硫黄入り入浴剤の使用で改善する。
疥癬予防に使用する硫黄入り入浴剤の使用は避け、尿素入りのものを用いる。 - 入浴後に保湿クリームの使用を勧める。
皮膚瘙痒症の場合は特に温かいお湯で皮脂が失われ、瘙痒を誘発する。入浴後、角質層に潤いのあるうちに保湿剤・保湿クリームを使用する。
高齢者の皮膚の特徴、加齢からくる瘙痒症の原因とその対策をとらえておく。また高齢者の皮膚疾患では、老人性疣贅(ゆうぜい)や皮膚癌、内臓まで侵される類天疱瘡(るいてんぽうそう)、感染症である疥癬なども覚えておく。
Q.20
腹痛を訴えて入院した認知症高齢者。消灯後に自分の荷物を持ってナースステーションに来た。看護師に「出口はどこ」と聞いてくる。対応で適切なのはどれか。(第97回)
①「ここは病院ですよ」
②「部屋に戻って寝ましょう」
③「今日はここに泊まるのですよ」
④「行きたいところがあるのですね」
解答を見る
正解:4
- 「ここは病院ですよ」
ここが病院であることはわかっていると考えられる。まずは家に帰りたいという本人の思いを聞くことが適切である。 - 「部屋に戻って寝ましょう」
本人の思いを聞かずに部屋へ戻るよう促すことは適切ではない。 - 「今日はここに泊まるのですよ」
解説[1]のとおり、まずは本人の思いを傾聴することが適切である。 - 「行きたいところがあるのですね」
まずは患者の思いを汲み取って、なぜ帰ろうとしているのか傾聴することが適切である。
認知症の程度は提示されていないが、入院による急激な環境の変化や身体的不調で混乱を起こし、帰宅願望が起きていると考えられる。