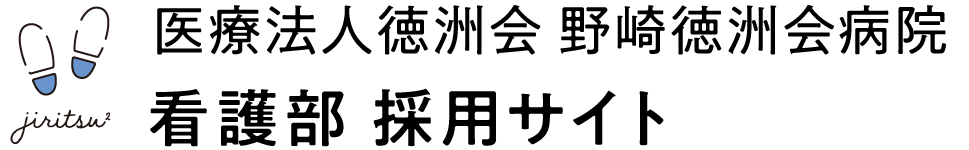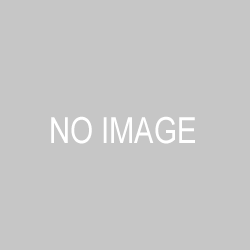Q.1
世界保健機関<WHO>が定義する健康の概念で正しいのはどれか。(第101回)
①万人の有する基本的権利である。
②健康と不健康とは不連続である。
③身体的健康が最も重要である。
④病気や障害がないことである。
解答を見る
正解:1
- 万人の有する基本的権利である。
WHO憲章では「人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権の1つである」としている。 - 健康と不健康とは不連続である。
健康と疾病は明確に区別できるものではなく、連続的な関係である。例えば現代では、疾病に罹患してはいないものの、何らかの身体的な不調を自覚している人が多い。 - 身体的健康が最も重要である。
WHO 憲章において、「健康とは、身体的、精神的ならびに社会的に完全に良好な状態であり、単に病気や虚弱でないことにとどまらない」としている。 - 病気や障害がないことである。
解説[3]のとおりである。
WHO憲章での定義をもとに解答しよう。
Q.2
看護師の対応で適切なのはどれか。(第95回)
①大部屋でポータブルトイレを使用中の患者からナースコールがあったので、インターホンを通して排便の確認をした。
②痛みを伴う検査を受ける患者から痛みの程度を聞かれたので、大した痛みではないと答えた。
③肝生検終了直後の患者から全身清拭の依頼があったが、本日は実施できないことを説明した。
④入院後初めて失禁した患者におむつを使用することを提案した。
解答を見る
正解:3
- 大部屋でポータブルトイレを使用中の患者からナースコールがあったので、インターホンを通して排便の確認をした。
インターホンによる確認は、排泄に関する情報を他の患者に聞かれてしまい、患者には羞恥心が生じると考えられるため不適切である。プライバシーを考慮して、直接病室に出向いて他の患者に聞かれないくらいの声の大きさで聞いたほうがよい。 - 痛みを伴う検査を受ける患者から痛みの程度を聞かれたので、大した痛みではないと答えた。
痛みの感じ方は人によって大きく異なる。看護師にとって「大したことのない痛み」であっても、患者にとっては「強い痛み」である可能性もある。どの程度の痛みが生じるのかを具体的に伝えることが必要である。 - 肝生検終了直後の患者から全身清拭の依頼があったが、本日は実施できないことを説明した。
患者が希望するケアよりも、治療上の安静が優先される場合がある。この場合には患者の希望を断ることも必要である。ただ断るだけでなく、その理由とともに伝えるとよりよい説明となる。 - 入院後初めて失禁した患者におむつを使用することを提案した。
おむつの着用は患者にとって羞恥心だけでなく喪失感、無力感にもつながるため、安易なおむつ着用は避けたほうがよい。なぜ失禁したのかについて詳細に情報収集とアセスメントをして、おむつ以外の失禁防止ケアを行うことが望ましい。
患者とのコミュニケーションは人間関係構築のよい機会でもある。必要な情報を看護師から一方的に伝えるのではなく、患者が理解できるか、患者が不快でないかについても注意深く考え、患者に合わせたコミュニケーションが必要である。
Q.3
判断能力のある成人患者へのインフォームド・コンセントにおける看護師の対応で適切なのはどれか。(第109回)
①患者の疑問には専門用語を用いて回答する。
②今後の治療に関しては医療者に任せるように話す。
③治療方針への同意は撤回できないことを説明する。
④納得ができるまで医師からの説明が受けられることを伝える。
解答を見る
正解:4
- 患者の疑問には専門用語を用いて回答する。
説明・質問への対応などに専門用語を使用しないようにする。医療従事者の説明に患者の理解できない用語や言い回しがあったとき、看護師は質問するよう促したり、補足して説明する役割をもつ。 - 今後の治療に関しては医療者に任せるように話す。
今後の治療に関しては医療者に任せるように話すことは、患者の意思を尊重した自律尊重の原則に反している。 - 治療方針への同意は撤回できないことを説明する。
治療方針への同意はいつでも撤回できることを保証する。撤回できないと説明するのは適切ではない。 - 納得ができるまで医師からの説明が受けられることを伝える。
十分な説明が行われたうえで患者が同意するのがインフォームド・コンセントで、看護師は患者の意思決定を十分に尊重できるように援助する。患者が納得するまで医師の説明が受けられることを伝えるのは適切である。
基本的な内容である。過去問で出題された内容は間違わないようにすれば解ける。
Q.4
良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。(第107回)
①リスボン宣言
②ヘルシンキ宣言
③ジュネーブ宣言
④ニュルンベルク綱領
解答を見る
正解:1
- リスボン宣言
患者の権利に関するWMA(世界医師会)リスボン宣言は1981年に初めて採択され、この第1原則に「良質の医療を受ける権利」が示されている。 - ヘルシンキ宣言
WMA(世界医師会)ヘルシンキ宣言は1964年に初めて採択され、人を対象とする医学研究の倫理原則が示されている。また、1975年の修正でインフォームド・コンセントについて明記された。 - ジュネーブ宣言
ジュネーブ宣言は1948年に採択され、人命尊重を基本理念とした医師の職業倫理が示されている。 - ニュルンベルク綱領
ニュルンベルグ綱領は1947年につくられ、人を対象とした医学研究で遵守すべき基本原則が示されている。
医療では、患者の権利を守るためのさまざまなガイドラインが存在する。ガイドラインの概要と名称を考えながら解答しよう。
Q.5
患者と看護師との協働について適切なのはどれか。(第105回)
①患者が目標達成できるよう支援する。
②治療に関する情報は看護師が占有する。
③看護計画は看護師の視点を中心に立案する。
④ケアは看護師の業務予定に基づき実施する。
解答を見る
正解:1
- 患者が目標達成できるよう支援する。
患者と看護師の協働では、患者と目標を共有し目標を達成できるように支援する。 - 治療に関する情報は看護師が占有する。
患者と看護師の協働では、治療に関する情報は看護師が占有せず、患者に理解できるように説明し共有することで問題解決に役立てる。 - 看護計画は看護師の視点を中心に立案する。
看護計画は看護師の視点中心ではなく、患者の個別性を考えながら立案する。 - ケアは看護師の業務予定に基づき実施する。
ケアは看護師の業務予定ではなく、患者の予定に合わせて実施する。
患者と看護師(医療従事者)の協働とは、患者も医療チームの一員として自分の治療などに参加し行動することである。
Q.6
クリティカルシンキングで適切なのはどれか。(第103回)
①直感的アプローチである。
②主観的情報を重視した考え方である。
③物事を否定的にみる思考過程である。
④根拠を持ち実践することを可能にする。
解答を見る
正解:4
- 直感的アプローチである。
直感的とは勘などを働かせて物事を感覚的にとらえることであり、理論や根拠をもとにじっくり考えるクリティカルシンキングとは異なる。 - 主観的情報を重視した考え方である。
クリティカルシンキングでは主観的情報も必要だが、より理論や根拠を重視しながら思考を進める。 - 物事を否定的にみる思考過程である。
「否定的」とはそのことを「打ち消し、否定する」ことであり、批判的に物事をとらえるクリティカルシンキングの考え方とは異なる。 - 根拠を持ち実践することを可能にする。
クリティカルシンキングでは理論や根拠をもとに考えるため、根拠を持ち実践することが可能である。
クリティカルシンキングとは批判的に考えることをいう。理論や根拠をもとにじっくりよく考え、思考の結果をよりよいものにするために行う。
Q.7
Aさん(56歳、男性)は、脳梗塞の後遺症のためにリハビリテーションをしている。食事中に箸がうまく使えずイライラしている。この状況で看護師が最も連携すべき専門職はどれか。(第105回)
①精神保健福祉士
②社会福祉士
③理学療法士
④作業療法士
解答を見る
正解:4
- 精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障害者に対する相談や援助などに携わる。Aさんは精神障害ではないので、不適切である。 - 社会福祉士
社会福祉士は、日常生活を営むのに問題がある人の相談に対して助言や指導、援助を行う。Aさんは日常生活に問題があるが、その原因は箸が使えないことによるものなので、社会福祉士との連携では解決できない。 - 理学療法士
理学療法士は、基本的動作回復のために理学療法を行う。Aさんはリハビリテーション中なので理学療法士はすでに関わっていると考えられるが、Aさんの問題は腕や指が動かないことではなく「箸がうまく使えないこと」で、理学療法士との連携では解決できない。 - 作業療法士
作業療法士は、生活動作の獲得や社会的適応能力の回復のために作業療法を行う。Aさんは箸をうまく使うことができずにイライラしているので、箸の上手な使い方について作業療法士との連携が必要である。
多職種連携では他の職種の専門的な役割を理解しておくことが必要である。
Q.8
Broca<ブローカ>失語のある患者とのコミュニケーション方法で適切なのはどれか。(第101回)
①五十音表を使う。
②患者の言い間違いは言い直すよう促す。
③言葉で話しかけるよりもイラストを見せる。
④「はい」、「いいえ」で答えられる質問をする。
解答を見る
正解:4
- 五十音表を使う。
発話や書字などの言葉の組み立てがうまくできないため、五十音表を使ってもうまく言葉を表出できない。 - 患者の言い間違いは言い直すよう促す。
言葉の言い間違いがあった場合に再度言い直してもらっても、同じように間違ってしまう可能性が高い。 - 言葉で話しかけるよりもイラストを見せる。
言語理解は可能なので、あえてイラストを用いる必要性は低い。 - 「はい」、「いいえ」で答えられる質問をする。
「はい」、「いいえ」は言葉が短く発語しやすいため、これらの言葉で返答できる質問をするのは適切である。
ブローカ失語は運動性失語ともいい、言語は理解できるが発話や書字に障害のある状態である。
Q.9
コミュニケーションにおけるラポールはどれか。(第100回)
①問題の本質の把握
②言語を用いない表現
③信頼し合う人間関係
④侵されたくない個人の空間
解答を見る
正解:3
- 問題の本質の把握
問題の本質の把握は、ラポールではない。 - 言語を用いない表現
言語を用いない表現は、非言語的コミュニケーション(ノンバーバルコミュニケーション)といい、ラポールとは異なる。 - 信頼し合う人間関係
信頼し合う人間関係はラポールである。 - 侵されたくない個人の空間
侵されたくない個人の空間はパーソナルスペースという。
ラポールとは「信頼・親近感」を意味し、患者と看護師の2者間に信頼し合って感情の交流ができる関係が成立している状態のことである。
Q.10
看護師が患者に行うタッチングについて適切でないのはどれか。(第103回追試)
①患者の価値観や社会的背景を考慮する。
②患者の心理的状態で有効性が異なる。
③看護師と患者の相互作用で成り立つ。
④無意識に触れることである。
解答を見る
正解:4
- 患者の価値観や社会的背景を考慮する。
タッチングは患者の価値観や社会的背景によって受け取り方が異なるため、これらを考慮して行う。 - 患者の心理的状態で有効性が異なる。
タッチングは患者の心理的状態によって効果があったりなかったりするため、心理的状態を考慮して行う。 - 看護師と患者の相互作用で成り立つ。
タッチングは看護師と患者の相互作用で成り立つため、看護師が一方的に行うものではない。 - 無意識に触れることである。
タッチングは何らかの目的のために行うもので、無意識に行うものではない。
タッチングは看護師の手で患者の身体の一部に触れることによる、非言語的コミュニケーションの1つである。患者の不安や緊張の緩和、良好なコミュニケーションなどのために行うことが多い。
Q.11
閉じた質問<closed question>はどれか。2つ選べ。(第101回)
①「乳癌と告げられたとき、どのように思いましたか」
②「ご家族に高血圧症の方はいらっしゃいますか」
③「何時に食事を摂(と)りましたか」
④「どのようにつらいのですか」
⑤「退院後は何をしたいですか」
解答を見る
正解:2・3
- 「乳癌と告げられたとき、どのように思いましたか」
質問に対して自由に答えることができるので、この質問は「開かれた質問」である。 - 「ご家族に高血圧症の方はいらっしゃいますか」
質問に対して「はい」または「いいえ」でしか答えられないので、この質問は「閉じた質問」である。 - 「何時に食事を摂(と)りましたか」
「8時です」、「10時です」など、質問に対して限定した内容でしか答えられないので、この質問は「閉じた質問」である。 - 「どのようにつらいのですか」
質問に対して自由に答えることができるので、この質問は「開かれた質問」である。 - 「退院後は何をしたいですか」
質問に対して自由に答えることができるので、この質問は「開かれた質問」である。
相手が「はい」または「いいえ」や、限定された内容でしか答えられないような質問の仕方を閉じた質問(closed question)、相手が自由に答えられるような質問の仕方を開かれた質問(open end question)という。
Q.12
痛みを訴える患者に対する共感的な対応はどれか。(第103回追試)
①「さっき痛み止めを使ったばかりなので様子を見ましょう」
②「どこがどのように痛いのですか」
③「痛み止めはまだ効きませんか」
④「痛いのはつらいですよね」
解答を見る
正解:4
- 「さっき痛み止めを使ったばかりなので様子を見ましょう」
「様子を見る」ことは患者が求めていることではなく看護師の考えなので、共感的な対応ではない。 - 「どこがどのように痛いのですか」
質問が痛みをアセスメントするための看護師のための情報収集となっており、共感的な対応ではない。 - 「痛み止めはまだ効きませんか」
質問が痛み止めの効果をアセスメントする看護師のための情報収集となっており、共感的な対応ではない。 - 「痛いのはつらいですよね」
看護師が患者の立場に立って、そのつらさを理解しようとしており、共感的な対応である。
共感的な対応では、患者の私的な世界をあたかも看護師自身のものであるかのように感じ取ることが重要である。
Q.13
看護過程で適切なのはどれか。(第95回)
①短期目標の評価は退院時に行う。
②看護計画は患者には開示しない。
③複数の看護問題には優先順位をつける。
④家族に対する指導は計画に含めない。
解答を見る
正解:3
- 短期目標の評価は退院時に行う。
短期目標の評価は退院日に行うのではなく、短期目標に到達すると予測される日を評価日としてあらかじめ設定された日に行う。 - 看護計画は患者には開示しない。
看護計画を開示することでインフォームドコンセントとなり、さらに、患者主体の看護を提供することにもつながる。 - 複数の看護問題には優先順位をつける。
看護問題が複数ある場合には優先順位をつける。これは、患者の安全を守り、看護介入の効果をより大きくすることにつながる。 - 家族に対する指導は計画に含めない。
患者だけでなく家族へも指導をすることで家族が患者へのケアに参加しやすくなり、患者への支援につながる。
看護過程は、情報収集と分析・アセスメント、看護問題の明確化、看護計画の立案、実施、評価の各段階に分けられる、看護実践の基盤となるものである。
Q.14
学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。(第107回)
①小学生へのインフルエンザ予防の指導
②塩分摂取量が多い地域住民への食事指導
③ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導
④3~4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導
解答を見る
正解:3
- 小学生へのインフルエンザ予防の指導
小学生へのインフルエンザ予防の指導は個別性に合わせた指導の必要性は低いため、個別指導よりも集団指導が望ましい。 - 塩分摂取量が多い地域住民への食事指導
塩分摂取量が多い地域住民の食事指導では、個別性に合わせた指導の必要性は低いため、個別指導よりも集団指導が望ましい。 - ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者への生活指導では、患者の生活パターンなどの個別性に合わせた指導が必要であるため、集団指導よりも個別指導が望ましい。 - 3~4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導
3~4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導では、個別性に合わせた指導の必要性は低いため、個別指導よりも集団指導が望ましい。
学習支援では指導の内容によって個別指導と集団指導を使い分ける。
Q.15
個別指導と比較したグループワークを用いた指導の利点はどれか。(第96回)
①参加者個々への助言がしやすい。
②参加者の持つ体験を活用しやすい。
③参加者との深い関係をつくりやすい。
④参加者の目標達成度を評価しやすい。
解答を見る
正解:2
- 参加者個々への助言がしやすい。
グループワークでは複数人が参加するため参加者全員に助言がしやすいという利点がある。参加者個々に助言すると他の参加者が指導を受けることができなくなってしまう。 - 参加者の持つ体験を活用しやすい。
グループワークでは一人の発言を全員で聞き、共有することが容易なため、参加者の持つ体験を活用しやすいという利点がある。 - 参加者との深い関係をつくりやすい。
グループワークでは複数人が参加するため、1対1で構築するような深い関係を築くのには適していない。 - 参加者の目標達成度を評価しやすい。
グループワークには複数人が参加するため、参加者1人ひとりの目標達成度を個別に評価するのは困難である。
グループワークはグループダイナミクスを利用した援助方法で、臨床では問題解決を目的とするグループワークが行われることが多い。
Q.16
看護計画の目標達成の評価で適切なのはどれか。(第96回)
①評価指標を用いて達成度を判定する。
②受持ち看護師の満足度で評価する。
③最初に設定した評価日は変更しない。
④数値化できないものは評価に用いない。
解答を見る
正解:1
- 評価指標を用いて達成度を判定する。
看護計画の目標達成の評価では、看護問題ごとに設定した評価指標への到達度をもとに成果の達成度を判定する。 - 受持ち看護師の満足度で評価する。
看護計画の目標達成の評価では、受持ち看護師の満足度で評価するのではなく、患者からの情報をもとに評価を行う。 - 最初に設定した評価日は変更しない。
評価日は患者の状態に合わせて変更することもできる。 - 数値化できないものは評価に用いない。
患者の「楽になった」などの発言のような数値化しにくい主観的な情報であっても、情報として評価に用いることができる。
看護計画の目標達成の評価では、看護の介入によって患者がどのように変化したのかに着目することで、看護介入の有効性を確認することができる。
Q.17
聴診器を用いた気管呼吸音の聴取部位で正しいのはどれか。(第96回)
①喉頭直下の上胸部(胸骨上部)
②肋骨縁と鎖骨中線の交差部位
③第2肋間と鎖骨中線の交差部位
④第4胸椎正中から肩甲骨部
解答を見る
正解:1
- 喉頭直下の上胸部(胸骨上部)
気管呼吸音の聴取部位は、喉頭直下の上胸部(胸骨上部)である。 - 肋骨縁と鎖骨中線の交差部位
肋骨縁と鎖骨中線の交差部位では肺胞呼吸音が聴取される。 - 第2肋間と鎖骨中線の交差部位
第2肋間と鎖骨中線の交差部位では肺胞呼吸音が聴取される。 - 第4胸椎正中から肩甲骨部
第4胸椎正中から肩甲骨部では肺胞呼吸音が聴取される。
気管呼吸音は粗く大きな音で吸気と呼気の間に短い無音があるのが特徴である。
Q.18
触診が適している観察項目はどれか。(第101回)
①発 疹
②側 弯
③腸蠕動
④声音振盪
解答を見る
正解:4
- 発 疹
発疹の観察では、数や大きさ、形状、色などにについて情報収集が必要となるため、視診が適している。 - 側 弯
側弯の観察は、患者を前傾姿勢として視診で観察することでその有無を情報収集することができる。視診が適している。 - 腸蠕動
腸蠕動は聴診器を腹部に当てて音を聞くことで観察することができる。聴診が適している。 - 声音振盪
声音振盪は看護師の手を患者の背部に当てて患者に発声を促し、その振動を確認する。触診が適している。
触診は看護師の手で患者に直接触れることで身体情報を得る技術である。
Q.19
触診法による血圧測定で適切なのはどれか。(第105回)
①血圧計は患者の心臓の高さに置く。
②マンシェットの幅は上腕全体を覆うサイズを選ぶ。
③150mmHgまで加圧して減圧を開始する。
④加圧後に1拍動当たり2~4mmHgずつ減圧する。
⑤減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値を拡張期血圧とする。
解答を見る
正解:4
- 血圧計は患者の心臓の高さに置く。
血圧計の高さは心臓の高さでなくてもよい。マンシェットを巻く位置は、測定値に影響するため心臓の高さに合わせる必要がある。 - マンシェットの幅は上腕全体を覆うサイズを選ぶ。
マンシェットの幅は、測定する部位の周囲径(上腕で測定する場合は上腕の周囲径)の40%を基準とする。上腕全体を覆うサイズでは、基準よりもかなり大きく、測定値が実際の血圧よりも低く測定されてしまう。 - 150mmHgまで加圧して減圧を開始する。
橈骨動脈の拍動を触れながら、徐々に加圧していき、脈が触れなくなったところから20~30mmHg加圧する。そこから徐々に減圧する。 - 加圧後に1拍動当たり2~4mmHgずつ減圧する。
減圧する速さは1拍動につき2~4mmHgが適切である。 - 減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値を拡張期血圧とする。
減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値は収縮期血圧である。触診法では拡張期血圧を測定することはできない。
触診法での血圧測定は、聴診法で測定するための目安としておおよその値をまず得るために実施するので、収縮期血圧しか測定できないという特徴がある。
Q.20
外来で患者の血液が付着したガーゼを処理する取り扱いで正しいのはどれか。(第103回)
①産業廃棄物
②一般廃棄物
③感染性産業廃棄物
④感染性一般廃棄物
解答を見る
正解:4
- 産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの廃棄物である(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)。 - 一般廃棄物
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物である(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)。 - 感染性産業廃棄物
感染性産業廃棄物とは、医療機関等から排出されるの産業廃棄物のうち、感染性病原体が付着している、または付着している恐れのあるものである。汚泥(凝固した血液)、廃油(アルコール)、廃酸(X線用の薬剤)、廃アルカリ(凝固していない血液)、プラスチック製の器具、ゴム(グローブ)、金属(注射針)、ガラス(アンプルなど)などがある。 - 感染性一般廃棄物
感染性一般廃棄物とは、医療機関等から排出される一般廃棄物のうち、血液等の付着した包帯·脱脂綿·ガーゼ·紙くずなどで、感染性病原体が付着している、または付着している恐れのあるものである。
廃棄物の分類は、一般廃棄物か産業廃棄物であるか、感染性があるかないかで区別する。