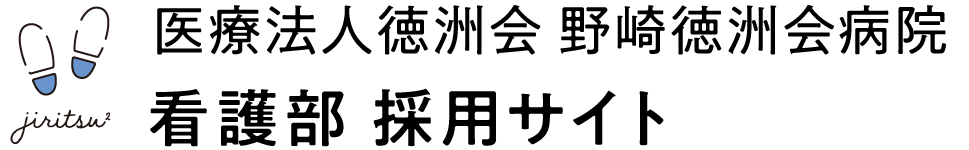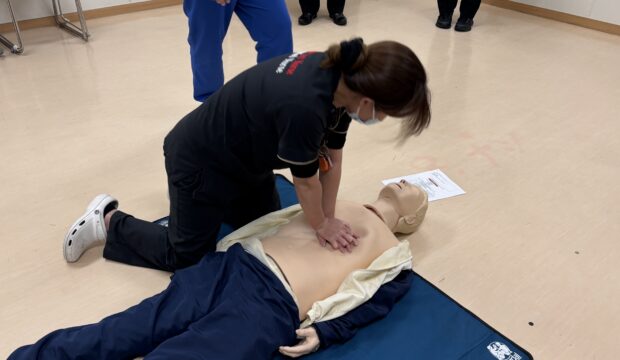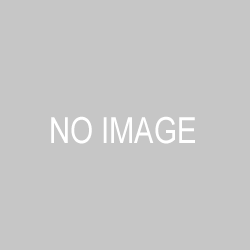Q.1
せん妄を起こしやすいのはどれか。(第99回改変)
①躁うつ病
②摂食障害
③頭部外傷
④人格障害
解答を見る
正解:3
- 躁うつ病
躁うつ病(気分障害)は、感情障害、欲動・行為の障害、思考障害などが主症状であり、せん妄を起こしやすい症状ではない。 - 摂食障害
摂食障害は、大きく分けると神経性無食欲症、神経性過食症に分類され、食べないもしくは食べた後に自発嘔吐、緩下薬の服用、過食と絶食の繰り返しなどにより、体重増加に抵抗する障害である。 - 頭部外傷
せん妄は意識の清明度の障害であり、器質脳疾患や頭部外傷などで起こしやすくなる。 - 人格障害
人格障害(パーソナリティ障害)は、多くの人とは違う反応、行動、考え方などの特性により、生活様式や対人関係様式などの行動パターンの偏りが社会生活の中で大きな障害になり、本人が苦しんでいたり、周りが困る障害である。
せん妄は、見当識障害、意識混濁、錯覚、幻覚、精神運動興奮・不安などによる意識障害である。せん妄は、身体疾患、器質脳疾患で起こることが多い。突然発生して精神機能の変動をもたらすが、通常回復する。
Q.2
脳波検査が診断・治療に有用な疾患はどれか。(第98回)
①うつ病
②てんかん
③総合失調症
④パーソナリティ障害
解答を見る
正解:2
- うつ病
うつ病の診断には使わない。 - てんかん
けいれん発作、意識障害、頭痛などがある場合にてんかんかどうかの検査、てんかんと診断されたときの発作の型、障害の程度などを脳波検査で診断する。 - 総合失調症
統合失調症の診断には使わない。 - パーソナリティ障害
人格の障害なので診断には使わない。
精神医学領域での脳波検査は、てんかん、意識障害の症例などに行われる。
Q.3
Aさんは約1年前から覚醒剤を始め、警察が介入して入院した。Aさんは「覚醒剤を吸引すると気持ちよくなるし、疲れなくなるので止められませんでした」と言う。
Aさんの薬物に対する状態はどれか。(第103回追試)
①依 存
②乱 用
③急性中毒
④慢性中毒
解答を見る
正解:1
- 依 存
Aさんは覚醒剤の使用を繰り返した結果、快楽のために止めたくても止められない依存状態にある。 - 乱 用
乱用は覚醒剤のような精神作用物質を不適切に使用しているが、耐性や離脱といった依存に満たない状態である。 - 急性中毒
覚醒剤の急性中毒の主な症状として、震え、不安、興奮、幻覚、けいれんなどの中枢神経症状、体温・血圧上昇、排尿障害、幻覚・幻聴、錯覚などがある。Aさんに現在このような症状はみられない。 - 慢性中毒
覚醒剤の慢性中毒の症状として、空虚感、悲哀感、社会的ひきこもりを伴う感情鈍麻、フラッシュバック、性格変化などが混在する。Aさんに現在このような症状はみられない。
覚醒剤などの精神作用物質(アルコールを含む)は薬物依存を起こしやすいとともに急性中毒や精神障害(健忘、認知障害、精神病状態)が残る場合もある。薬物依存とは「薬物の作用による快楽を得るために、有害であることを知りながらその薬物を続けて使用せずにいられなくなった状態」である。
Q.4
知覚障害はどれか。(第103回)
①幻 味
②離人症
③注察妄想
④観念奔逸
解答を見る
正解:1
- 幻 味
食物に「毒のような味がする」など、実際には本人だけが感じている味覚の幻覚(幻味)は、知覚障害である。被害妄想に関連して起こることがある。 - 離人症
離人症は自己が自分でないような感じ、生きていないような感じなど現実感の喪失が起こる自我状態の異常である - 注察妄想
注察妄想は、実際はそうではないのに他人から見られていると考える思考内容の異常である。 - 観念奔逸
観念奔逸とは、観念が次々に起こり、思考全体のまとまりがなくなる思考過程(思路)の異常である。躁状態で起こりやすい。
幻覚とは実際に存在しない対象を存在するように知覚するものである。幻視、幻聴、幻触、幻臭、幻味、体感幻覚、考想化声などがある。現実感喪失による離人感や錯覚も知覚の異常である。
Q.5
思考の障害はどれか。2つ選べ。(第101回)
①妄 想
②幻 聴
③昏 迷
④連合弛緩
⑤抑うつ気分
解答を見る
正解:1・4
- 妄 想
妄想は誤りであると伝えても、訂正不能な思考内容の異常である。 - 幻 聴
幻聴は、実在しないものが知覚される(聞こえる)障害である。 - 昏 迷
昏迷は、意識はあるのに行動などの意志の発動がなくなった障害である。 - 連合弛緩
連合弛緩は思考過程(思路)の障害であり、話は大体わかるが思考にまとまりがない状態である。 - 抑うつ気分
抑うつ気分は、はっきりした原因がないのに、気分がゆううつになる障害である。
思考の障害には、思考過程(思路)の障害、思考形式の障害、思考内容の障害がある。
Q.6
統合失調症の陰性症状はどれか。(第97回)
①作為体験
②感情鈍麻
③滅裂思考
④被害妄想
解答を見る
正解:2
- 作為体験
作為体験(させられ体験)は、「自分は人の意思で動かされている」という統合失調症の陽性症状のうちの、自我の障害である。自我障害には、「考えを吹き込まれている」という思考吹入、「考えが抜き取られる」という思考奪取などもみられる。 - 感情鈍麻
感情鈍麻は、喜怒哀楽の感情が乏しくなり、周りの状況に無関心になる陰性症状である。 - 滅裂思考
観念が次々に起こり、思考全体のまとまりがなくなる観念奔逸が顕著になると、思考内容がバラバラになる滅裂思考となる。陽性症状の思考障害(思路障害)である。 - 被害妄想
被害妄想は、人から危害を加えられているというような、統合失調症の初期によくみられる陽性症状である。
統合失調症の陽性症状は幻覚、妄想、思考の障害、自我の障害、緊張症状、奇異な行動などであり、陰性症状は精神機能の減少または欠如である感情鈍麻、感情の平板化、意欲・自発性の欠如、動きの緩慢、ひきこもりなどである。
Q.7
Aさん(21歳、男性)は、統合失調症と診断され、入院してハロペリドールの投与が開始された。入院後3日、39.5℃の急激な発熱、発汗、筋固縮および意識障害を認めた。
Aさんの状態で考えられるのはどれか。(第103回)
①昏 迷
②悪性症候群
③てんかん発作
④静座不能〈アカシジア〉
解答を見る
正解:2
- 昏 迷
昏迷とは、意識がはっきりしているのに意思の発動がない状態である。 - 悪性症候群
悪性症候群は、抗精神病薬の過量投与により起こる副作用であり、高熱、意識障害、筋強剛、頻脈や血圧の上昇などの自律神経症状が出現し、適切な処置をしないと死に至る状態である。 - てんかん発作
てんかん発作は、抗精神病薬の副作用とは考えられない。てんかん発作は焦点発作、全般発作に分類されている。発作は大脳ニューロンの異常によって起こるもので、意識障害、けいれん、自動症などの症状を現す。 - 静座不能〈アカシジア〉
静座不能(アカシジア)は、抗精神病薬の副作用ではあるが、設問のような症状は呈さない。錐体外路症状によって起こるアカシジアでは、足のムズムズ感などにより静座ができないような状態が現れる。
抗精神病薬は、主として統合失調症の治療に用いられ、全般的な鎮静効果と抗精神病作用がある。化学構造によって定型抗精神病薬と非定型抗精神病薬があり、ハロペリドールはブチロフェノン系定型抗精神病薬の1つである。錐体外路系の副作用が出やすいとされる。
Q.8
不安が強いうつ病患者への対応で最も適切なのはどれか。(第100回)
①不安の原因を言語化するよう促す。
②不安が強いときは意識的に話題を変える。
③抗不安薬はなるべく使用しない方がよいと伝える。
④病気の治療とともに不安は軽減する可能性があることを伝える。
解答を見る
正解:4
- 不安の原因を言語化するよう促す。
恐怖は対象がある恐れであるのに対して、不安は対象のない恐れであり、その原因について本人も理解できないことがある。したがって言語化することは難しいと考えられる。 - 不安が強いときは意識的に話題を変える。
不安が強いときには、その感情に寄り添い話を聞くなど、受容的に関わる必要がある。 - 抗不安薬はなるべく使用しない方がよいと伝える。
不安が強いときには、それを軽減する効果のある抗不安薬が必要である。 - 病気の治療とともに不安は軽減する可能性があることを伝える。
状態が回復する可能性など、治療の見通しを伝える対応が必要である。
患者の不安に対し、寄り添った対応が必要となる。
Q.9
会社員のAさんは、うつ病の診断で精神科クリニックに通院している。これまでも外来での診察中に、自責的な発言を繰り返していた。ある日、Aさんから外来看護師に自殺念慮の訴えがあった。外来看護師からAさんへの声かけで、最も適切なのはどれか。(第100回)
①「自殺はしてはいけないことです」
②「あまり深く考えすぎないほうがいいですよ」
③「Aさんよりもつらい状況の人もいるのですよ」
④「死にたくなるくらいつらい気持ちでいるのですね」
解答を見る
正解:4
- 「自殺はしてはいけないことです」
自殺念慮の訴えがあった場合にはまず、聞き役に徹して、訴えを受け止めることが重要である。 - 「あまり深く考えすぎないほうがいいですよ」
自殺念慮は、死にたい気持ちが常に頭から離れない状態なので、「深く考えないほうがいい」という対応は役に立たない。 - 「Aさんよりもつらい状況の人もいるのですよ」
Aさんの苦しさは本人しかわからないもので、他者と比較されても解決にはならない。 - 「死にたくなるくらいつらい気持ちでいるのですね」
自殺の訴えに対しては、その訴えを受容的に聞くことが重要であり、自分のことを理解し、助けようとする人かいることを実感してもらうことが必要である。
うつ病では、微小妄想や罪業妄想による自殺念慮が考えられる。うつ病での自殺率は約15%といわれている。症状が最も重症のときよりも、その前後の時期に自殺を実行しやすい。特に回復期に注意が必要である。
Q.10
長期に抗精神病薬を服用している患者の副作用でないのはどれか。(第95回)
①過呼吸
②巨大結腸症
③悪性症候群
④頻 脈
解答を見る
正解:1
- 過呼吸
抗精神病薬の副作用として、過呼吸は明記されていない。 - 巨大結腸症
抗精神病薬の抗コリン作用により、便秘を起こしやすい。そのため巨大結腸症を起こす可能性がある。巨大結腸症は麻痺性腸閉塞に進展することがあるので注意が必要である。 - 悪性症候群
重篤な副作用として、悪性症候群がある。錐体外路症状、発熱、頻脈、意識障害などを起こし、最悪死に至ることもある。 - 頻 脈
抗精神病薬の副作用として頻脈が挙げられる。
抗精神病薬の副作用は細かく問われることもあるため、まとめて覚えておきたい。
Q.11
オランザピン<非定型抗精神病薬>内服中の患者で最も注意しなければならないのはどれか。(第99回)
①高血圧
②高血糖
③高尿酸血症
④高アンモニア血症
⑤高ナトリウム血症
解答を見る
正解:2
- 高血圧
高血圧に最も注意すべきとはいえない。 - 高血糖
高血糖に最も注意しなければならない。 - 高尿酸血症
高尿酸血症に最も注意すべきとはいえない。 - 高アンモニア血症
高アンモニア血症に最も注意すべきとはいえない。 - 高ナトリウム血症
高ナトリウム血症に最も注意すべきとはいえない。
オランザピンは、高血糖を起こすため糖尿病のある人には禁忌である。糖尿病の家族歴、高血糖、肥満などで糖尿病発症リスクの高い人は慎重に用いる必要がある。
Q.12
妄想的な発言を繰り返す統合失調症の患者。腹部を押さえ「お腹の中で何かが暴れている」と看護師に訴えた。患者の顔色は蒼白で、発汗していた。対応で適切なのはどれか。(第96回)
①何も暴れていないと伝える。
②食べすぎではないかと尋ねる。
③患者の了解を得て腹部を触診する。
④処方されている鎮痛薬を服薬させる。
解答を見る
正解:3
- 何も暴れていないと伝える。
妄想的な発言を繰り返す患者ではあるが、「何かが暴れている」という表現で、腹部の違和感、不快感を訴えていると思われるので、それを受け止めなければならない。 - 食べすぎではないかと尋ねる。
食べすぎかもしれないが、顔色が蒼白で発汗もしているので、苦しさを受け止める必要がある。 - 患者の了解を得て腹部を触診する。
妄想的な訴えであるが、身体的な苦しさととらえ、腹部触診をして、苦しさの原因を探る必要がある。 - 処方されている鎮痛薬を服薬させる。
苦しさの原因がわからないので、鎮痛薬の服薬は安易に行えない。
「妄想的な発言を繰り返す」という前提にとらわれすぎず、適切な看護を考えよう。
Q.13
事実に反する内容にもかかわらず、正しいと確信し訂正不可能な思考障害はどれか。(第103回追試)
①妄 想
②思考途絶
③連合弛緩
④観念奔逸
解答を見る
正解:1
- 妄 想
妄想は、思考内容の異常であり、突然不合理な思考が起こり、訂正不能でそれを確信してしまう。 - 思考途絶
思考途絶は、思考の進行が突然中断され思考停止の状態になる。 - 連合弛緩
連合弛緩は、思考過程の異常であり、話は大体わかるがまとまりが悪い状態である。統合失調症にみられる。 - 観念奔逸
観念奔逸は思考過程の異常であり、観念が次々にわき起こり、思路が最初の目標から外れ、思考全体がまとまらない状態であり、躁状態で起こる。
思考の異常には、思考形式の異常と思考内容の異常があり、思考形式の異常は思考過程(思路)の異常と体験の異常に分けられる。
Q.14
意識障害を伴わないてんかん発作はどれか。(第103回追試)
①欠神発作
②強直間代発作
③単純部分発作
④複雑部分発作
解答を見る
正解:3
- 欠神発作
欠神発作では数秒間の意識消失を認めることが多い。 - 強直間代発作
強直間代発作は意識消失を伴う全身性けいれんである。 - 単純部分発作
単純部分発作は意識消失を伴わない。てんかんの国際分類(2010年改訂提案版)では、焦点発作の「意識障害なし」にほぼ相当する。 - 複雑部分発作
複雑部分発作は意識障害を伴う。てんかんの国際分類(2010年改訂提案版)では、焦点発作の「意識障害あり」にほぼ相当する。
てんかんの国際分類(2010年改訂提案版)によると、てんかん発作は全般発作と焦点発作に大別される。1と2が全般発作、3と4は従来の分類名であるが、焦点発作にほぼ相当する。
Q.15
入院患者のせん妄に対する予防的介入で適切なのはどれか。
①可能な限り離床を促す。
②昼間は部屋を薄暗くする。
③家族や知人の面会は必要最低限にする。
④夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。
解答を見る
正解:1
- 可能な限り離床を促す。
早期離床、昼間の覚醒を促し、規則正しい生活を支えることが予防につながる。 - 昼間は部屋を薄暗くする。
照明や音などの過度な刺激は抑える必要はあるが、規則正しい生活をするためにも、昼間は明るく、夜は暗い、日常通りの環境を整えることが大切である。 - 家族や知人の面会は必要最低限にする。
家族や知人の面会の制限をする必要はない。いつも通りの対応を心がける。 - 夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。
睡眠障害がある患者もいるため、夜間睡眠がとれるように日中はなるべく起きているように働きかけることが大切である。
せん妄は、意識混濁・錯覚・幻覚・精神運動興奮・不安などを伴った意識障害で、アルコールなどの中毒、感染症、脳外傷などで出現する。高齢者に多く、また薬の過剰摂取によっても起こることがある。
Q.16
てんかんの患者が強直、間代発作(大発作)を起こし畳の上に仰向けに倒れた。正しい対応はどれか。(第95回改変)
①発作の持続時間を観察する。
②上肢を固定し発作を抑制する。
③舌圧子を口腔内に挿入する。
④頸部を固定し保護する。
解答を見る
正解:1
- 発作の持続時間を観察する。
危険な場所で発作を起こしたときには安全な場所に移動させ、危険物を取り除く。設問では畳の上であるため、ある程度安全であると考えられる。そのうえで発作の継続時間を確認し、発作の様子を観察する。10分以上の発作や発作の繰り返しは要注意である。 - 上肢を固定し発作を抑制する。
呼吸しやすいように、服のボタンやベルトを緩める必要はあるが、発作を抑制しようとしない。 - 舌圧子を口腔内に挿入する。
口腔内に舌圧子や割り箸などを差し込むと口腔内を傷つけたり歯が折れたりする可能性がある。あごを少し挙げて舌を噛まないようにして、口の中には何も挿入しない。 - 頸部を固定し保護する。
安全を確保して、発作が治まるまで見守ることが必要である。
強直・間代発作はてんかんの典型的なけいれん発作であり、意識消失を伴う。大発作ともいう。
Q.17
パニック発作でみられるのはどれか。(第97回)
①便 秘
②強い怒り
③強い予期不安
④間代性けいれん
解答を見る
正解:3
- 便 秘
便秘はみられない。 - 強い怒り
怒りではなく、強い不安を伴う。 - 強い予期不安
パニック発作を起こすと、再び発作が起こるのではないかとのおそれや不安を持ち続ける。これを予期不安という。 - 間代性けいれん
間代性けいれんは、筋肉が収縮と弛緩を規則的に交互に繰り返すけいれんのことをいう。てんかん発作でみられる。
パニック発作とは、思いがけない状況で突然強い不安とともに、動悸、息切れ、手足の震えなどを伴う発作である。
Q.18
向精神薬と副作用(有害事象)の組合せで正しいのはどれか。(第105回)
①抗精神病薬 ― 多 毛
②抗認知症薬 ― 依存性
③抗てんかん薬 ― 急性ジストニア
④抗うつ薬 ― セロトニン症候群
解答を見る
正解:4
- 抗精神病薬 ― 多 毛
多毛は、抗精神病薬ではなく、副腎皮質ステロイド薬の副作用である。 - 抗認知症薬 ― 依存性
抗認知症薬の副作用には、不整脈の一種である徐脈、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、腹痛など消化器症状、激越、錯乱などがある。依存性はない。 - 抗てんかん薬 ― 急性ジストニア
抗てんかん薬の副作用には、発疹などのアレルギー反応、肝機能の低下、白血球減少、脱毛、体重増加、食欲低下、体重減少、発汗低下、歯肉増殖などがある。急性ジストニアはない。 - 抗うつ薬 ― セロトニン症候群
セロトニン症候群は、抗うつ薬などにより脳内セロトニン濃度が過剰になることによって起こる副作用である。選択的セロトニン再取り込み阻害薬などのセロトニン系の薬物(SSRI・SNRI)を服用中に出現する。
向精神薬とは、睡眠導入薬・抗不安薬・抗精神病薬・抗うつ薬・抗躁薬・抗てんかん薬など、精神機能に作用する薬の総称である。さらに、抗うつ薬には、三環系、四環系、SSRI、SNRI、NaSSAなどがある。抗うつ薬は日常生活に大きく支障が出ている中等症や重症の患者には有効であるが、軽症の場合は効果が定かでないため、精神療法、心理教育などを行い、安易に薬を使うべきではないとされている。それぞれの効能や副作用を覚えておこう。
Q.19
強迫症状を持つ患者への看護で適切なのはどれか。(第99回)
①症状の弊害について説明する。
②気にしないように繰り返し話す。
③症状の無意味さについて説明する。
④不安や葛藤のつらさを受け止める。
解答を見る
正解:4
- 症状の弊害について説明する。
弊害について理解していても、止められずに苦しむため適切ではない。 - 気にしないように繰り返し話す。
気にしないようにしても、気にしてしまうことが症状であり、そのことに苦しむため適切ではない。 - 症状の無意味さについて説明する。
症状の無意味さがわかっても解決しないため適切ではない。 - 不安や葛藤のつらさを受け止める。
不安や葛藤などのつらい感情を受け止めることが大切である。
強迫症状(強迫性障害)は、自分の意志に反して何度も考えが出現し、不安や苦痛をもたらし、考えを打ち消そうとするが成功しない。その考えを打ち消すために確認行動を繰り返してしまう。強迫性障害には強迫観念、強迫行為などがある。
Q.20
選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。(第110回)
①パニック障害に対して有効である。
②抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。
③うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。
④抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。
解答を見る
正解:1
- パニック障害に対して有効である。
SSRIは、主にうつ病、うつ状態の治療に使われる抗うつ薬であるが、パニック障害、強迫性障害、社交不安障害、外傷後ストレス障害などにも有効とされている。 - 抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。
SSRIは三環系抗うつ薬に比べ、抗コリン作用による口渇、便秘、排尿障害、眼圧上昇などの副作用が少ない。 - うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。
うつ病は通常6~8週間で症状が改善するが、改善まで長期に及ぶ場合もある。また再燃、再発の頻度が高いため、症状がおさまり治ったと思っても、様子を見ながら投薬を続ける必要がある。 - 抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。
一般的に効果が発現するのに1~2週間程度かかる。少なくとも3~4週間投与を継続して評価する必要がある。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)は、放出されたセロトニンの細胞内への再取り込みを阻害することで脳内のセロトニン濃度を上昇させ、神経伝達をスムーズにし、抗うつ作用および抗不安作用を示す薬である。