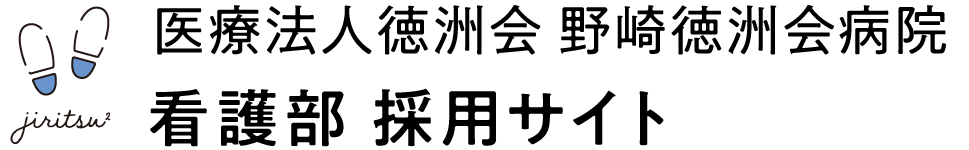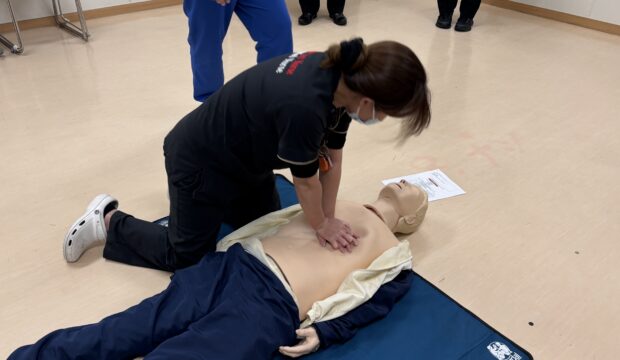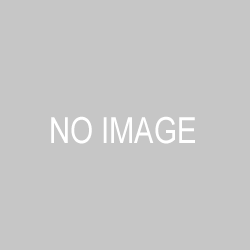Q.1
パルスオキシメータによる経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>測定において、適切なのはどれか。(第101回)
①ネームバンドは外して測定する。
②マニキュアは除去せず測定する。
③末梢循環不全のある部位での測定は避ける。
④継続して装着する場合は測定部位を変えない。
解答を見る
正解:3
- ネームバンドは外して測定する。
パルスオキシメータによるSpO2の測定部位は指先で、ネームバンドを外す必要はない。 - マニキュアは除去せず測定する。
マニキュアはSpO2の測定値を不正確にする原因となるため、除去する。 - 末梢循環不全のある部位での測定は避ける。
SpO2は、機器で脈拍が計測できないと正確な測定値を得られない。末梢循環状態不全がある部位は、機器で脈拍が正確に計測できずSpO2は不正確となる可能性がある。 - 継続して装着する場合は測定部位を変えない。
パルスオキシメータを装着した指先には機器による圧迫が加わるため、継続して装着する場合には測定部位を変えるようにする。
経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は、パルスオキシメータを用いて、非侵襲的に、簡便に測定できる。
Q.2
上部消化管造影を受ける患者への説明で適切なのはどれか。(第98回)
①検査前24時間は絶飲食である。
②発泡剤による噯気は我慢しない。
③検査後は下剤を服用する。
④検査後は白色の排便は異常である。
解答を見る
正解:3
- 検査前24時間は絶飲食である。
飲食物が消化管内に残っていると検査結果に影響するため、検査前12時間から絶飲食となる。24時間前からの絶飲食ではない。 - 発泡剤による噯気は我慢しない。
検査前に消化管を膨らませて消化管辺縁を明瞭にするために発泡剤を内服する。噯気をしてしまうと消化管の膨らみがなくなり検査結果に影響してしまうため、噯気は我慢する。 - 検査後は下剤を服用する。
検査では造影剤として硫酸バリウムを内服する。硫酸バリウムは検査後消化管内に停留しやすく、消化管穿孔などを生じる可能性があるため、検査後は下剤を内服する。 - 検査後は白色の排便は異常である。
造影剤として内服する硫酸バリウムは白色で、排泄される際の排便は白色となるため、異常ではない。
上部消化管造影検査は検査前に造影剤と発泡剤を内服し、さまざまな体位で上部消化管のエックス線写真を撮影する。
Q.3
7時から翌朝7時までの24時間尿を採取する方法として正しいのはどれか。(第102回)
①7時に排尿した尿から蓄尿を始める。
②排便時に出た尿は蓄尿しない。
③翌朝7時に出た尿は蓄尿しない。
④24時間の全尿の一部を採取する。
解答を見る
正解:4
- 7時に排尿した尿から蓄尿を始める。
7時に排尿した尿は、7時より前に腎臓でつくられて膀胱に貯まっていた尿なので、容器には貯めずに捨てる。 - 排便時に出た尿は蓄尿しない。
排便時に出た尿は捨てずに容器に貯めなければならない。このとき、便と尿が混ざらないような工夫が必要である。 - 翌朝7時に出た尿は蓄尿しない。
翌朝7時に出た尿は7時より前に腎臓でつくられた尿なので、捨てずに容器に貯める。 - 24時間の全尿の一部を採取する。
24時間尿を検査に出すときには、検体として尿の一部を採取し、全量を提出することはない。
24時間尿は、開始時間ちょうど以降に腎臓でつくられた尿から容器に貯め始め、終了時間ちょうどに腎臓でつくられた尿まで容器に貯める。
Q.4
気管支鏡検査で正しいのはどれか。(第95回)
①検査前禁食の必要はない。
②体位は左側臥位にする。
③挿入時に息を止めるよう指示する。
④苦痛時の合図を決めておく。
解答を見る
正解:4
- 検査前禁食の必要はない。
気管支鏡検査で使用する咽頭麻酔や、気管内に気管支鏡を挿入した際に嘔気嘔吐を生じる可能性がある。吐物による窒息や誤嚥を防ぐために、検査前日の就寝時から禁食・検査前2~3 時間から絶飲食とすることが多い。 - 体位は左側臥位にする。
気管支鏡検査は仰臥位で行う。上部消化管内視鏡検査は左側臥位で行う。 - 挿入時に息を止めるよう指示する。
挿入時の息止めは必要ない。肺の組織を採取する場合には息止めが必要となる場合がある。 - 苦痛時の合図を決めておく。
気管支鏡の挿入中は患者は声を出すことができない。そのため、手を挙げるなど、苦痛時の合図をあらかじめ決めておく必要がある。
気管支内視鏡は患者の侵襲が大きい検査である。検査について正しく理解することが、患者に安全な看護を提供することにつながる。
Q.5
午前9時に経静脈性腎盂造影を受ける予定の患者が、検査直前に以下のように話した。
検査を延期すべきなのはどれか。(第100回)
①今朝8時に朝食を食べた。
②2日前に造影CTを受けた。
③最終月経開始から10日目である。
④昨夜、腹痛のため鎮痛薬を服用した。
解答を見る
正解:1
- 今朝8時に朝食を食べた。
造影剤によるアレルギー反応によって生じる嘔吐や、嘔吐による誤嚥・窒息を防ぐため、朝食は摂取すべきではない。よって、朝食を食べた場合は検査を延期すべきである。 - 2日前に造影CTを受けた。
2日前の造影CTは、経静脈性腎盂造影に影響しない。 - 最終月経開始から10日目である。
最終月経開始から10日目であっても、経静脈性腎盂造影には影響しない。 - 昨夜、腹痛のため鎮痛薬を服用した。
腹痛のために昨夜服用した鎮痛薬は、経静脈性腎盂造影に影響しない。
経静脈性腎盂造影(IVP)は、静脈から注射した造影剤が腎臓、腎盂、尿管、膀胱に流れていく様子を、X線写真で撮影する検査である。
Q.6
心電図検査における肢誘導はどれか。2つ選べ。(第108回)
①Ⅰ
②V1
③V2
④V3R
⑤aVR
解答を見る
正解:1・5
- Ⅰ
I誘導は肢誘導である。 - V1
V1誘導は胸部誘導である。 - V2
V2誘導は胸部誘導である。 - V3R
V3Rは胸部誘導である。右側誘導といわれ、右室の異常発見に有用である。 - aVR
aVR誘導は肢誘導である。
標準12誘導心電図は、双極誘導と単極誘導に分けられ、双極誘導としてはⅠ、Ⅱ、Ⅲ誘導、単極誘導としては肢誘導(aVR、aVL、aVF誘導)と胸部誘導(V1~V6誘導)が用いられる。
Q.7
血液検査で抗凝固剤が入っている採血管を使用するのはどれか。(第103回)
①血球数
②電解質
③中性脂肪
④梅毒抗体
⑤交差適合試験
解答を見る
正解:1
- 血球数
採血後の血液をそのまま放置すると血液は凝固してしまう。凝固によって、血球数が数えられなくなってしまうため、血球数検査(血算:血球数算定検査)の採血管には、凝固を防ぐための抗凝固剤が入っている。 - 電解質
電解質検査の採血管には抗凝固剤は入っていない。 - 中性脂肪
中性脂肪検査の採血管には抗凝固剤は入っていない。 - 梅毒抗体
梅毒抗体検査の採血管には抗凝固剤は入っていない。 - 交差適合試験
交差適合試験の採血管には抗凝固剤は入っていない。
採血管にはその後の検査に影響しないよう、さまざまな薬品が入っている。
Q.8
皮内注射の実施方法で適切なのはどれか。(第97回)
①注射針は23Gを用いる。
②刺入角度は0度に近くして刺す。
③針を約10mm刺入する。
④抜針後その部位をマッサージする。
解答を見る
正解:2
- 注射針は23Gを用いる。
皮内注射では26~27Gの注射針を用いる。 - 刺入角度は0度に近くして刺す。
刺入角度は皮膚に対してほぼ水平、0度に近くにして刺す。 - 針を約10mm刺入する。
針の刺入深度は2~3mmとする。10mmでは針が表皮を突き抜けて出てきてしまったり、真皮の深い位置に進んでしまう恐れがある。 - 抜針後その部位をマッサージする。
皮内注射は成分をゆっくりと体内に吸収させる必要がある。吸収を早めてしまうため、マッサージはしない。
皮内注射はツベルクリン反応やアレルゲンテストで行われる注射法の1つである。
Q.9
静脈血採血の部位として選択してよいのはどれか。(第101回)
①左鎖骨下静脈から中心静脈栄養を実施している人の左上肢
②右乳房切除術でリンパ節郭清をした人の右上肢
③左上肢に透析シャントがある人の左上肢
④右手背で輸液をしている人の右上肢
解答を見る
正解:1
- 左鎖骨下静脈から中心静脈栄養を実施している人の左上肢
左鎖骨下静脈から投与されている中心静脈栄養は、心臓を経由して全身に送り出される。左上肢の静脈から採血する場合、中心静脈栄養は検査に影響しない程度に希釈されていると考えられる。 - 右乳房切除術でリンパ節郭清をした人の右上肢
乳房切除術でリンパ節郭清をした側の腕を駆血すると、リンパのうっ滞を生じることがあるため避ける。 - 左上肢に透析シャントがある人の左上肢
透析シャントがある側の腕を駆血したり採血のために穿刺するとシャントへの負担となりシャント閉塞の原因ともなるため避ける。 - 右手背で輸液をしている人の右上肢
右手背で輸液をしている人の右上肢から採血をする場合、右上腕を駆血する必要がある。右上腕を駆血すると、静脈圧が上昇して輸液が逆流する可能性があるため避ける。
採血では駆血や穿刺によって患者に悪影響がないかどうかを判断する必要がある。
Q.10
検査の目的と採尿方法の組合せで正しいのはどれか。(第106回)
①細菌の特定 ― 中間尿
②腎機能の評価 ― 杯分尿
③肝機能の評価 ― 24時間尿
④尿道の病変の推定 ― 早朝尿
解答を見る
正解:1
- 細菌の特定 ― 中間尿
中間尿は、尿中の細菌を特定するための採尿法である。中間尿は排尿のし始めの尿を捨て、排尿の中間あたりの尿を集める採尿方法である。出始めの尿には尿道口や尿道内の細菌が混じっている可能性があるためこのような方法で採尿を行う。 - 腎機能の評価 ― 杯分尿
杯分尿は、排尿の前半2/3と後半1/3を別々の容器に採尿する方法である。前半の尿は尿道の病変、後半の尿は後部尿道、前立腺、膀胱の病変を検査するために用いる。 - 肝機能の評価 ― 24時間尿
24時間尿は、24時間に排尿された尿をすべて貯め(蓄尿)その一部を検査する。腎機能検査で用いられる採尿方法である。 - 尿道の病変の推定 ― 早朝尿
早朝尿は、早朝起床時に採尿する。飲食や運動の影響を受けにくいため、定量検査や沈渣検査で用いられる。
尿検査にはさまざまな採尿方法があり、検査の目的によって使い分けられている。
Q.11
全血の検体を25℃の室内に放置すると低下するのはどれか。(第104回)
①血 糖
②乳 酸
③遊離脂肪酸
④アンモニア
解答を見る
正解:1
- 血 糖
血液中の細胞がエネルギーとして血糖を消費するので、血糖は低下する。 - 乳 酸
血液中の細胞がエネルギーとして血糖を消費すると、乳酸が産生される。よって、乳酸は増加する。 - 遊離脂肪酸
血液中の中性脂肪はリパーゼによって分解され、その結果産生される遊離脂肪酸は増加する。 - アンモニア
血液中のアンモニアは赤血球からのアンモニア遊離や血漿中のアミノ酸の加水分解などにより、増加する。
全血とは採血した血液そのもののことをいう。
Q.12
真空採血管を用いる採血で正しいのはどれか。(第103回追試)
①ホルダーに真空採血管を装着してから刺入する。
②真空採血管はホルダーを固定したまま取り替える。
③ホルダーに真空採血管を装着した状態で抜針する。
④使用したホルダーは消毒して再使用する。
解答を見る
正解:2
- ホルダーに真空採血管を装着してから刺入する。
刺入前に真空採血管をホルダーに装着してしまうと採血管内の陰圧がなくなり、刺入後に静脈血を吸引できなくなってしまう。 - 真空採血管はホルダーを固定したまま取り替える。
ホルダーには注射針が装着されているため、採血開始後はホルダーをしっかり固定したまま真空採血管の交換を行う。 - ホルダーに真空採血管を装着した状態で抜針する。
ホルダーに真空採血管を装着したまま抜針すると、採血管内の血液が逆流してしまう恐れがあるため、真空採血管をホルダーから外した後に抜針する。 - 使用したホルダーは消毒して再使用する。
注射針はもちろん、ホルダーにも血液が付着している可能性があるため、使い回しはせず単回使用(使い捨て)とする。
真空採血管を使用した採血はシリンジでの採血に比べて手技が複雑で、血管刺入の確認ができないが、一度に複数の採血管への採血ができるという特徴がある。
Q.13
上部消化管内視鏡検査について適切なのはどれか。(第107回)
①2時間前から絶飲食とする。
②前投薬には筋弛緩薬を用いる。
③体位は左側臥位とする。
④終了直後から飲食は可能である。
解答を見る
正解:3
- 2時間前から絶飲食とする。
胃や十二指腸内に残存する食物は内視鏡の観察では邪魔になるため、検査前12時間は絶食とする。 - 前投薬には筋弛緩薬を用いる。
前投薬では胃内を観察しやすくするための消泡剤を内服し、内視鏡が挿入しやすいように薬剤で咽頭に麻酔を行う。強い苦痛が予測される場合は鎮痛薬や鎮静薬を使用することもある。 - 体位は左側臥位とする。
体位は胃内容物が逆流しにくい左側臥位とする。 - 終了直後から飲食は可能である。
終了直後は咽頭部の麻酔が残っているので、飲食すると誤嚥の可能性が高い。麻酔の効果が切れるまでは絶飲食とする。
上部消化管内視鏡は口や鼻から内視鏡カメラを挿入して咽頭から食道、胃、十二指腸までを観察する検査である。観察だけでなく治療に用いることもある。
Q.14
採血の際、血液が凝固するのを防ぐために試験管にクエン酸の結晶を入れておくことがある。クエン酸によって血液から除かれるのはどれか。(第108回)
①トロンビン
②プラスミン
③カルシウムイオン
④ナトリウムイオン
⑤フィブリノーゲン
解答を見る
正解:3
- トロンビン
トロンビンはクエン酸では除去されない。 - プラスミン
プラスミンはクエン酸では除去されない。 - カルシウムイオン
クエン酸で血中のカルシウムを除去して抗凝固作用を示す。 - ナトリウムイオン
ナトリウムイオンはクエン酸では除去されない。 - フィブリノーゲン
フィブリノーゲンはクエン酸では除去されない。
採血管には、採血後の血液の変化で検査や測定値に影響が出ないように、あらかじめ薬剤が封入されている場合がある。採血後の血液をそのまま放置すると血液は凝固してしまう。凝固によって、血球数が数えられなくなってしまうため、血球数検査(血算:血球数算定検査)の採血管には、凝固を防ぐための抗凝固剤が入っている。
Q.15
穿刺と体位の組合せで正しいのはどれか。(第98回)
①胸腔穿刺 ― 腹臥位
②腹腔穿刺 ― 半坐位
③腰椎穿刺 ― 仰臥位
④骨髄穿刺 ― 砕石位
解答を見る
正解:2
- 胸腔穿刺 ― 腹臥位
胸腔穿刺は半座位または起座位で行う。 - 腹腔穿刺 ― 半坐位
腹腔穿刺は仰臥位または半座位(ファウラー位)で行う。 - 腰椎穿刺 ― 仰臥位
腰椎穿刺は側臥位で、膝を抱えて背中を丸めた姿勢で行う。 - 骨髄穿刺 ― 砕石位
骨髄穿刺は採取部位によって仰臥位や側臥位、腹臥位で行う。砕石位では行わない。
胸腔穿刺、腹腔穿刺、腰椎穿刺、骨髄穿刺はすべて医師が行い、看護師は介助を行う。患者を適切な体位にするのは看護師の役割である。
Q.16
クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する方法で適切なのはどれか。(第109回)
①同じ指で24時間連続で測定する。
②マニキュアをしたままで測定する。
③装着部位に冷感がある場合は温める。
④指を挟んだプローブはテープで固定する。
解答を見る
正解:3
- 同じ指で24時間連続で測定する。
クリップ式は圧迫が強く、まれであると報告されているがパルスオキシメータに使われているLED(発光ダイオード)の光によって低温熱傷が起こる可能性がある。同じ指で8時間以上測定しないように注意する。 - マニキュアをしたままで測定する。
マニキュアがLED(発光ダイオード)の透過光を吸収するため測定値に誤差が生じやすい。マニキュアのない手指で測定する。 - 装着部位に冷感がある場合は温める。
装着部位の冷感は末梢循環不全を表すので、測定誤差を避けるために温めてから測定する。 - 指を挟んだプローブはテープで固定する。
クリップ式はテープで固定する必要はない。テープの固定は循環不全の原因となるほか、パルスオキシメータに使われているLED(発光ダイオード)の光による熱が逃げにくくなり低温熱傷のリスクが高くなる。
パルスオキシメータは患者に侵襲を与えず簡便に使用できる。正しい使い方をきちんと覚えておこう。
Q.17
成人の腸骨の骨髄穿刺で適切なのはどれか。(第102回)
①穿刺前6時間は絶食とする。
②穿刺は仰臥位で行う。
③穿刺時は深呼吸を促す。
④穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。
解答を見る
正解:4
- 穿刺前6時間は絶食とする。
絶食は必要ない。 - 穿刺は仰臥位で行う。
腸骨を穿刺部位とする場合、成人では後腸骨稜が推奨され、その場合は腹臥位で行う。 - 穿刺時は深呼吸を促す。
深呼吸を促す理由はなく、通常の呼吸でよい。 - 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。
穿刺後はガーゼをあてて用手圧迫を行う。止血を確認後にガーゼとテープで圧迫固定を行う。
骨髄穿刺は医師が実施するが、その介助の際に必要な知識が問われている。
Q.18
穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。(第108回)
①胸腔穿刺 ― 胸骨体第2肋間
②腹腔穿刺 ― 剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点
③腰椎穿刺 ― 第1・2腰椎間
④骨髄穿刺 ― 後腸骨稜
解答を見る
正解:4
- 胸腔穿刺 ― 胸骨体第2肋間
胸腔穿刺は貯留した胸水の除去や気胸の脱気などを目的に行う。穿刺部位は胸水除去では中腋窩線上の第5~7肋間、気胸の場合は鎖骨中線上の第2~3肋間の鎖骨中線上である。 - 腹腔穿刺 ― 剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点
腹腔穿刺は貯留した腹水の除去などを目的に行う。穿刺部位は腹直筋外側の側腹部である。 - 腰椎穿刺 ― 第1・2腰椎間
腰椎穿刺は髄液採取や圧測定などを目的に行う。穿刺位置は第3・4腰椎間、第4・5腰椎間の棘突起間である。 - 骨髄穿刺 ― 後腸骨稜
骨髄穿刺は骨髄液採取などを目的に行う。穿刺部位は後腸骨稜や胸骨中央の第2肋間の位置である。
穿刺の目的によって穿刺部位が異なるため、穿刺の目的を考えながら解答しよう。
Q.19
成人の学習の特徴として正しいのはどれか。(第102回)
①学習者のこれまでの経験が資源となる。
②外的動機づけによって学習が促進される。
③自己評価よりも他者による評価が重要である。
④課題中心の学習よりも講義形式による学習の方が効果が高い。
解答を見る
正解:1
- 学習者のこれまでの経験が資源となる。
成人の学習の特徴として、学習者の人生における経験の蓄積が学習のための貴重な資源となることが挙げられる。 - 外的動機づけによって学習が促進される。
成人の学習への動機づけは内的誘因によって促進される。自分が直面している生活に関する問題には取り組みやすい。 - 自己評価よりも他者による評価が重要である。
自分のことは自分で管理できるという自己概念が強まることから、自己評価が重要である。 - 課題中心の学習よりも講義形式による学習の方が効果が高い。
主体的に自己管理学習ができるため、課題中心の学習の方が効果が高い。
成人の学習の特徴として、それまでの人生における経験が学習資源となり、学習するために必要な認知能力も備えているため、自己主導性が強く、学習者主体の自己管理学習ができる。外的動機づけより内的動機づけが学習意欲を高める。
Q.20
成人の健康行動の特徴はどれか。(第96回)
①自尊感情の低下で自己概念が揺らぐ。
②無力感はエンパワメントから生じる。
③自己効力感は失敗体験により培われる。
④アドヒアランスは知識不足が促進要因となる
解答を見る
正解:1
- 自尊感情の低下で自己概念が揺らぐ。
自尊感情の低下から、自己概念が揺らぐことが成人の健康行動の特徴である。 - 無力感はエンパワメントから生じる。
無力感はエンパワメントから生じるのではない。 - 自己効力感は失敗体験により培われる。
自己効力感が培われるのは失敗体験からではない。 - アドヒアランスは知識不足が促進要因となる。
アドヒアランスは、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って自ら行動することをいう。アドヒアランスを高めるためには、患者に必要な知識や技術を提供することが大切であるため、知識不足は抑制要因となりうる。
自尊感情とは、自己に対して肯定的な評価を抱いている状態、自分自身を価値ある存在としてとらえる感覚を指す。