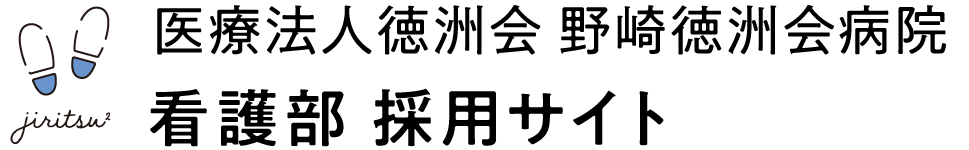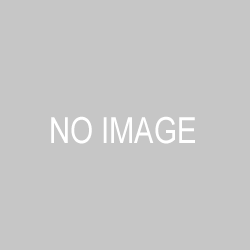Q.1
頭頂葉の障害で出現しやすい症状はどれか。(第95回)
①言葉を流暢に話せなくなる。
②話せるが錯語が多くなる。
③安定して立っていられない。
④手にした物品が閉眼では識別できない。
解答を見る
正解:4
- 言葉を流暢に話せなくなる。
前頭葉のブローカ中枢(運動性言語野)が障害されると、言葉を流暢に話せなくなる。 - 話せるが錯語が多くなる。
側頭葉のウェルニッケ中枢(感覚性言語野)が障害されると、錯語が多くなる。 - 安定して立っていられない。
小脳が障害されると平衡感覚に異常が生じ、安定して立っていられない状態となる。 - 手にした物品が閉眼では識別できない。
頭頂葉の障害では各種の感覚障害が起こり、手にした物品が閉眼では認識できなくなる。
頭頂葉は身体各部からの感覚情報の統合などに関わる領域である。
Q.2
原発緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。(第102回)
①眼球が突出する。
②眼圧が上昇する。
③瞳孔が縮小する。
④視神経が萎縮する。
⑤眼底に出血がみられる。
解答を見る
正解:2・4
- 眼球が突出する。
原発緑内障では眼球が突出することはない。眼球の突出が有名なのはバセドウ病である。 - 眼圧が上昇する。
原発緑内障では眼圧が上昇する。 - 瞳孔が縮小する。
原発緑内障では瞳孔が縮小することはない。 - 視神経が萎縮する。
原発緑内障では視神経が萎縮する。 - 眼底に出血がみられる。
原発緑内障では眼底に出血はみられない。眼底出血を起こす原因は高血圧、糖尿病、脂質異常症、動脈硬化などの全身的な疾患であることが多い。
「緑内障診療ガイドライン」(第5版:2021年)によると、緑内障は「視神経と視野に特徴的変化を有し、通常、眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である」と定義されている。
Q.3
伝音性難聴を起こすのはどれか。(第96回)
①老 化
②鼓膜穿孔
③騒音下での作業
④ストレプトマイシンの使用
解答を見る
正解:2
- 老 化
老化で起きる難聴は老人性難聴で、高い音が聞こえにくくなる感音性難聴が生じる。 - 鼓膜穿孔
鼓膜は音波をとらえて振動し、耳小骨を通して内耳へと伝達する。鼓膜穿孔では音波が振動に変換しにくくなり、伝音性難聴を起こす。 - 騒音下での作業
騒音下での作業で起きる難聴は騒音性難聴で、感音性難聴が生じる。 - ストレプトマイシンの使用
ストレプトマイシンは結核などに用いられる抗菌薬である。ストレプトマイシンの使用で起こる難聴は薬剤性難聴で、感音性難聴が生じる。
伝音性難聴は外耳から中耳に障害があると生じる難聴である。
Q.4
純音聴力検査で正しいのはどれか。(第98回)
①一定の周波数で測定する。
②オージオメータで検査する。
③被検者の応答に関係なく測定できる。
④気導聴力は頭蓋骨から内耳の経路を検査する。
解答を見る
正解:2
- 一定の周波数で測定する。
純音聴力検査ではさまざまな周波数で測定を行う。 - オージオメータで検査する。
純音聴力検査ではオージオメータと呼ばれる測定器具を用いる。 - 被検者の応答に関係なく測定できる。
純音聴力検査では、被検者の応答によって聴力を判定する。 - 気導聴力は頭蓋骨から内耳の経路を検査する。
気導聴力では、外耳から内耳の経路を検査する。頭蓋骨から内耳の経路を検査するのは骨導検査である。
純音聴力検査は気導聴力や骨導聴力を測定する検査である。
Q.5
眼底検査が必要なのはどれか。2つ選べ。(第105回)
①中耳炎
②糖尿病
③麦粒腫
④高血圧症
⑤筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉
解答を見る
正解:2・4
- 中耳炎
中耳炎は鼓膜の状態を確認する必要があり、眼底検査ではない。 - 糖尿病
眼底検査によって、糖尿病の合併症である糖尿病網膜症を発見することができる。 - 麦粒腫
麦粒腫は俗にいう「ものもらい」であり、眼を直接観察して診断する。 - 高血圧症
高血圧では、高血圧網膜症を起こす。眼底検査によって高血圧の網膜血管への影響、動脈硬化の程度、網膜実質の異常を確認する必要がある。 - 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、MRI、針筋電図検査、末梢神経伝導検査、髄液検査、血液検査などの検査を必要とする。
眼底検査は網膜の血管を見る検査で、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症などで眼底に病変が起こるおそれがある。
Q.6
中枢性嗅覚障害の原因となるのはどれか。2つ選べ。(第103回)
①小脳出血
②被殻出血
③慢性副鼻腔炎
④頭部外傷後遺症
⑤Alzheimer〈アルツハイマー〉病
解答を見る
正解:4・5
- 小脳出血
小脳出血は中枢性嗅覚障害の原因とならない。 - 被殻出血
被殻出血は中枢性嗅覚障害の原因とならない。 - 慢性副鼻腔炎
慢性副鼻腔炎は感染が原因で嗅覚障害が起こる。中枢性ではない。 - 頭部外傷後遺症
頭部外傷後遺症は中枢性嗅覚障害の原因となる。 - Alzheimer〈アルツハイマー〉病
アルツハイマー病は中枢性嗅覚障害の原因となる。
中枢性嗅覚障害とは頭蓋内の嗅覚路の障害によって起こる。原因となるのは、頭部外傷による脳挫傷が最も多く、脳腫瘍、脳出血、脳梗塞などが原因となる。
Q.7
先天性の重度視覚障害があるAさんは、早期胃癌の手術目的で入院した。Aさんは妻と2人で暮らしており、自宅ではほぼ自立して日常生活を送っていた。護師のAさんへの入院当日の対応で最も適切なのはどれか。(第100回)
①Aさんの病室は監視モニター付きの個室にする。
②Aさんの病室で食堂やトイレの場所などを説明する。
③起き上がるとスイッチが入るナースコールを設置する。
④CT検査室への移動の際は、看護師が順路を説明しながら一緒に歩く。
解答を見る
正解:4
- Aさんの病室は監視モニター付きの個室にする。
重度の視覚障害があったとしても、監視モニター付きの個室にするのは適切ではない。 - Aさんの病室で食堂やトイレの場所などを説明する。
Aさんの病室で食堂やトイレの場所などを説明しても、Aさんは一人で使用することができない。Aさんと一緒に病室から食堂、病室やトイレに行き、行き方(距離)や使用方法(ボタンの位置など)などを、視覚以外の方法で確認するのが適切である。 - 起き上がるとスイッチが入るナースコールを設置する。
重度の視覚障害があってもナースコールの位置や使用方法を説明することで使用することができる。起き上がるとスイッチが入るナースコールを設置するのは適切ではない。 - CT検査室への移動の際は、看護師が順路を説明しながら一緒に歩く。
普段行く機会の少ない場所に行く場合には看護師の付き添いで説明しながら歩行することが必要である。CT検査室への移動の際に看護師が順路を説明しながら一緒に歩くのは最も適切である。
重度の視覚障害があったとしてもその他のADLが自立している場合には、Aさん自身でできることは自分で行えるように援助することが適切である。
Q.8
網膜剝離で正しいのはどれか。(第95回)
①眼圧上昇
②硝子体混濁
③視野欠損
④瞳孔縮小
解答を見る
正解:3
- 眼圧上昇
網膜剝離では、眼圧上昇は生じない。 - 硝子体混濁
網膜剝離では、硝子体混濁は生じない。 - 視野欠損
網膜剝離では、視野欠損や視力低下などが生じる。 - 瞳孔縮小
網膜剝離では、瞳孔縮小は生じない。
網膜剝離は、感覚網膜層と網膜色素上皮層との間が剝離した状態で、視機能の低下が生じる。
Q.9
緑内障と診断された患者への説明で適切なのはどれか。(第107回)
①「治療すれば視野障害は改善します」
②「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」
③「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」
④「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」
解答を見る
正解:3
- 「治療すれば視野障害は改善します」
緑内障の視野障害は不可逆的であり、進行を抑制することはできるが改善は望めない。治療の目的は進行の予防であることを理解してもらう必要がある。 - 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」
緑内障は主に眼圧の上昇が原因である。 - 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」
緑内障の初期には自覚症状がなく、視野障害を自覚するころには病状が進行していることが多い。 - 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」
眼圧をさらに上げる可能性のある眼瞼のマッサージは避けたほうがよい。特に急激な眼圧上昇によって急性緑内障発作が生じると、数日で失明するリスクがある。
緑内障は40歳代から加齢に伴い増加し、失明原因の第1位となっている疾患である。
Q.10
眼底検査の前処置で散瞳薬を点眼する際の看護で適切なのはどれか。(第104回)
①白内障の既往の有無を確認する。
②羞明が強くなると説明する。
③散瞳薬による症状は30分程度で消失すると説明する。
④眼を閉じた状態で検査室に誘導する。
解答を見る
正解:2
- 白内障の既往の有無を確認する。
散瞳によって眼圧が上昇するため緑内障、狭隅角や浅前房などの眼圧上昇の素因があるかを確認する。 - 羞明が強くなると説明する。
散瞳することによって羞明が強くなる。 - 散瞳薬による症状は30分程度で消失すると説明する。
散瞳薬は点眼して30分程度で散瞳し4~5時間ほど続く。 - 眼を閉じた状態で検査室に誘導する。
散瞳することによって羞明が起こるが、眼を閉じたままにする必要はない。
散瞳薬は点眼して30分程度で散瞳し4~5時間ほど続き、その間まぶしさ(羞明)を感じる。緑内障、狭隅角や浅前房などの眼圧上昇の素因があると、散瞳することによってより眼圧を上昇させる恐れがある。トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩では、高血圧症、動脈硬化症、心臓疾患、糖尿病、甲状腺機能亢進症がある場合に状態が悪化することがある。
Q.11
骨折で正しいのはどれか。(第103回)
①肋骨骨折は第一肋骨に好発する。
②骨折部の腫脹は数時間後が最も強い。
③骨盤骨折では出血性ショックに注意する。
④胸壁動揺は1か所の肋骨骨折によって生じる。
解答を見る
正解:3
- 肋骨骨折は第一肋骨に好発する。
肋骨骨折の好発部位は第5~8肋骨である。 - 骨折部の腫脹は数時間後が最も強い。
骨折部位の腫脹は骨折治癒過程でいう炎症期であり、炎症期は2~3日でピークを迎える。 - 骨盤骨折では出血性ショックに注意する。
骨盤骨折では約2,000mLの出血が予測されることや、骨折によって血管損傷を引き起こすことがあり、ひとたび起こると大量出血を起こす。いずれも出血性ショックを引き起こすことになる。 - 胸壁動揺は1か所の肋骨骨折によって生じる。
胸壁動揺とはフレイルチェストとも呼ばれ、2本以上の連続する肋骨において2か所以上の骨折があることによって生じる。
骨折の全身症状として、神経原性ショックや出血性ショックを起こすことがあるため、意識、呼吸、脈拍、血圧の変化を観察する必要がある。また、局所症状として疼痛、腫脹、変形、異常可動性がある。
Q.12
脊髄造影について正しいのはどれか。(第104回)
①検査前の食事制限はない。
②造影剤を硬膜外腔に注入する。
③検査中のけいれん発作に注意する。
④検査後は水平仰臥位で安静を保つ。
解答を見る
正解:3
- 検査前の食事制限はない。
脊髄造影検査では、ヨード造影剤を使用することでショックを起こすことがある。そのため検査前は食事制限を行う。 - 造影剤を硬膜外腔に注入する。
造影剤はくも膜下腔に注入する。 - 検査中のけいれん発作に注意する。
ヨード造影剤の副作用にけいれん発作があるため注意する。 - 検査後は水平仰臥位で安静を保つ。
脊髄造影検査後は、頭部を挙上した状態で安静にする。水平仰臥位をとると造影剤が急激に頭蓋内に移動し、頭痛や悪心・嘔吐、けいれん発作の原因となる。
脊髄造影検査はくも膜下腔に造影剤を注入し、エックス線で障害を調べる検査である。検査にはヨード造影剤を使用するため、副作用にけいれん発作やショックが起こることもある。
Q.13
麻痺のある患者の関節可動域の評価で正しいのはどれか。(第96回)
①半年に一度実施する。
②測定にはノギスを用いる。
③他動運動による範囲も含める。
④麻痺側拘縮部は健側より大きな値となる。
解答を見る
正解:3
- 半年に一度実施する。
麻痺の変化を観察するためには、半年に一度ではなくより観察頻度を増やしたほうがよいと考えられる。 - 測定にはノギスを用いる。
関節可動域測定では関節角度計を用いる。ノギスは使用しない。 - 他動運動による範囲も含める。
関節可動域には自分で動かすことのできる範囲である自動的関節可動域と、他者などの外力で動かすことのできる範囲である他動的関節可動域がある。 - 麻痺側拘縮部は健側より大きな値となる。
麻痺側の拘縮部位は健側と比較して、関節可動域は健側よりも小さくなると考えられる。
関節可動域(ROM)は関節の運動範囲のことで、関節自体の動きだけでなく腱や靱帯の伸展性などの影響も受ける。
Q.14
他動運動による関節可動域〈ROM〉訓練を行うときの注意点で適切なのはどれか。(第106回)
①有酸素運動を取り入れる。
②等尺性運動を取り入れる。
③近位の関節を支持して行う。
④痛みがある場合は速く動かす。
解答を見る
正解:3
- 有酸素運動を取り入れる。
有酸素運動は全身を動かすような運動で取り入れる方法で、1つの関節を動かす関節可動域訓練では取り入れることができない。 - 等尺性運動を取り入れる。
等尺性運動とは関節を動かさずに筋収縮をする運動であり、関節の動きを伴う関節可動域訓練では取り入れることができない。 - 近位の関節を支持して行う。
近位の(体幹に近い)関節を支持することで、目的の関節を動かすことができる。遠位の関節を支持すると、目的の関節を動かすことができない。 - 痛みがある場合は速く動かす。
痛みがある場合に速く動かすと痛みが増強するため、痛みがある場合にはゆっくり動かす。
他動運動による関節可動域訓練は関節拘縮の予防や改善を目的に実施する。
Q.15
交通事故で腰椎骨折し、第1腰髄節レベルで脊髄を損傷した。受傷当日にみられる症状で可能性が高いのはどれか。(第101回)
①尿 閉
②血圧上昇
③頭蓋内圧亢進
④麻痺性呼吸障害
解答を見る
正解:1
- 尿 閉
膀胱や尿道の括約筋を支配する下腹神経はT11~L2、骨盤神経はS2~4由来で、その上位であるL1の損傷では排尿障害や尿閉が生じる可能性が高いと考えられる。 - 2. 血圧上昇
- 脊髄損傷で血圧上昇が生じる可能性は低い。
- 3. 頭蓋内圧亢進
- 脊髄損傷で頭蓋内圧亢進が生じる可能性は低い。
- 4. 麻痺性呼吸障害
- 麻痺性呼吸障害は、横隔膜運動を支配するC3~5より上位の障害で生じる可能性が高い。L1の損傷では麻痺性呼吸障害が生じる可能性は低い。
脊髄損傷による神経障害はその損傷部位によって、運動麻痺や感覚障害以外にもさまざまな機能障害を引き起こす。
Q.16
Aさん(63歳、女性)は、右変形性股関節症で人工股関節置換術を受けた。脱臼の予防のために行う指導で適切なのはどれか。(第103回)
①和式のトイレを使用する。
②椅子に座るときは足を組む。
③就寝時は患肢を補助具で固定する。
④床に落ちた物を拾うときは右膝をつく。
解答を見る
正解:4
- 和式のトイレを使用する。
和式のトイレは脚が内側に入る姿勢となり、また股関節を深く曲げる姿勢となるため禁忌である。 - 椅子に座るときは足を組む。
足を組む姿勢は、脚が内側に入り脱臼を招くため禁忌である。 - 就寝時は患肢を補助具で固定する。
就寝時の脱臼予防は重要であるが、患肢を補助具で固定する必要はない。良肢位を保つために、枕をはさみ込む側臥位などを指導する。 - 床に落ちた物を拾うときは右膝をつく。
患側が右下肢の場合は、右膝をつくと股関節の屈曲を避けることができる。膝が内側に入ると脱臼しやすくなるため、膝を外側に向ける。
人工股関節置換術後は股関節が脱臼しやすい。後方アプローチで手術した場合は、股関節を曲げて膝を内側に入れるようにねじった姿勢や足を組む姿勢、和式トイレなどの脚が内側に入る姿勢や横座りは禁忌である。前方アプローチで出術した場合は、股関節を深く曲げたり、つま先を外にして、腰を反るような姿勢が禁忌とされている。
Q.17
関節リウマチについて正しいのはどれか。(第101回)
①有病率に男女差はない。
②介護保険法で定める特定疾病に含まれる。
③疾患の活動性は罹患期間が長いほど高い。
④リウマトイド因子は関節リウマチに特異的である。
解答を見る
正解:2
- 有病率に男女差はない。
関節リウマチは女性は男性よりも3~4倍多く、特に40~50歳代の女性に多い。 - 介護保険法で定める特定疾病に含まれる。
関節リウマチは介護保険法で定める特定疾病に含まれる。 - 疾患の活動性は罹患期間が長いほど高い。
疾患の活動性は患者ごとに多彩で罹患期間が長いほど高いとはいえない。 - リウマトイド因子は関節リウマチに特異的である。
リウマトイド因子(RF)は関節リウマチの診断に利用される自己抗体の一種である。関節リウマチ患者のリウマトイド因子陽性率は80%で、疾患がなくても1~5%は陽性となる。特異的とはいえない。
関節リウマチは炎症性の自己免疫疾患で、慢性的な経過をたどるという特徴をもつ。
Q.18
腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。(第106回)
①高齢の女性に多発する。
②診断には MRIが有用である。
③好発部位は第1・2腰椎間である。
④急性期では手術による治療を行う。
解答を見る
正解:2
- 高齢の女性に多発する。
腰椎椎間板ヘルニアは、20~40歳代の男性に多い。 - 診断には MRIが有用である。
腰椎椎間板ヘルニアの診断にはMRIが有用で、ヘルニアの形態や椎間板変性の程度、神経圧迫の程度が観察できる。 - 好発部位は第1・2腰椎間である。
腰椎椎間板ヘルニアの好発部位は下位腰椎で、第4と第5腰椎の間、第5腰椎と仙骨の間に生じやすい。 - 急性期では手術による治療を行う。
腰椎に限らず、椎間板ヘルニアは時間が経過すると自然に消失することもあるので、治療は保存療法が第一選択であり、安静・骨盤牽引・コルセット装着が行われる。
腰椎椎間板ヘルニアは椎間板ヘルニアの中で最も多い。腰痛や片側下肢の放散痛や感覚障害が生じる。
Q.19
Aさん(25歳、男性)は、オートバイの単独事故による交通外傷で救急病院に入院した。外傷部位は左上下肢で左脛骨骨折に対しては長下肢ギプス固定をした。左前腕部は不全切断で、再接着術が行われた。入院後3日、左足趾のしびれと足背の疼痛を訴えた。看護師の観察で適切なのはどれか。2つ選べ。(第106回)
①膝窩動脈を触知する。
②足背の皮膚色を観察する。
③足趾の屈伸運動が可能か確認する。
④Volkmann〈フォルクマン〉拘縮の有無を確認する。
⑤ギプスを数cmカットして浮腫の有無を確認する。
解答を見る
正解:2・3
- 膝窩動脈を触知する。
膝窩動脈はギプスで覆われており、触知できない。コンパートメント症候群の有無を観察するためには動脈触知が有効であるが、ギプス固定位置よりも末梢側の動脈を触知する必要があるため触知するのは足背動脈が正しい。 - 足背の皮膚色を観察する。
コンパートメント症候群では、血流障害によってギプス固定位置よりも末梢側で皮膚色が蒼白となる。足背の皮膚色を観察するのは正しい。 - 足趾の屈伸運動が可能か確認する。
コンパートメント症候群では、血流障害で筋や神経組織の壊死が起こると、ギプス固定位置や末梢側で疼痛や運動麻痺が生じる。よって、足趾の屈伸運動が可能かを確認するのは正しい。 - Volkmann〈フォルクマン〉拘縮の有無を確認する。
フォルクマン拘縮は上肢の骨折で起こるコンパートメント症候群でみられる症状で、示指から小指の第3関節伸展、母指第1関節の屈曲、母指の内転、手関節の屈曲が生じる。 - ギプスを数cmカットして浮腫の有無を確認する。
コンパートメント症候群の浮腫はギプス固定位置や末梢側で生じる。よって、ギプスをカットしなくてもすでに露出している足背などで観察できる。
ギプス固定をしている部位では、固定部位に長時間圧が加わり筋区画(コンパートメント)の内圧が上昇して血流障害や拘縮が生じるコンパートメント症候群が起こることがある。
Q.20
Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb 16.0g/dL、Ht 55%、白血球8,900/μL、CRP 0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(-)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。入院後3日、腹部CTの再検査で脾臓損傷は否定された。また、左膝のMRI検査では、左半月板損傷と確定診断され、自宅療養することとなった。退院準備中のAさんから「ベッドから立ち上がろうとしたら、左膝が曲がったままで伸びない。痛みはそれほどでもないです」と訴えがあった。この時、医師への連絡と同時に看護師が実施することで適切なのはどれか。(第108回)
①作業療法士へ相談する。
②下肢の関節可動域を確認する。
③処方された鎮痛薬を服用させる。
④下肢の徒手筋力テストを実施する。
解答を見る
正解:2
- 作業療法士へ相談する。
作業療法士への相談は適切ではない。 - 下肢の関節可動域を確認する。
Aさんは左膝が曲がったままで伸びないという症状のため、半月板損傷が進行したと考えられる。損傷の程度を調べるために下肢の関節可動域を確認する必要がある。 - 処方された鎮痛薬を服用させる。
痛みはそれほどでもないので、鎮痛薬を服用させる必要はない。 - 下肢の徒手筋力テストを実施する。
半月板損傷では突然筋力が低下するような症状は出ない。よって、下肢の徒手筋力テストを実施するのは適切ではない。
半月板損傷の治療は保存療法と手術療法があり、保存療法では安静や筋力訓練のみで症状が軽減する。